

70年ぶりの抜本改革と言われる改正漁業法が2018年12月に成立し、2020年12月に施行されました。
改正漁業法には、「持続可能性」が初めて目的として記載され、水産資源の評価対象を5年間で50種から200種程度に拡大することが定められました。また、資源管理に効果的な基準として最大持続生産量(Maximum Sustainable Yield; MSY)が導入され、MSYベースを目指した漁獲可能量(Total Allowable Catch; TAC)の管理を推進し、個別漁獲割当量(Individual Quota; IQ)を導入することになりました。国と都道府県の管理責務も規定されています。
資源管理の必要性を訴え続けてきた勝川俊雄先生は、改正漁業法をどうとらえ、日本の漁業を巡る状況にどんな思いを抱いているのか、今の心境を伺いました。(Part 1を読む)
——70年ぶりの抜本改革と言われる改正漁業法についてのお考えをお聞かせください。
海の憲法と呼ばれる国連海洋法条約では、沿岸国に200海里の排他的経済水域を認める一方で、MSYを基準とした水産資源管理を行う義務を課しています。これまで、日本は排他的経済水域を主張しながら、資源管理義務を果たしてこなかったのですが、法改正によって沿岸国の義務である漁獲規制ができるようになりました。
管理義務を怠っていた日本の水産政策について批判をしてきたのですが、政治主導で法改正がなされたことで、行政の姿勢が明確に変わりました。なので、法改正には大きな意味があったと評価しています。政治主導のトップダウンで法改正が行われたことからも、政治が正しい方向性を示すことが大事であることがわかります。
——なぜ、70年間も動かなかった政治が、このたび動いたのかというところが国民からあまり見えません。
そこ見えないですよね。

2014年に『ウェッジ(Wedge)』という、新幹線のグリーン車などにも置いてある雑誌が『魚を獲り尽くす日本人』という水産資源に関する特集を組み、私も寄稿しました。それが地元広島に帰る小林史明という議員の目に留まり、彼は実家で漁業の網をつくる会社の後を継いでいたお兄さんに、「この記事の内容は本当なのか」と尋ねたそうです。
これがきっかけになり、水産業が危機的な状況にあると気がついた小林議員が、何とかしようと動き出し、若手議員を中心に理解者を増やして、漁業法改正の流れをつくっていきました。
日本の民主主義では選挙で選ばれた政治家が方向を決める仕組みになっているので、今回のプロセスはそれが機能したといえます。ただ、国民や業界を巻き込んだ議論を経て、皆が納得した上で方向転換したわけではないので、これから現場の意識を変えるという大仕事をやらないといけません。
——施行されて半年ちょっとですが、だいぶ変わりつつあるのでしょうか。
もちろん、法律を変えたからと言って世の中が180度変わるというものではありません。これまで避けていたものもふくめて、問題は山積みです。問題の先送りをやめて、解決の道筋を模索しだしたことから、短期的に見ればこれまで以上に混乱するかもしれません。でも、それは日本の水産業が生き残るために必要なプロセスなので、応援していきたいと思っています。
——水産資源の問題を啓蒙する「海の幸を未来に残す会」はどんな活動をしているのですか。
漁業法改正に向けて2013年に立ち上げた団体で、SNSなどで活発に活動していた時期もありました。漁業法改正前は、まず、きちんと法改正するのがスタート地点でした。当時は、水産庁も「問題がないから漁獲規制をやらない」と言って法改正に反対していたので、現状では未来がないことを主張してきました。

——これからのアプローチとして、どんなやり方を考えておられますか。
今回の法改正を受けて、水産庁がその法律に沿って前に進もうと努力しているのは外からでも見えます。これまでのように、対決姿勢で問題点を強いトーンで指摘するやり方だと、かえって自分たちがブレーキになりかねないとも考えています。
また、法改正が必要だった時代には永田町や霞ヶ関に働きかける必要がありましたが、今後は未来につながる魚食システムを構築するために、生産と消費の現場を変えていく必要があります。コロナで動きづらい状況が続いていますが、現場に近い場所での活動に軸足を移していくつもりです。
日本の消費者は持続可能性への関心が低い上に、キャンセルカルチャー(※)を好まないので、欧米のようにエコラベル認証を持っていない水産物を市場から追い出そうというアプローチは、市民権を得るのは難しいでしょう。美味しく、楽しく、持続可能性という問題にコミットできるようにしないと、間口は広がらないし、長続きしない気がします。
「あれもダメ、これもダメ」という道徳的な話よりも、むしろ、「持続可能な水産物を楽しく食べて、志のある生産者を応援しよう」というアプローチが良いと考えています。これからも魚を食べ続けるためにどうしたらいいかを消費者と生産者が一緒に考えるような場づくりをしたいですね。
——そうなると、社会問題という切り口ではないということですね。
エシカル消費というような難しいことよりも、単純に漁業の現場を消費者にも知ってもらうのが近道ではないかと思っています。
消費者が生産者と分断されている現状では、消費者は自分の利益だけを考えて、良いものをいかに安く買ってくるかに関心がいくのも仕方が無いでしょう。生産の現場を知って、生産者がいかに手間ひまをかけて、誇りを持って仕事をしているかを知れば、生産者を応援したいと思うようになります。生産現場を知れば、資源の枯渇や流通の問題点なども見えてきます。
だから、まずはつながること。生産者と消費者の接点をつくるような取り組みを今やっています。自分が食べているものを、誰がどうやって生産しているのかを知るのは楽しいものです。そういう機会を増やすことで、当事者意識が高まり、水産物を食べ続けるために、なにかをしたいう気持ちも高まるでしょう。

最近は、自治体と連携をして、消費地と産地を結ぶ教育プロジェクト「さかな大好き!」を行っています。東京の子どもたちが、本物の漁師の話を聞き、本物の魚や漁具にふれて、漁業の現場のことを学んだ後で、産地直送の魚が提供されます。聞く、見る、触る、食べるといった体験を通して、子どもたちには水産業を身近に感じてもらいます。
日本の水産物や漁業者のファンを増やしていくことが、消費者の当事者性を高めて、未来につながる水産業を応援する原動力になると考えています。また、生産者にとっても、若いファンが増えることはやりがいに直結するし、子どもたちに魚を食べ続けてもらうためにも資源や漁業の持続可能性への意識も高まります。
今後は、日本の水産業のファンを増やしながら、生産者と消費者が連携をして、持続可能な水産業を育てていく手伝いをしたいと思っています。
勝川 俊雄
1972年東京都生まれ。東京大学農学部水産学科卒。農学博士。東京大学海洋研究所助教、三重大学生物資源学部准教授を経て、2015年4月より東京海洋大学 産学・地域連携推進機構 准教授。国内外の漁業の現場を回りながら、漁業を成長産業にするための取り組みを続けている。日本水産学会奨励賞、日本水産学会論文賞を受賞。主な著書に、『漁業という日本の問題』(NTT出版)、『魚が食べられなくなる日』(小学館新書)。一般社団法人海の幸を未来に残す会理事。
取材・構成:井内千穂
中小企業金融公庫(現・日本政策金融公庫)、英字新聞社ジャパンタイムズ勤務を経て、2016年よりフリーランス。2016年~2019年、法政大学「英字新聞制作企画」講師。主に文化と技術に関する記事を英語と日本語で執筆。




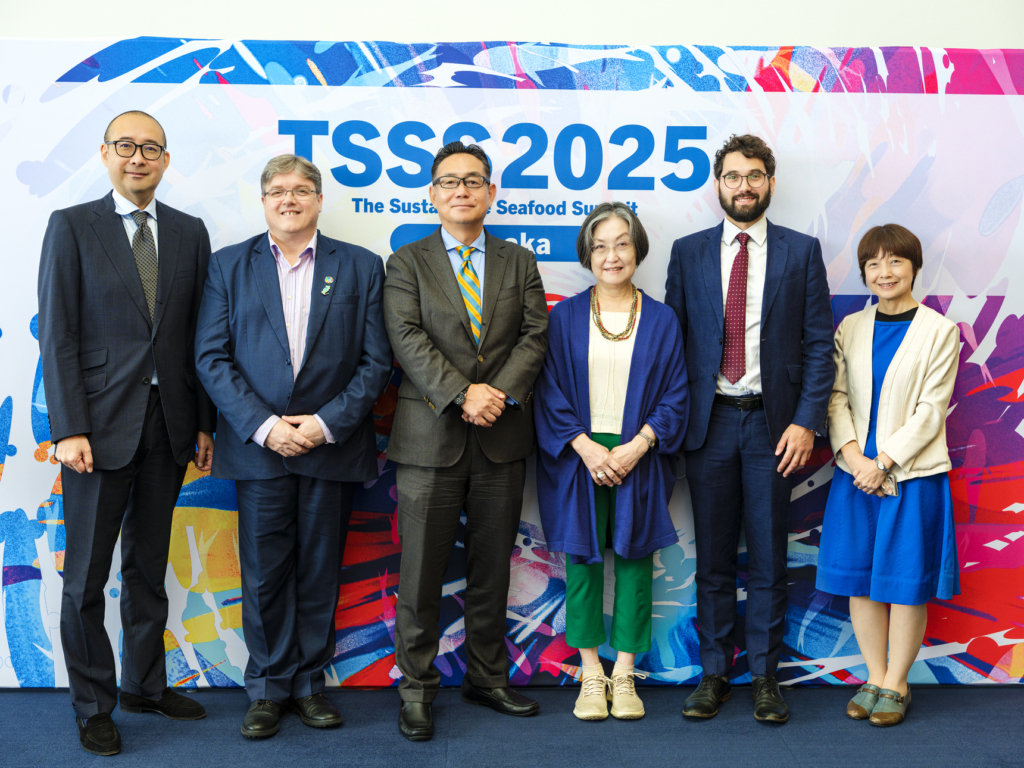














--1024x819.jpg)


































Times-top-banner-1024x609.png)
Times-top-banner-1024x609.png)














































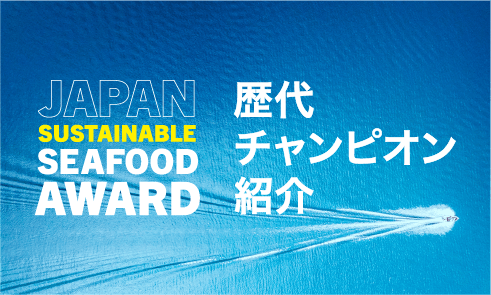
KEY WORD
水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。