

私たちは久しく、海と人の関係を見直す岐路に立っています。
漁獲量の減少、後継者問題、気候変動や国際的な資源管理への対応といった課題は、いずれも長らく水産業界において懸念されてきたものです。これらの複雑な課題を乗り越えるためには、現場に根ざした多様なアクターによる対話と、持続可能な未来を共につくる姿勢が求められています。
2024年2月28日から3月1日、鹿児島県で開催された「第2回水産未来サミット」(フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング、グローバル・オーシャン・ワークス主催)。全国から漁業者、メディア、研究者、NGO、学生など約200名が集い、水産業の現在と未来を多角的に考え、議論を深めた2日間となりました。
現場のリアルな声、世代を超えた対話、そして各地で生まれている新たな挑戦に触れた今、私たちがこの業界の未来に対して何を思い、どう行動していくのかを、今回参加したシーフードレガシーのメンバーから皆さんに現地レポートの形でお届けしたいと思います。

初日のキーノートスピーチでは、東京海洋大学の松井隆宏教授が、日本の漁業が抱える構造的課題を示し、資源評価と漁業統計の分析から、今の水産業が直面する現実を浮き彫りにしました。
日本の漁獲量は1984年をピークに大幅に減少しており、市場価格は上昇しているにも関わらず、燃料や飼料価格の高騰、IUU漁業由来水産物が市場に入る影響で生産金額はピーク時の半分近くまで減り、漁業者の収入は減少しています。
そして年々漁獲の技術が進歩しているにも関わらず、2002年以降は一人当たりの漁獲量が変わっていないというデータは、海の資源そのものが確実に減っていることを指します。
また、世界の漁業生産量は増加し続けている一方で、日本の周りだけ極端に減っているのは、温暖化のせいだけではなくこれまでの資源管理のあり方にも原因があることがわかります。
このことから科学的なデータに基づく資源管理と、流通の透明性を高める仕組みづくりが、現場の日本の水産業において特に重要だと強調しました。
持続可能な水産業の基盤には、現状を正確に捉える「見える化」が不可欠なのです。

その後のパネルディスカッションでは、全国から集まった漁師たちが、それぞれの「挑戦」と「問い」について語りました。
「これまでは海に漁師を合わせてきたが、これからは漁師が海にどう適応するかを考えるべきだ」と語ったのは、北海道から来ていた波心会で刺し網漁を行う林強徳(つよのり)氏。
林氏のもとには、大阪や栃木など全国各地から若者が集まり、実践の場で漁業を学んでいます。彼らは林さんのように、親が漁師という家庭ではありませんが、漁師の仕事に興味を持ち、はるばる北海道まで学びに行っています。
「これまでは、漁師の獲りたい量に海が合わせてくれていた。これからは、漁師が海にどう適応するかを考えるべき」と語る林さんは、産卵時期などは資源を守っていくために漁にでない選択をするといいます。「今の海は獲れるときは獲れるし、獲れないときは獲れない」という現実を受け入れ、変化する海洋環境や資源状況に柔軟に対応する姿勢を大切にされています。
2024年に行われた「東京サステナブルシーフード・サミット」でも漁業全体の若手後継者不足が語られていた通り、日本の漁業就業者の平均年齢は、2022年時点で56.4歳。また同年で約12.3万人*1 の漁業就業者数は、このまま行くと2050年頃には約7万人*2 にまで減少する可能性が指摘されています。
*1 水産庁「図で見る 日本の水産」よりhttps://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/pr/pamph/attach/pdf/index-14.pdf
*2 水産庁「水産政策の改革について」よりhttps://www.jfa.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/attach/pdf/190214-3.pdf
若手漁師不足が心配される中、パネリストの中で最も若かったのが、鹿児島県の野村優一郎氏(海盛水産)です。彼自身は28歳、平均年齢35歳という若いチームで、巻き網や定置網漁業に取り組んでいます。また痩せた魚を逃がすといった形で、資源の持続性にも配慮しています。
そして他にも、漁師を目指す人を増やしたいと語る若手漁師の方がいました。青森県にある尾駮鮮魚団の橋本翔氏は、漁師・買い付け・屋台・音楽フェス主催という多様な肩書きを持ち活動しています。幼稚園での食育授業や、インドネシア人の採用にも積極的に取り組み、「漁業を次世代に“継がせる”のではなく、“継ぎたい”と思われる存在にしたい」と語りました。活動を楽しみながら地域とのつながりをつくっているその背中を見て、憧れる人は多数いるはずです。
また、パネルディスカッションでは能登半島地震の影響で地域の復興のために立ち上がる漁師、消滅可能性都市を立て直すべく、地域に人を呼ぶための施策を地域ぐるみで行っている人々もいました。地域全体を活性化する一つの考え方として、「魚を獲るだけではない“海業(うみぎょう)”という考え方も広まっており、観光や教育、6次産業化を含めた水産業との融合で、新たな可能性を見ている」という声もありました。水産業を“点”ではなく“面”で捉え、地域全体で支えることの重要性が語られ、会場の共感を得ていました。水産業の持続可能性は、漁場だけでなく、地域社会全体の持続可能性と表裏一体なのです。

1日目の夜は、参加者同士の交流を深める懇親会が開かれました。全国各地から参加した漁師から届けられた新鮮な魚介類を囲みながら、思い思いに語り合う時間となりました。

サミット2日目の朝は、ASC認証を取得しているグローバル・オーシャン・ワークスのカンパチ養殖場を訪問しました。同社では、最新の技術を活用した養殖を行っています。また、養殖業で発生する環境負荷への対策や、地元の高校生との連携や地域資源の活用にも力を入れています。

養殖場の見学中に思い起こしていたのは、養殖業を取り巻く経済的課題が浮き彫りになった昨日のパネルディスカッション。特に飼料価格の高騰は深刻で、養殖生産コストが高騰しているからこそ、マーケットは国内だけでなく、高く販売することのできる輸出を拡大する仕組みづくりも必要といった声もありました。
養殖の持続可能性を担保するには、上記のコスト対応を含め、環境インパクト、労働環境、地域との関係性までを含めた取り組みが不可欠です。

2日目の、参加者全員で水産改革の課題とアクションプランを議論した『テーマディスカッション』では、IUU漁業に対するアクション、認証水産物をさらに広めていくためのアクション、など具体的なテーマごとに分かれて話し合いました。その中で実際に漁師の方々と会話した言葉のひとつひとつが、心に深く残っています。そして、海外から輸入されるIUU漁業の水産物はもちろん、日本各地でも起きているIUU漁業を現場で目の当たりにされているというお話を聞いて、きちんと資源管理のために漁をしない時期を作り、お金のためだけでなく環境のことを考えて柔軟に漁をしている漁師が正当に評価されるような仕組みも大切だと感じました。
2日間にわたるサミットを通じて、私が最も印象的だったのは「立場の違いを超えた対話の力」でした。漁師が中心でありながらも、参加者にはNGO、研究者、学生など多様な立場の人々が集まり、多角的な視点からのアイデアや意見が交わされていました。
NGOや研究者が現場の声に耳を傾け、漁業者が科学的データを尊重し、学生など若い世代と漁師が協力して漁業の楽しさを発信する。そうした姿の中に、未来の水産業に必要な“共創”の土壌が確かに育ちつつあることを実感しました。
これまで私は、水産業を政策や企業の取り組みという俯瞰的な視点から捉えてきました。しかし今回の日本の生産現場の方が集まるサミットに初めて行ったことで、漁師の方々の生の声に触れ、制度の先にある“現場のリアル”を深く知ることができました。
なかでも心を動かされたのは、山積する課題に対して悲観するのではなく、前向きかつ楽しみながら解決策を模索しようとする漁師の方の姿でした。たとえば長崎県の対馬にある丸徳水産では、磯焼けや漂着ごみといった環境問題を観光客に知ってもらうため、実際に現場を見学し、原因とされるウニの捌き方を体験するツアーが行われています。「良いところだけでなく、あえてのある部分も見せることが問題提起のきっかけになる」と語っていた姿に、課題を「伝える」ことから始め、共に考え、巻き込んでいこうとする現場の工夫が感じられました。
今もなお、漁業や養殖業は多くの課題を抱えていますが、現場で一番水産物が減っていることを直面し、実感している漁師だからこそ、地域の人々に伝えていくことができるのも同じく漁師です。そのように現場の状況を前向きに変えていく推進力を今後も後押しして行きたいと感じています。

文/シーフードレガシー Comms & Branding Officer 冨塚 由希乃






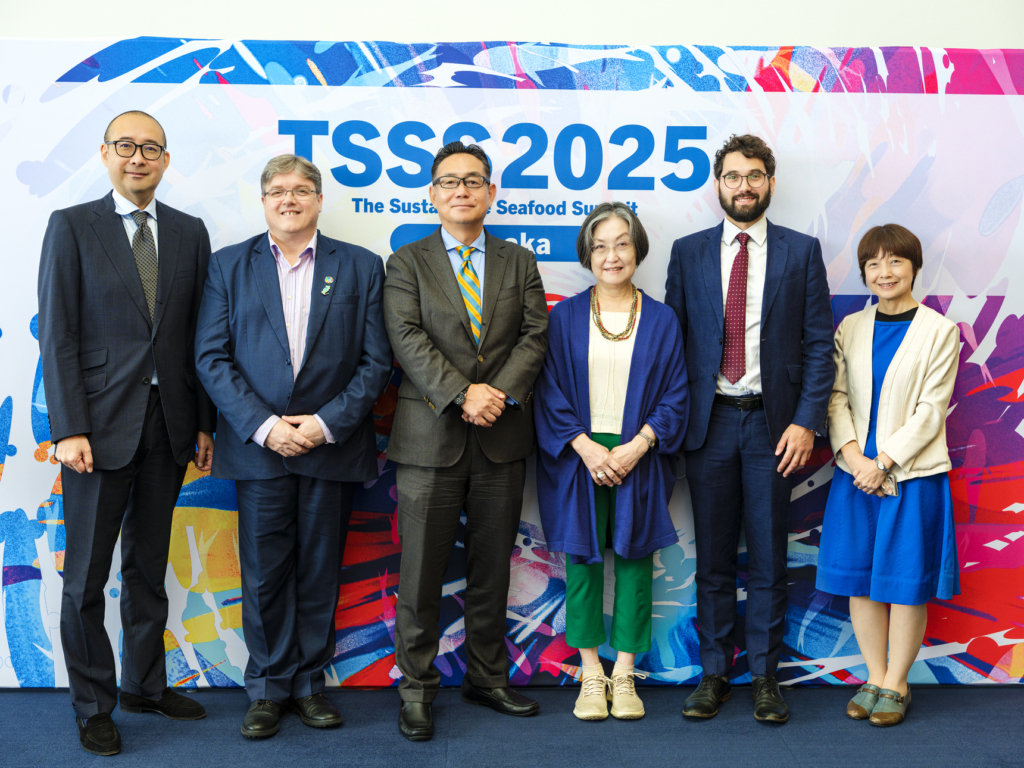














--1024x819.jpg)


































Times-top-banner-1024x609.png)
Times-top-banner-1024x609.png)





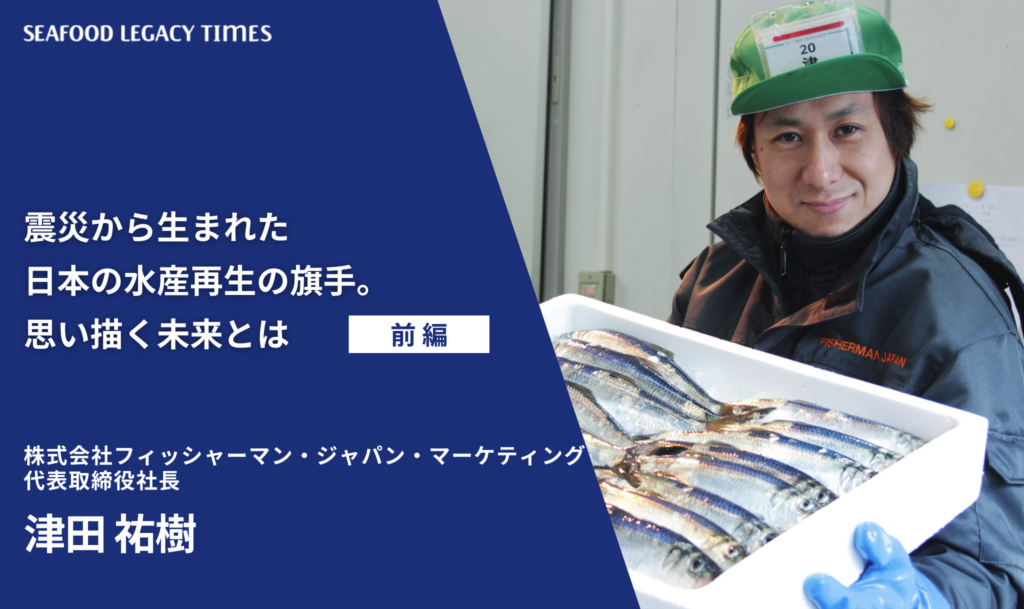























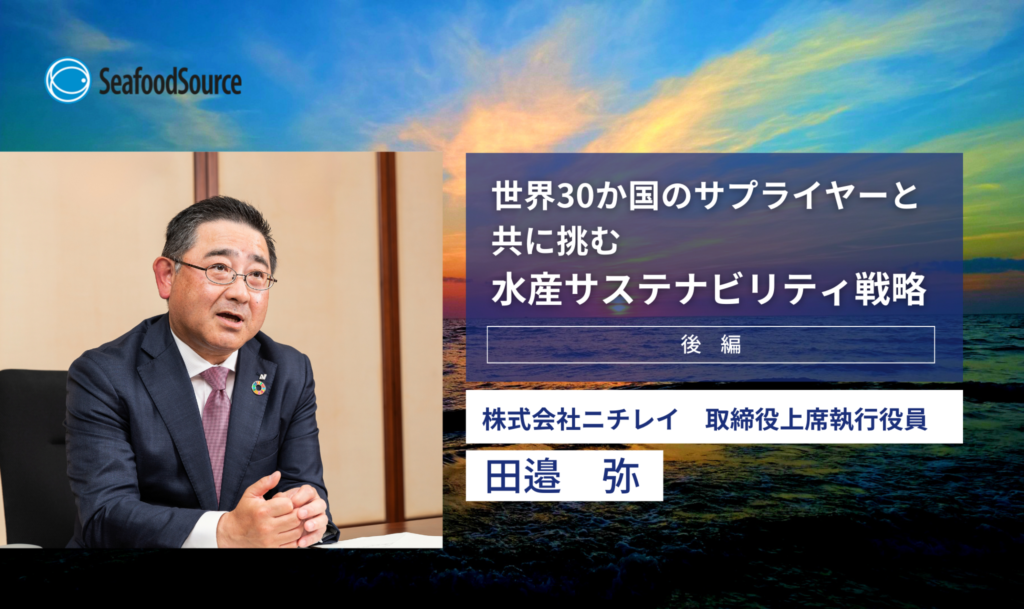
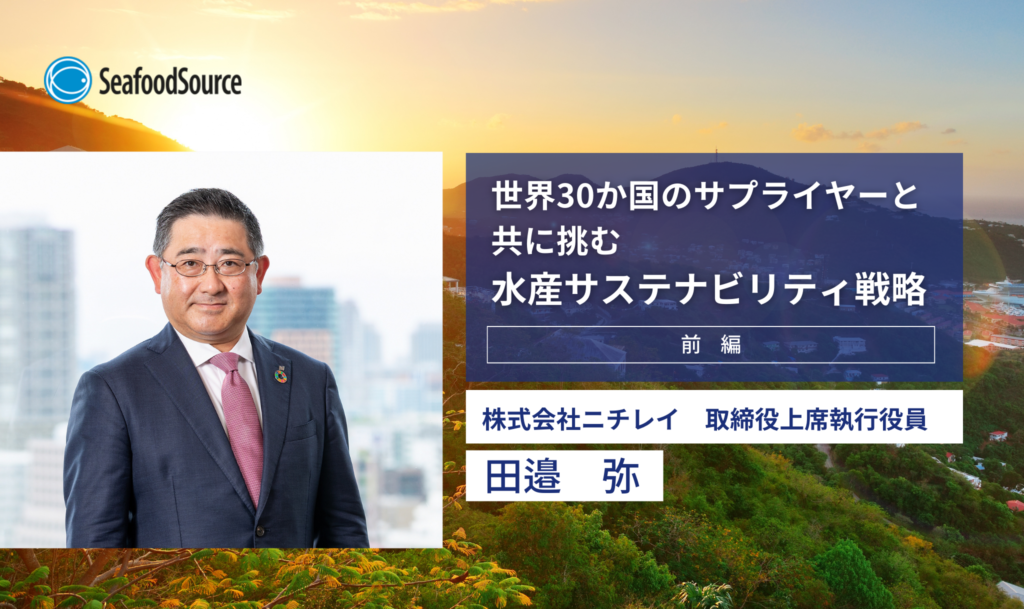










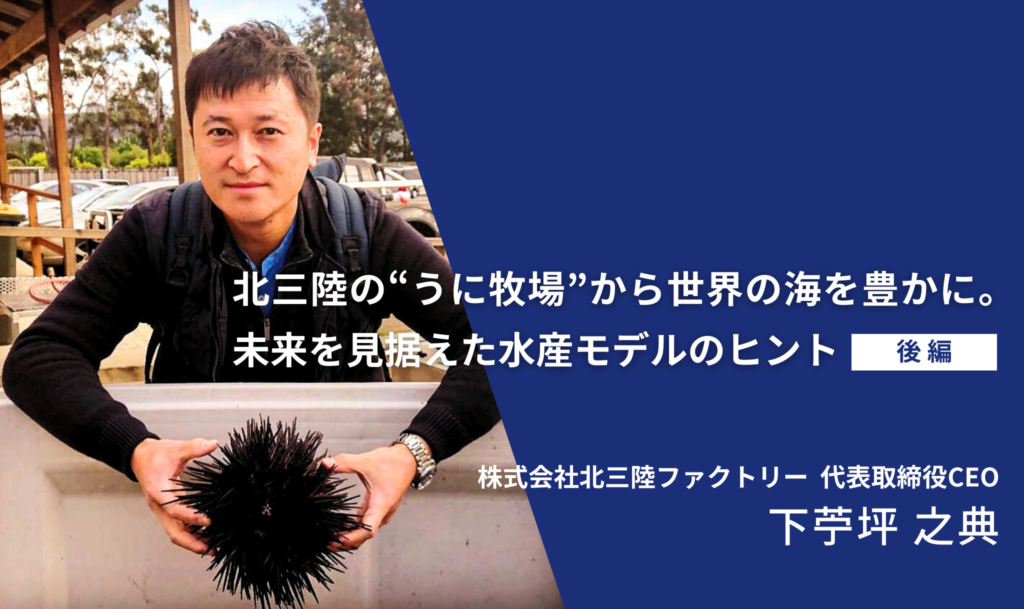


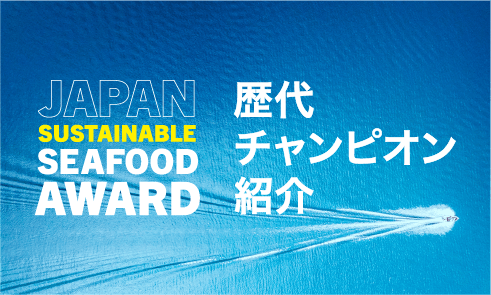
KEY WORD
水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。