

世界銀行が2013年に公開したレポート『2030年までの漁業と養殖業の見通し』*1によると、2010年から2030年までの間に世界全体の漁業生産量は23.6%増え、インド、中国、アジア諸国など、漁業が成長産業化するポテンシャルが高い国や地域が多々ある中で、日本の漁業はマイナス成長(マイナス9.0%)という予測がなされています。
実際、『世界漁業・養殖業白書(SOFIA)』(国際連合食糧農業機関FAO発行)によると、世界の食用の漁業生産量は、2009年の1億2,380万トン*2から2018年には1億5,640万トン*3に増え、10年間で26%増加しました。
一方、2020年の日本の漁獲量は前年比0.5%減の417万トン*4で、比較可能な1956年以降の最低を2年連続で更新し*5、世界的に見ても例外的な状況です。
1970年代までは世界をリードしていた日本漁業が衰退産業に転じたのはなぜか。大学院生だった1990年代から、データを元に警鐘を鳴らし続け、日本漁業の改革の必要性を訴えてきた東京海洋大学 産学・地域連携推進機構 准教授の勝川俊雄先生にお話を伺いました。
——かつては乱獲による資源減少で産業として成り立たないような状態だった諸外国が、漁業を持続的で収益性の高い産業へと改革できたのはなぜでしょうか。
まず、国連海洋法条約ができる前は、「公海自由の原則」により、陸地から見えるような沿岸まで外国船が入ってきて、好きなだけ魚を獲れた時代だったので、他国の乱獲を抑止する手段がなく、自国の水産資源を管理することは不可能でした。
1982年に国連海洋法条約に基づく200海里の排他的経済水域(EEZ)が設定されると、沿岸国主導の資源管理が可能になり、ノルウェーやニュージーランドなど、先見の明がある合理的な国から資源を管理する新しい仕組みに移行していきました。これらの国でも、漁獲規制を導入するときには漁業者は反対しましたが、実際に漁獲規制が始まってみると魚が増え、漁業ももうかるようになり、今ではほとんどの漁業者が資源管理に賛成という形に変わっています。
——一方、日本は戦後の深刻な食糧難の中、食糧増産の手段として、国を挙げて海外漁場の開発に励み、漁船の大型化・冷凍冷蔵技術を開発して乱獲を続けたという歴史がありますが、なぜ、時代が変わっても国策に変更がなかったのでしょうか。
構造的な問題をきちんと考えて、必要な変化を自ら起こしていくという文化が日本にはなく、あの手この手で、これまでの枠組みを延命することに心血を注いできました。問題を先送りするのは、水産の世界に限った話ではなく、年金制度もそうですよね。少子高齢化の時代にはどう見ても回っていかないことは明らかなのに、都合の悪いことは先送りにしています。
これは消費者にも言えることです。諸外国でも最初は業界が抵抗する中、政治主導で資源管理制度が導入されましたが、それはちゃんと漁獲を減らして水産資源を守ろうという国民の後押しがないとできなかったことです。
資源の減少が取り沙汰されるようになって久しいですが、日本の消費者はいまだに「値段が高くなるから今のうちに食べておこう」という発想です。
——啓蒙活動によって消費者の考えは変わるものでしょうか。
社会的な問題を解決する上で、自分がその問題の一部であるという意識を持つことは重要です。日本人の多くは、水産資源の減少は外国の乱獲や地球温暖化が原因で、自分は無関係だと思っている。自国の漁業に原因があることを知っている人も、漁業者や行政の問題であり、消費者自身の問題とは捉えていません。
世界の消費者の水産資源の持続性に関する意識調査をした結果がインターネット上に公開されているのですが、日本人の持続可能な消費行動の意識が世界的に見て例外的に低いという興味深い結果が得られています*6。
例えば、激減している生物資源は食べるべきではないと考える消費者の割合が、世界の多くの国の中で日本は一番低いです。サステナブル・シーフードを食べるべきと思う日本人は4割しかいません。日本の次にスコアが低いロシアでも7割ぐらいいるのに。また、地産地消を心がけている消費者の割合も世界最低でした。

ここまで世界と差がついてしまったのは、教育に原因がありそうです。日本の魚食教育では、魚をたくさん食べるのが良いことだと指導しています。持続可能性については情報を与えず、量を多く食べるように指導するのは、教育よりは、販売促進といったほうが適切かもしれません。
持続可能性を無視して、安く買って、たくさん食べる消費活動は、水産の現場での乱獲と相補的な関係にあります。持続可能性を無視した消費活動を、持続可能性を無視した漁業が支えてきたのです。その末路が今のウナギですよ。

——乱獲を避けて漁業の生産性を維持するには、①自然の生産力を科学的に把握する(資源評価)、②生産力の範囲に漁獲を制限する(実行性のある規制)、③水産物の付加価値付け(マーケティング)の3点が必須だと、『漁業という日本の問題』などのご著書やさまざまな記事で繰り返し書いておられます。どういうことでしょうか。
基本的に、現在の環境で生き残る能力を持った種だけが存在しています。自然に消滅してしまうような種はすでに淘汰されているわけです。なので、その生物が種として持っている、増加能力の範囲で獲っていれば持続可能性には問題がありません。
現状では、自然の生産力を大きく越えてしまっている漁業も多く存在するので、漁獲量を今より大幅に減らす必要があります。一方で、その結果として漁業者がいなくなってしまえば、水産業も魚食も持続可能にならない。水産資源の持続可能性と水産業の持続可能性が両立する道を探る必要があります。
——日本では水産資源の評価は、どうなっているのでしょうか。
水産資源評価にはざっくり言うと2つの手法があります。
一つは漁獲統計から見る手法で、魚が半分に減ったら、1回網を引いたときに獲れる魚もたぶん半分になるという考え方ですね。もう一つは、漁業とは独立した調査船による試験操業です。最近は高性能の魚群探知機(魚探)による調査も行われています。
最近は、魚群探知機の性能が上がったので、海の中の魚の量がより正確に把握できるようになってきました。しかし、群れをつくらない魚は魚群探知機では資源量が把握できません。また、今の漁業者は性能の良い漁具を持っているので、魚が減っても群れの場所を特定して効率的に漁獲をすることができます。特に産卵場で獲っている場合、産卵期には親魚が集まってくるので、本当にいなくなるまで、漁獲量は安定する傾向があり、資源量の指標にはなりづらいです。
どちらの手法にも精度が低い部分があり、専門家は複数の手法を組み合わせて推定するのが一般的です。ただ、データの解釈や扱い方には、様々な方法があり、100人の専門家が同じデータを渡されて推定したら、100通りの答えが出てくるといっても過言ではありません。
このように不確実性が大きい場合には、控えめな行動が要求されます。今年獲らなかった魚を来年獲ることはできますが、今年獲ってしまった魚を海に戻すことはできないからです。情報が不十分な場合は、控えめに行動をして、魚が十分いることがわかってから、漁獲枠を増やすべきなのです。残念ながら、日本の漁獲枠は現状ではそのようになっていません。漁業者から「獲りたいから魚がいることにしてよ」と言われれば、パラメータ次第で相当増やせるわけです。不確実性が大きい上に、科学者に圧力がかかると、資源評価は容易にゆがめられてしまいます。

——「資源評価の独立性」というのはそこの問題ですね。
そうです。たとえば、国際海洋開発理事会(International Council for the Exploration of the Sea; ICES)では、ヨーロッパ中から研究者が集まって、同じデータを元に議論をするので、特定の国の意向で資源評価を歪めることが難しい仕組みになっています。
日本の場合、水産業界と政府と研究者の距離が近いため、良くも悪くも漁業者の意向が反映されやすい仕組みになっています。結果として、漁獲規制が不十分なままで今日に至っています。
(「漁業法改正の次のステップを模索。漁業という日本の問題を考え続ける(Part 2)」に続く。)
勝川 俊雄
1972年東京都生まれ。東京大学農学部水産学科卒。農学博士。東京大学海洋研究所助教、三重大学生物資源学部准教授を経て、2015年4月より東京海洋大学 産学・地域連携推進機構准教授。国内外の漁業の現場を回りながら、漁業を成長産業にするための取り組みを続けている。日本水産学会奨励賞、日本水産学会論文賞を受賞。主な著書に、『漁業という日本の問題』(NTT出版)、『魚が食べられなくなる日』(小学館新書)。一般社団法人海の幸を未来に残す会理事。
*1 FISH TO 2030 Prospects for Fisheries and Aquaculture (The World Bank、2013年)
*2 The State of World Fish and Aquaculture (FAO、2016年)
*3 The State of World Fish and Aquaculture (FAO、2020年)
*4 令和2年漁業・養殖業生産統計(農林水産省、2021年)
*5 農林水産省「漁業・養殖業生産統計」より
*6 Global attitudes about sustainable fishing and policies to curb overfishing (Ipsos、2019年)
取材・構成:井内千穂
中小企業金融公庫(現・日本政策金融公庫)、英字新聞社ジャパンタイムズ勤務を経て、2016年よりフリーランス。2016年~2019年、法政大学「英字新聞制作企画」講師。主に文化と技術に関する記事を英語と日本語で執筆。




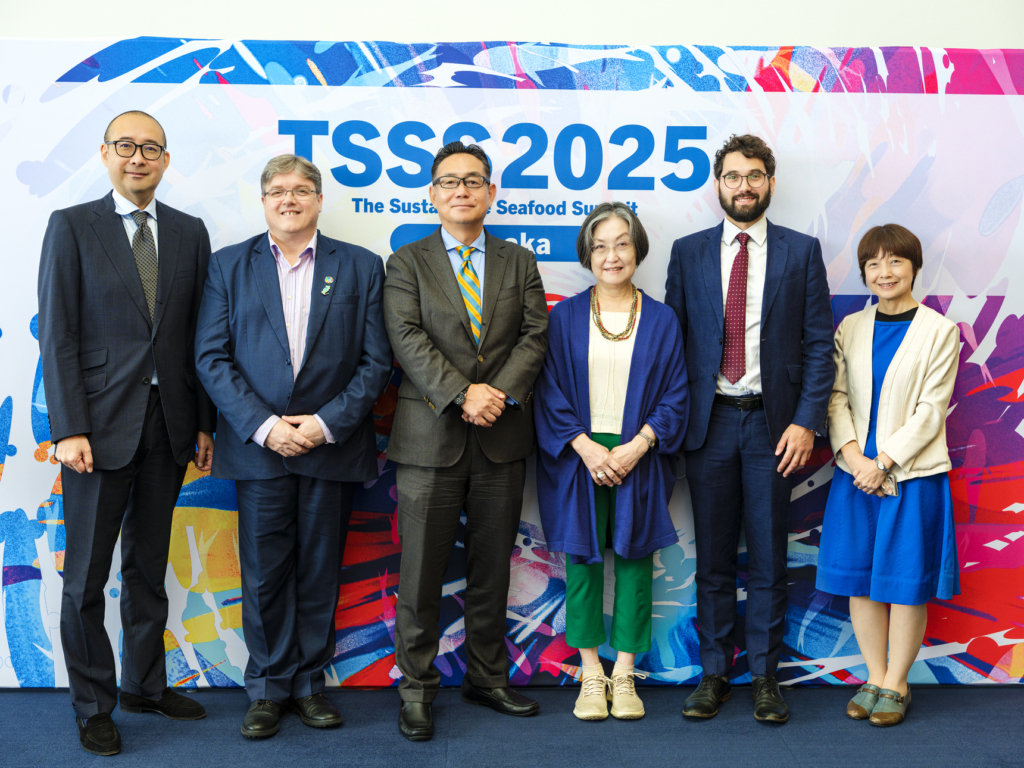














--1024x819.jpg)


































Times-top-banner-1024x609.png)
Times-top-banner-1024x609.png)














































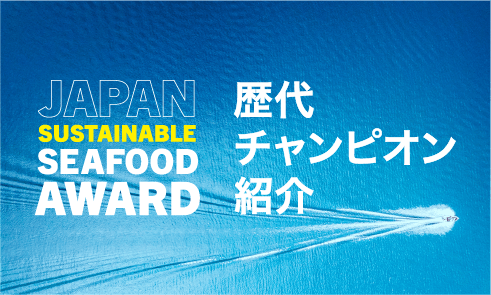
KEY WORD
水産分野の専門用語や重要概念を解説。社内説明やプレゼンにも便利です。