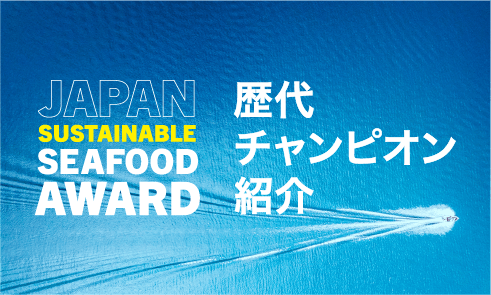サステナブル・シーフードのムーブメントは15年ほど前から欧米を中心に始まりました。
その中で、小売業界内で先陣を切ったと言われているのが、北米の小売企業の最大手、Walmartです。Walmartはサステナブル・シーフードの調達にいち早く取り組み、その後、他の小売企業が後に続くきっかけをつくりましたが、それでも同社の水産マーチャンダイズ・ディレクター、トレヴィア・レスター氏によれば、「取り組みを始めたばかりの頃はまだ周りの事例も少なく、全ての商品をすぐに認証取得済のサステナブルな商品に切り替えることは無理だと分かっていた。できることは、原産地の情報などを調べ上げることだった*1」のだそうです。
ではWalmartは実際、どのように取り組みを推進してきたのでしょうか?
WalmartはAmazonを超える、世界最大の売上高60兆円を超える企業です*2。その多大なる影響力を環境問題の解決に生かすため、2005年にサステナビリティ関する3つの目標を設定しました。その中の「人と環境に配慮した製品を販売する」*3の一環で、全ての海外のエビのサプライヤーに対しBAP認証の取得を求めることを発表し、国際環境NGOのConservation International (CI)と協働して調達のためのプログラムを策定したほか、BAP認証の基準に則って沿岸湿地の保全も強化しました*4。
2006年、国内向けの全ての天然漁業による生鮮・冷凍魚を3-5年以内に全てMSC認証に置き換えることを目標とし、年内にまず、認証を取得してはいるがラベルが表示されていない商品のラベルを表示することから始める、と発表*5しました。この目標を達成するために、WalmartはCIやWorld Wildlife Fundとも協働しました。
その後2009年には「Sustainable Product Index(現:The Sustainability Insight System (THESIS) Index)」を発表しました*6。これは、製品のサステナビリティを評価するためにデータの情報源を一元化するための取り組みで、3段階に分けて進められています。
・世界中の10万社のサプライヤーを対象に、「エネルギーと気候変動」、「原材料の使用効率」、「天然資源」、「人とコミュニティ」の4分野での取り組みに関して15問の質問票を送り、トレーサビリティを調査
・世界中の、製品の原材料から廃棄までのライフサイクルに関するデータベースを構築するためにサプライヤー、小売、NGO、政府が協力する大学間コンソーシアムの形成を支援
・製品のサステナビリティに関する情報を消費者が簡単に理解できるような形に変換

現在は、2016年に北米、カナダ、ブラジルなどのWalmartやSam’s Club、ASDAで販売する水産物について掲げた以下2つの目標の達成に取り組んでいます(Seafood Policy)*7。
1. 生鮮、冷凍水産物は2025年までに以下のいずれかの条件を満たした水産物に切り替える
・MSC、ASC、BAP認証を取得している
・水産エコラベル認証のベンチマークプログラムを運営する国際組織Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)に認定され、FAOのガイドライン*8を満たす認証を取得している
・または認証を取得しようとしている、あるいは生産手法を持続可能にする「漁業・養殖業改善プロジェクト(FIP、AIP)」を行っている漁業・養殖業により生産されている
2. ツナ缶のツナ
上記の3項目に加え、世界のマグロの研究者や企業、環境NGOにより構成される組織 International Sustainable Seafood Foundation (ISSF)が定めた基準を満たす方法で獲られたマグロに2025年までに全て切り替える
また、2017年には、米NGOのSustainable Fisheries Partnershipが始めた、Ocean Disclosure Projectに参加し、自社の水産物の調達元を同プロジェクトのWebサイトにて公表しています*9。
15年前からその時々に応じて目標を設定し、取り組みを進めてきたWalmartですが、実は2006年に立てた、国内向けの全ての天然漁業による生鮮・冷凍魚を3-5年以内に全てMSC認証に置き換えるという目標はまだ2021年7月現在達成できていません(認証を取得した、またはFIPによる水産物を足すと、2021年7月時点では、Walmart USで98%*10)。また、当初はMSC認証のみを切り替える水産物として設定していましたが、2016年にはFIPやAIPも追加されています。しかし、立てた目標を100%達成していなくてもWalmartは、レポートなどを通じて定期的に途中経過を公表してきました。
日本でも、具体的な調達目標を設定して取り組みを進めている企業が増えてきました。
例えば、イオンは2017年に発表した「持続可能な調達方針2020年目標」の中で、同社連結対象の総合スーパー、スーパーマーケット企業で、MSC、ASCの流通・加工認証(CoC)の100%取得をめざすことを目標としており、2020年10月時点*11で80%達成しています。

また、日本生活協同組合連合会(日本生協連)は、2017年に採択した「コープSDGs行動宣言」の下で、「日本生協連の水産部門コープ商品の供給金額でMSC/ASC等の認証品を2020年度までに20%以上」にすると目標を掲げていましたが、2019年に商品として取り扱っていた大西洋のサバのMSC認証が一時停止されたため、「2025年までの早い時期に20%を達成する」*12という目標に変更しました。
大西洋のサバはMSC認証を取得している魚種の中でもメジャーな魚種であったため、認証一時停止の対応に追われる企業も多くありましたが、需要に応じて審査基準を緩める認証も存在する中で、環境持続性の担保においてMSCがいかに信頼できる認証であるかが、改めて浮き彫りになりました。
目標未達分を別の認証で補うのではなく、厳格なMSC認証を軸に置き続けて対策を練るこうした姿勢は、消費者だけでなくサプライチェーン上にいる数多くの生産者や加工流通業者の未来への責任を果たそうとする本気度を表していると言えるでしょう。
ブレない方針をつくるには以下の3つのポイントがあります。
調達目標を設定する
消費者の嗜好や動向分析は、商品やサービスの開発や発展に不可欠ですが、その根幹には、「企業としてこういう将来をつくりたい」という姿があります。この姿がはっきりすれば、そのつくりたい将来のために何をすべきか、そのために販売すべき商品は何か、というように、最終的には短期的かつ具体的なアクションを取ることができます。
達成までの道のりを描く
目標達成への道のりは、Walmartのように信頼できる複数のNGOや専門機関とパートナーシップを組み、水産エコラベル認証や漁業・養殖業改善プロジェクトに代表されるツールを上手に組み合わせて活用することが、成功への近道です。また欧米では近年、課題を共有する同業他社が解決に協働する非競争連携プラットフォームの設立も活発になってきています。
当初の目標達成が難しそうであれば軌道修正中であることを公表する
目標を到達できないことをリスクととらえ、具体的な数値目標を設定し公表することを躊躇う企業もありますが、ウォールマートの事例が示す通り、目標達成が難しい場合は原因と対策をしっかり練って公表することで、新たな加速をつける機会にすることができます。
今、多くの企業が達成しようとしているSDGsの達成期限は2030年です。
その目標12「つくる責任 つかう責任」のテーマ中のターゲットには「12.6 大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導入し、定期報告に持続可能性に関する情報を盛り込むよう奨励する。」などがあります。
不確定要素が増えていくであろう将来に備え、多少の軌道修正はありつつも、自社、顧客、ステークホルダー、そして社会のサステナビリティためにも、中長期的な視点を持って事業を成長させていくことが必要です。

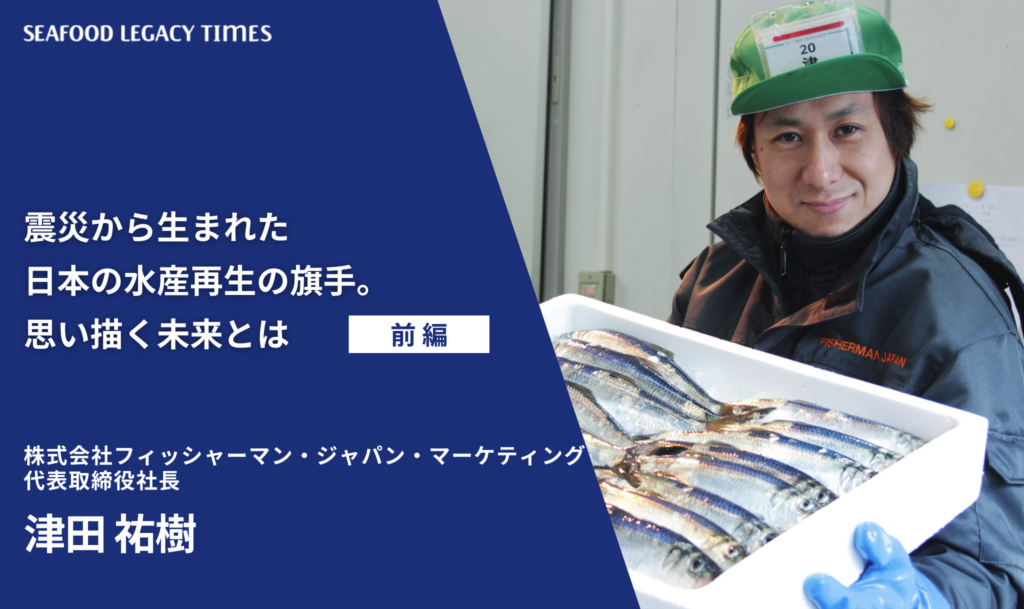























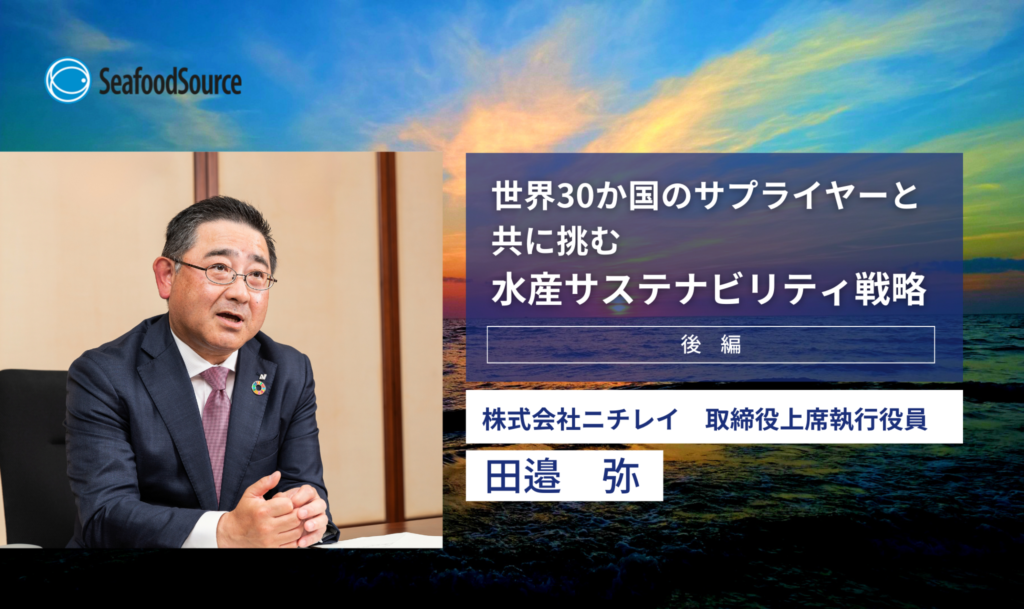
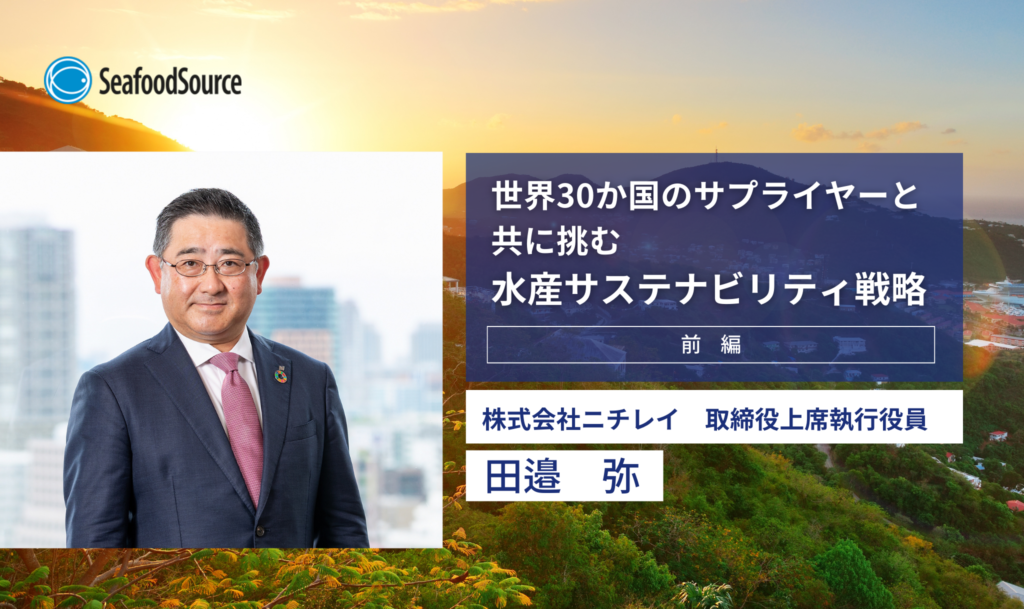










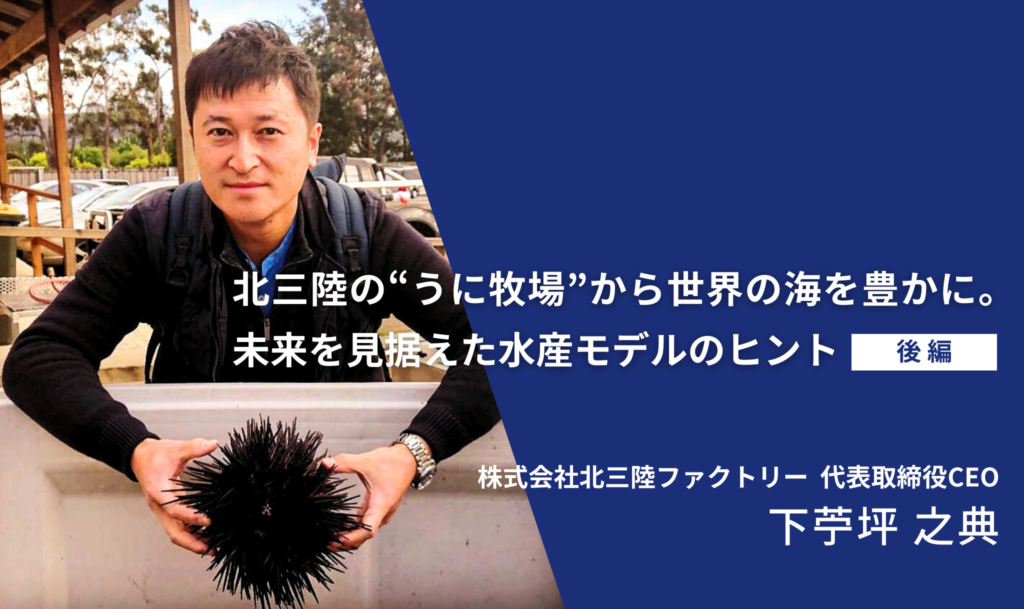




-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

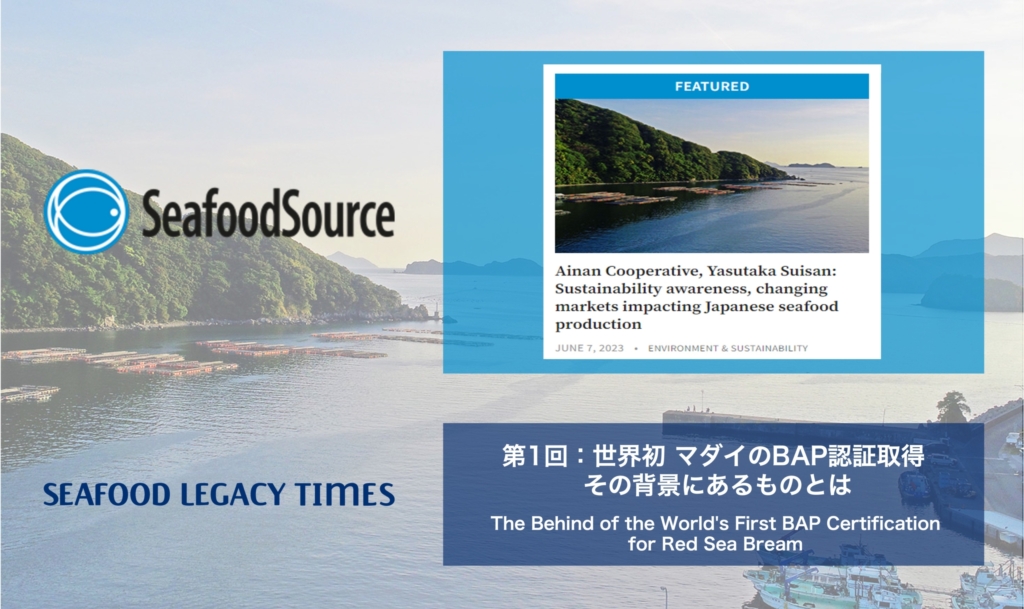
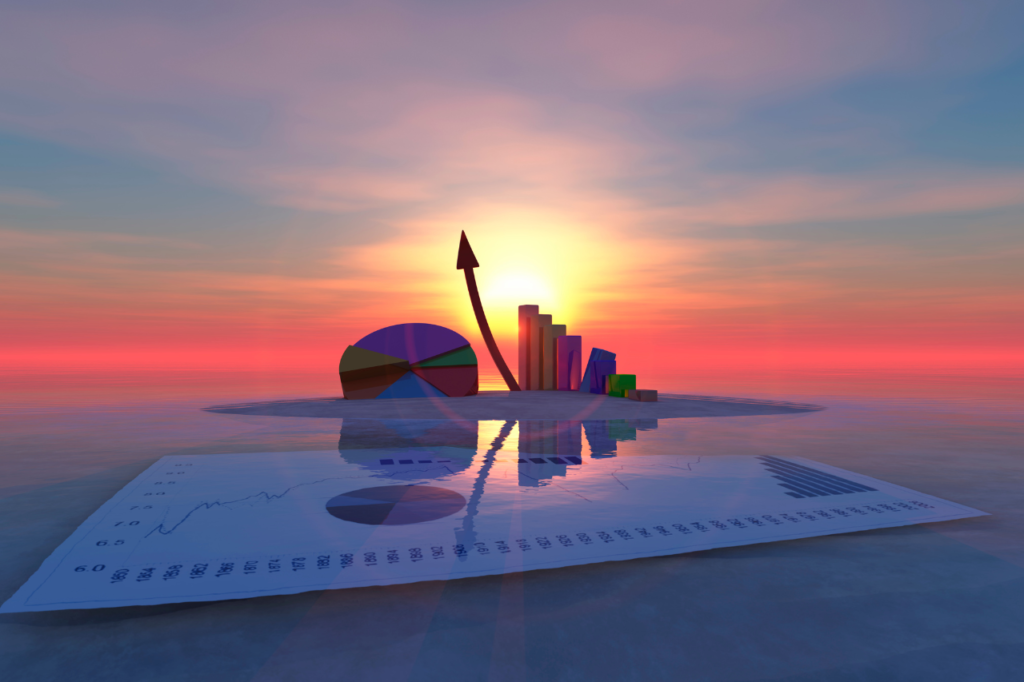










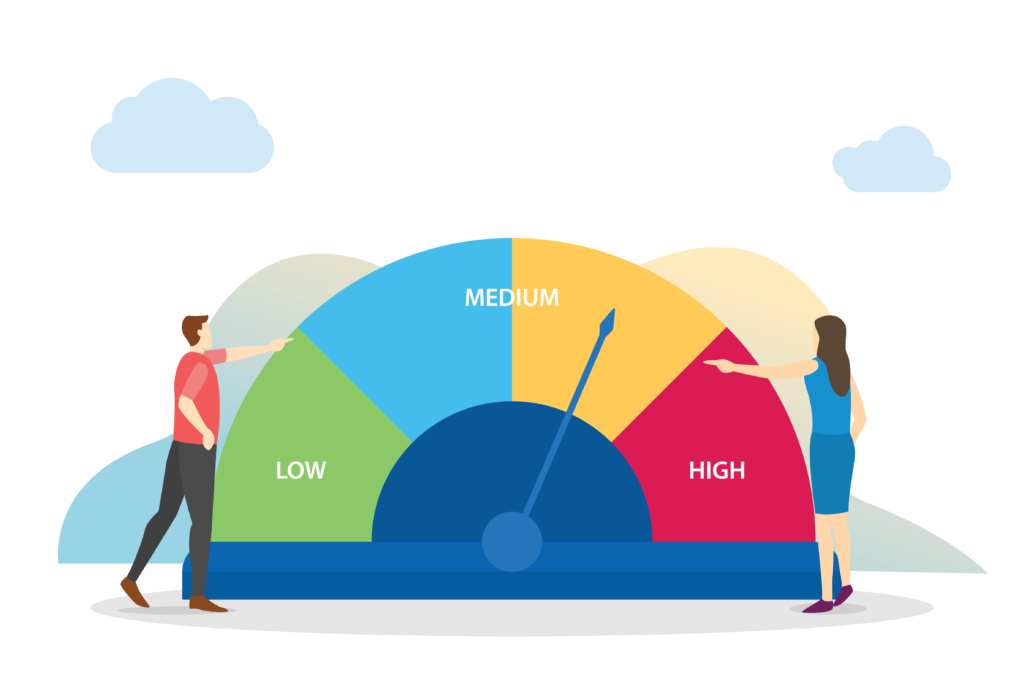

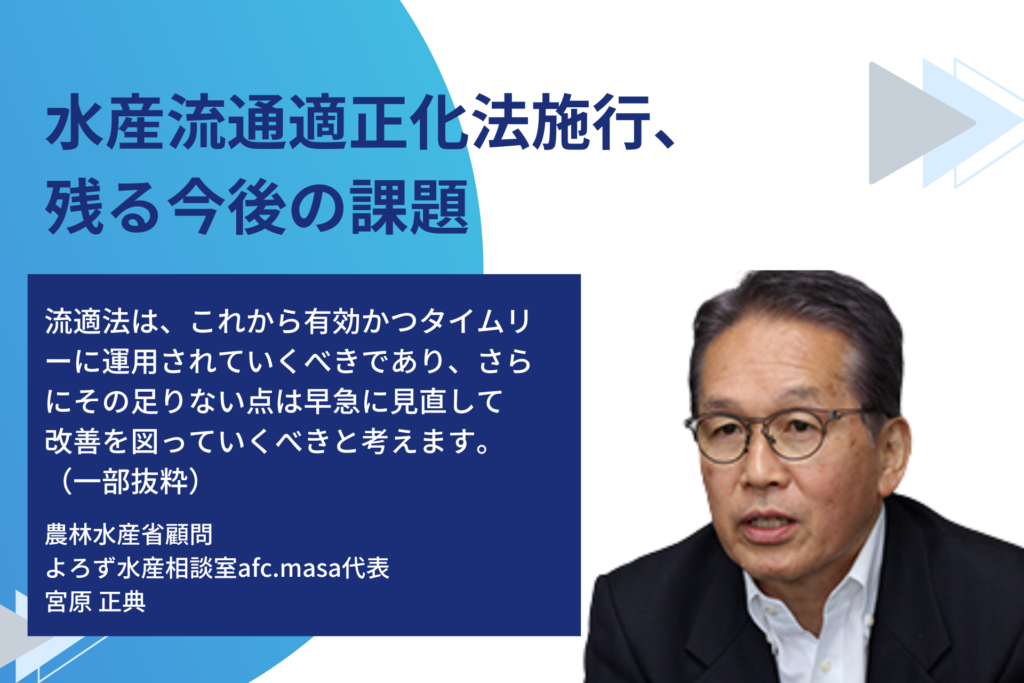
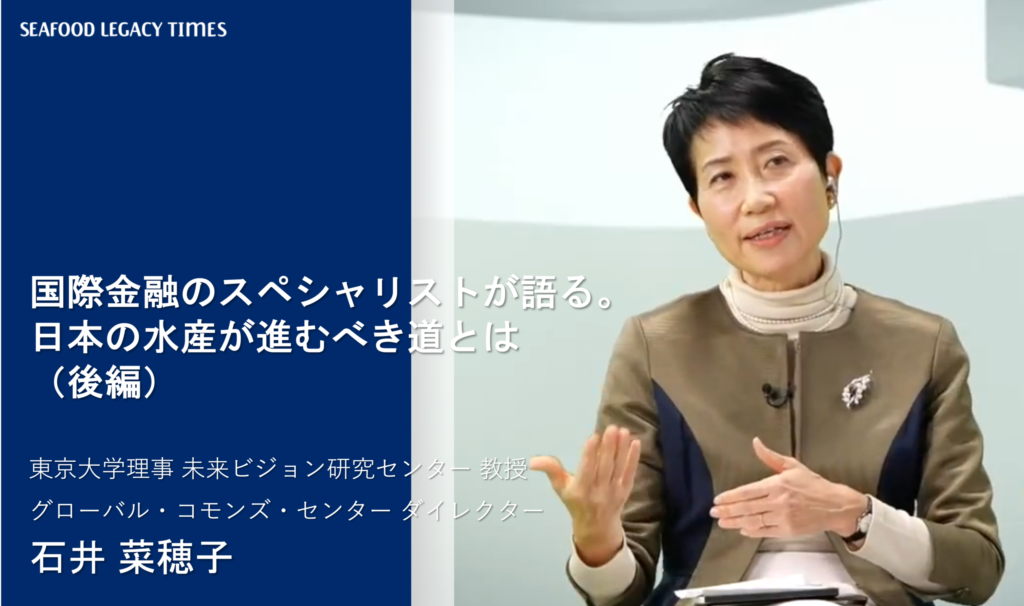


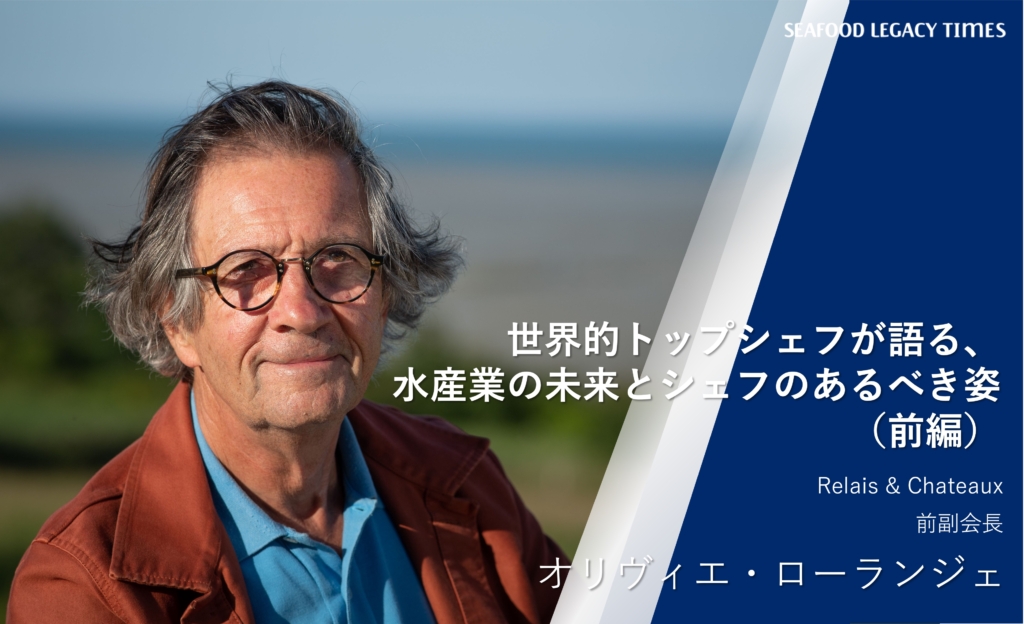



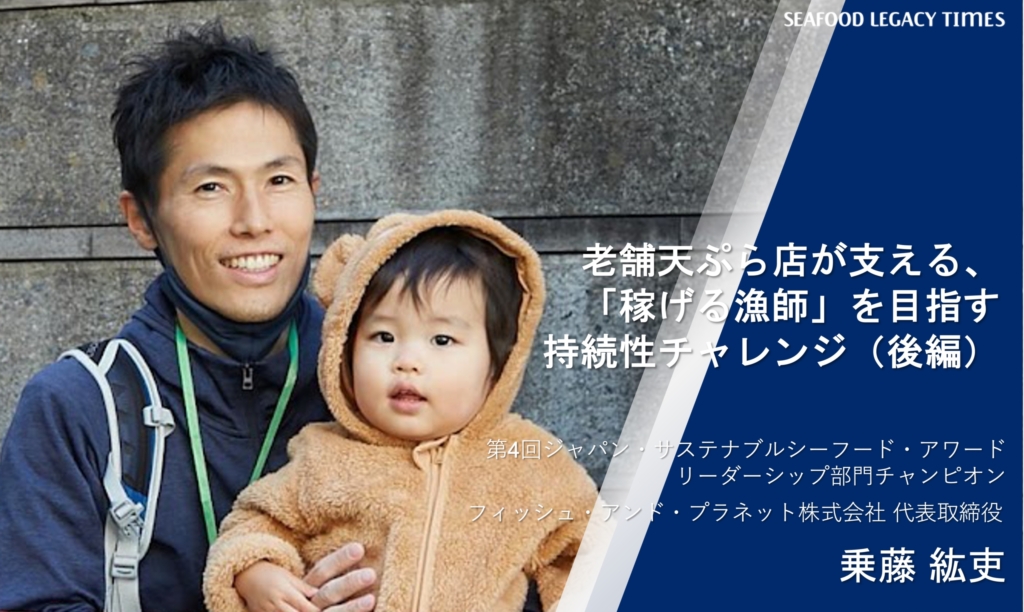
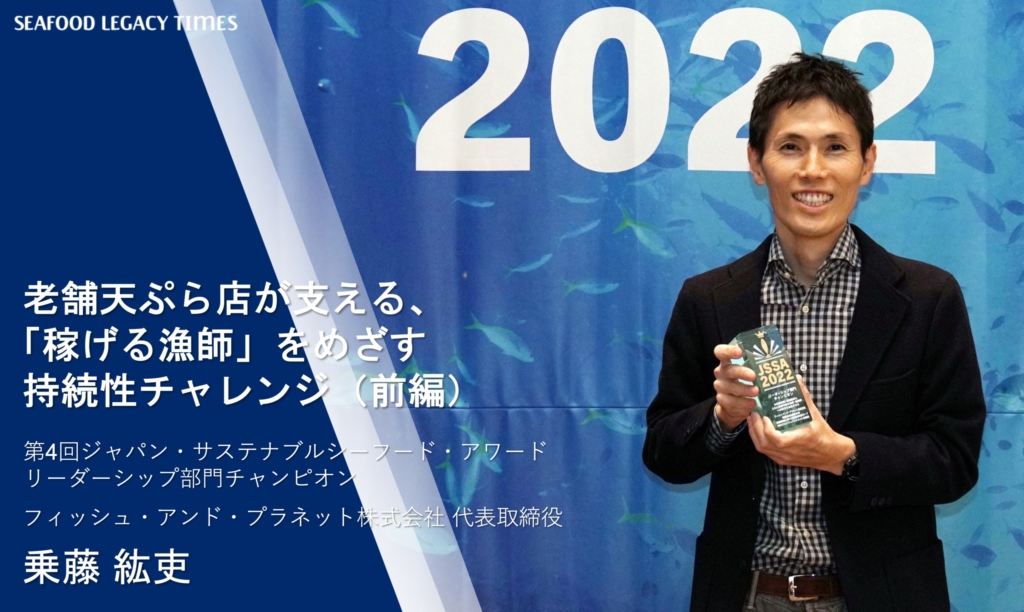

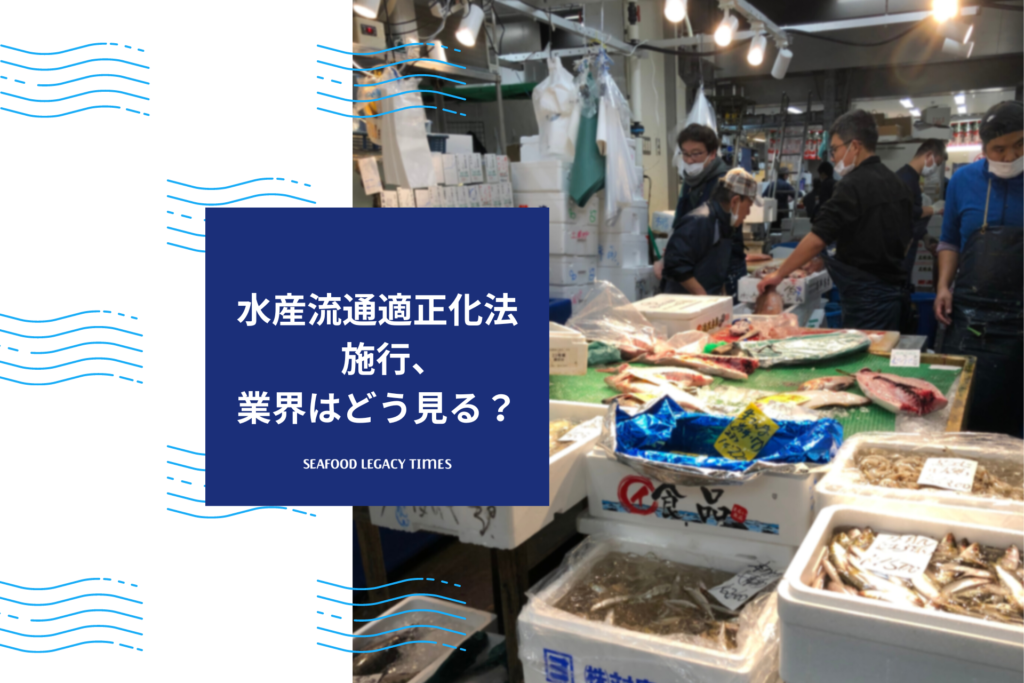
-2560-×-1536-px-1024x614.png)

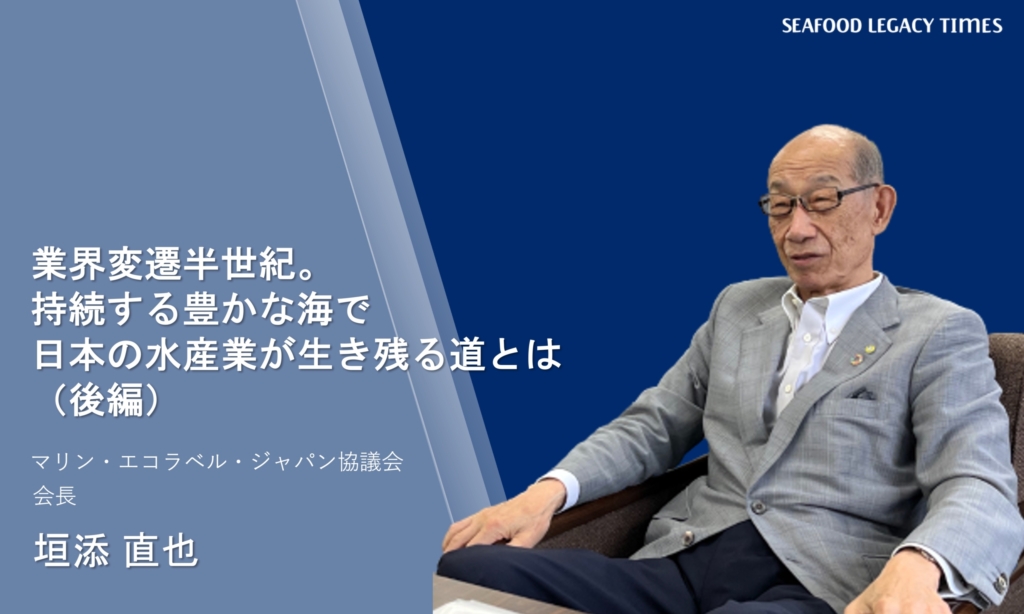

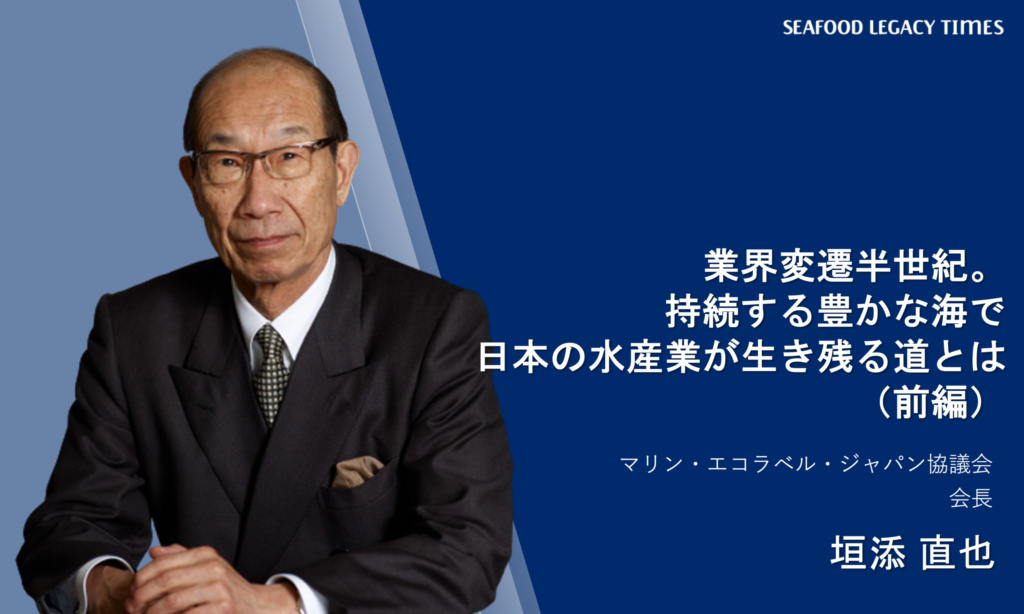







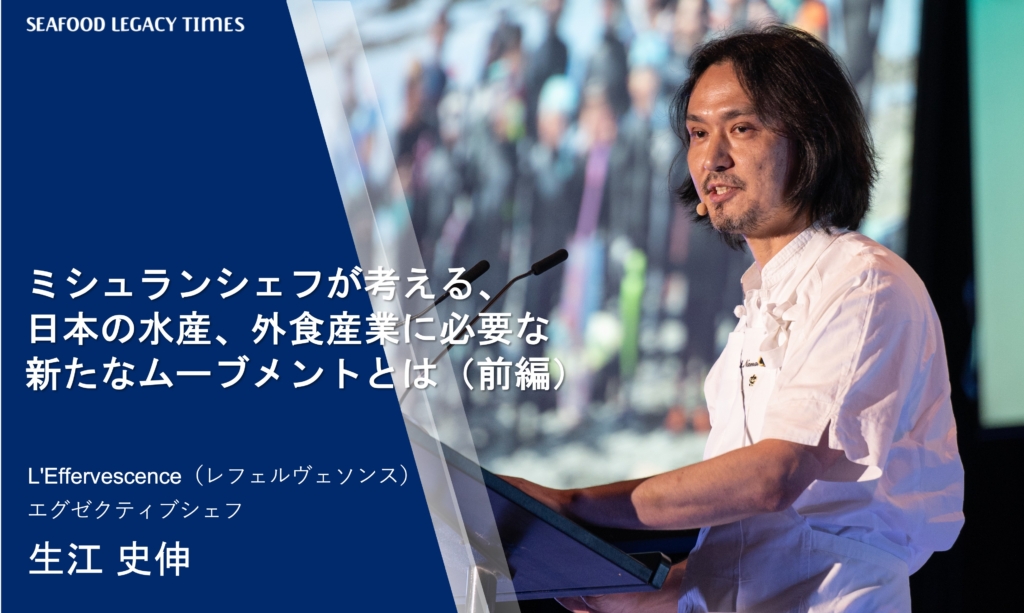






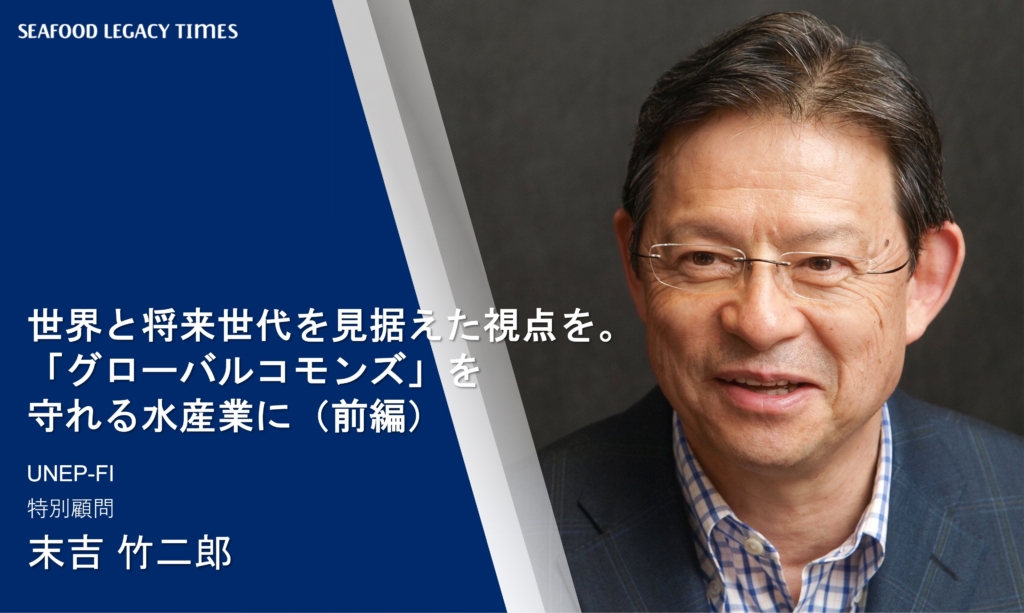









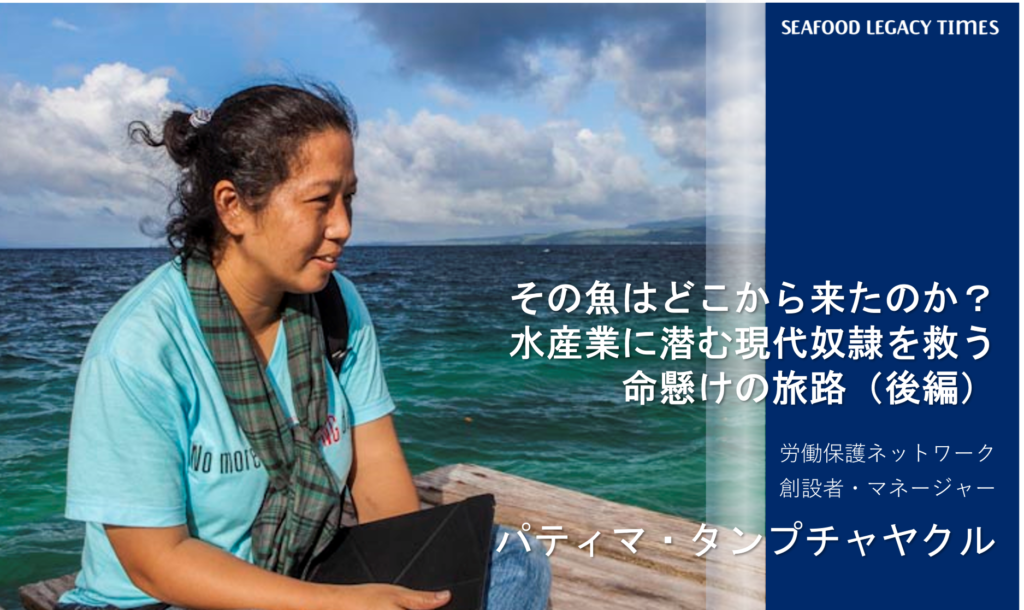

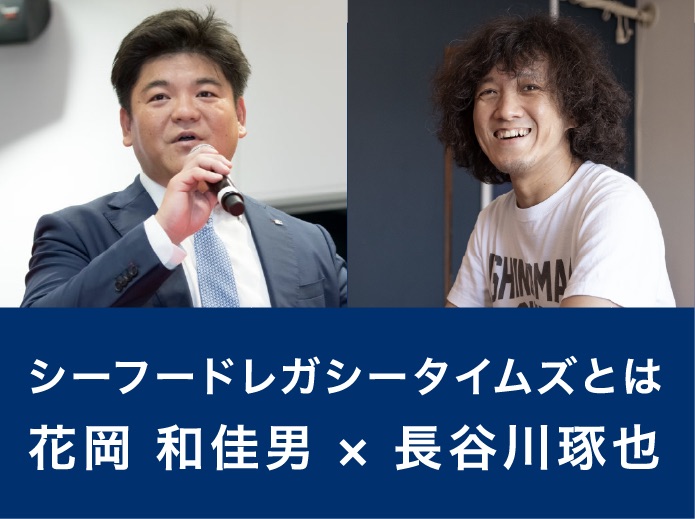
.jpg)