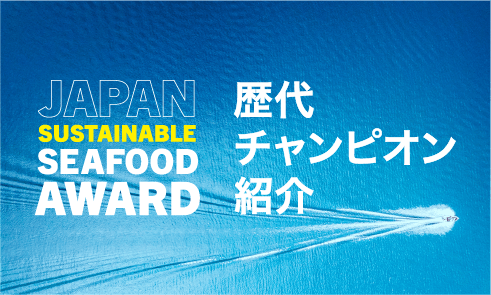前編で、ブルーボンドの課題や、サステナビリティ・リンク・ローン(以下SSL)などサステナブルファイナンスへの需要の高まりについてお話いただいた末吉光太郎さん。後編では、水産の中小企業でも活用できるサステナブルファイナンスや、SDGsの取り組みをサポートする融資を行うことの意義などについて伺います。
また、カーボンニュートラルを見据え、気候変動に関連する情報開示を推進する「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」に続き、その生物多様性版、「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)」について、どう捉えているかなどについてもお話いただきました。
——水産業界がもっと上手に投資を活用していくにはどうしたら良いのでしょうか。
日本の企業は99%が中小企業です。その中でも特に農林水産業界は小さな事業者が多いように思われます。そういった中小の事業者の方々はお金を借りるのも農業協同組合や漁業協同組合から借りることが多く、いわゆる銀行から融資を受けることは少ないかもしれません。
ブルーボンドのような公募債はある程度大きな事業の資金調達に適しており、それぞれの事業の規模に合わせた資金調達の方法があります。例えばみずほ銀行では中小企業向けのSSLを行っています。これは、格付け会社ではなくみずほ銀行がSSLの国際原則に則って評価を行うので、調達される方は評価費用のコストを負担せずにSSLを組むことができます。
SSLは、サステナビリティに関する目標を掲げ、それを達成すれば金利が下がるというものです。海の生物多様性、海洋に関する人権問題など、それぞれの事業内容に合わせた目標を設定すれば、中小企業でも活用いただけますし、対外的にも取り組みをアピールしていただけるはずです。
そのほか、自社の取り組み状況を診断し、強みの強化や課題の改善に向けたSDGs宣言をしていただく「SDGs推進サポートファイナンス」という取り組みも進めています。具体的には、これから取り組みを開始される中小企業のお客さま向けに、野心的な数値目標の代わりにSDGsの17のゴールや169の指標から自社が解決すべきものを選んで宣言することで資金を調達できるというものです。
「SDGs推進サポートファイナンス」は、東京都様と連携し、東京都の「信用保証協会保証付貸出」を活用した制度融資として、同様のスキームを活用し保証料の優遇などを付した取り組みを開始しています。「SDGs宣言」については、その後の実際の事業がどのように進んでいるか、みずほ銀行が定期的に取り組み状況をお伺いし、達成に向けた支援の提案も進めています。
金融機関は、あらゆる規模の企業にご利用いただけるよう、さまざまな融資の方法を用意しています。自社の財務状況に合わせていかにサステナビリティに関する取り組みのための資金を調達するか、水産業界でも検討していただきたいですし、私たち金融機関もお伝えしていかなければならないと思います。
 みずほ銀行が提供する中小企業向けSSLとSDGs推進サポートファイナンス
みずほ銀行が提供する中小企業向けSSLとSDGs推進サポートファイナンス
——水産分野のサステナビリティをすすめる上で、金融機関はどんな役割を果たせると思われますか。
金融機関の役割は、水産に関わる企業がサステナビリティを推進する上で必要な資金をしっかりとご提供することだと思います。そのために金融機関は、どの取り組みが本当にサステナビリティのためになるのか判断できる力を持たねばなりません。
〈みずほ〉は、脱炭素社会の実現に向けた長期的な戦略に則り着実な温室効果ガス削減の取り組みを行う企業を支援するトランジション・ファイナンスでも高いシェアを誇るトップランナーです。それは、これまでに積み上げてきた産業知見や環境知見から企業の取り組みを正しく判断できる力を持っているためです。今後、水産分野のサステナビリティをすすめるために、自然資本に関してもそういった知見を積み上げていきたいと考えています。
また、金融機関は、水産分野の中でサステナビリティに資する取り組みを見極めてそこへ融資することによって、「この事業は正当である」という信頼性を社会に示していく役割も担う必要があります。「〈みずほ〉が融資する企業ならば安心だ」と、他の金融機関からも資金が集まるような流れをつくっていくことができればと思います。
——2023年の秋にはTNFDの枠組みの発表が予定されていますが、これによって海を含めた自然資本への投資はどう変化すると期待されますか。
脱炭素の分野の情報開示を推進するTCFDを例に考えると、まず「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が示す科学的根拠が交際交渉の元になり、「気候変動枠組条約(UNFCCC)」や「パリ協定」が誕生しています。そこで温室効果ガスを測る計測方法が決められていて、科学的根拠に基づいた気候変動の目標、SBT(Science Based Targets)がありますます。TCFDは気候変動に関する各企業の情報を開示するための枠組みです。金融機関はTCFDによって統一され開示された各企業の情報と財務情報を合わせお客さまとの対話を進めていく時代になりつつあります。
生物多様性の場合、2022年に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、気候変動同様、科学的根拠に基づいた自然に関する目標、SBT for Natureが掲げられました。しかし、生物多様性の場合、課題となるのは、状況を定量化できる測定方法がないことです。今年の秋にTNFDの最終的な枠組みが発表されましたが、何かを定量化できる方法の具体化や発展が、取り組みの浸透には必要だと思われます。
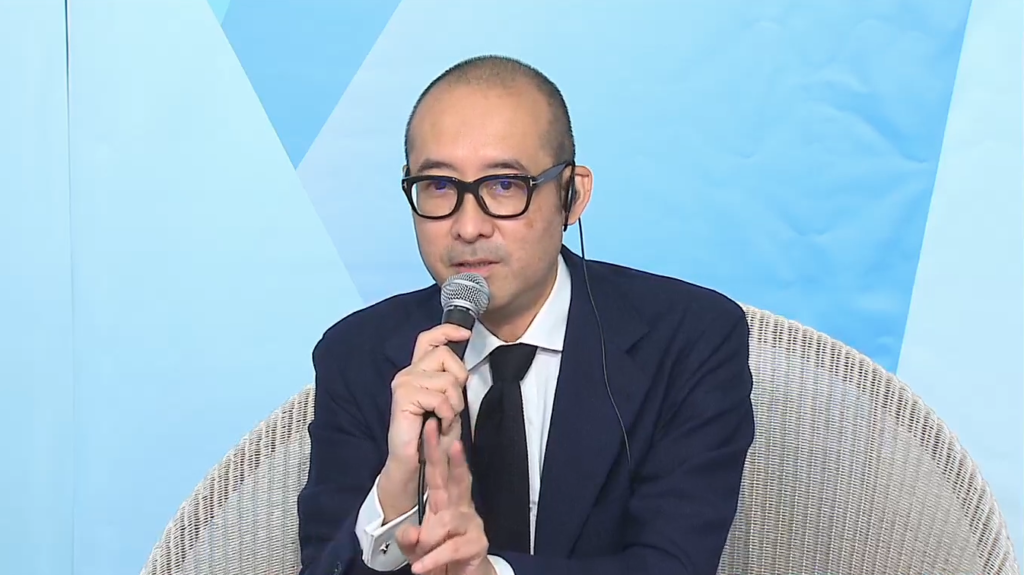 TSSS 2022(東京サステナブルシーフード・サミット2022)にて
TSSS 2022(東京サステナブルシーフード・サミット2022)にて
生物多様性は幅広く定量化が難しい問題ですが、経済界も自然資本に支えられているわけですから、仕組みが整えばTNFDもTCFDと同じように機能していくと思います。2025年にSBT for Natureの最終的なガイダンスが完成すれば、弾み車のように勢いを持って前に動き出すのではないでしょうか。
——みずほフィナンシャルグループのサステナブルビジネス部では今後、水産分野のサステナビリティに関連してどのような取り組みを予定されていますか。
まだ具体的に決定しているものはないのですが、ビジョンとしては、ブルー(海の持続可能性に資する)を含めたサステナビリティの実現に貢献する革新的なイノベーションにリスクマネーを提供していくことで、新たな取り組みを共創していきたいと考えています。
〈みずほ〉は、水産分野を含めサステナビリティを実現していく力になる新しい技術やビジネスモデルを、実証段階に入る前の段階のものを含めて支援していくために、今後10年間で500億円を目途に投資を行うことを標榜しています。今後、水産業界を成長分野として応援していきたいと思っています。
末吉光太郎(すえよし こうたろう)
みずほ銀行入行後、大企業法人営業、国際業務・国内法人業務企画部門等を経て18年より法人向け銀行ビジネスのデジタル化ならびに自ら立ち上げたSDGsビジネスデスクを率いて、社会課題解決型ビジネス開発・支援とインパクト投融資を推進中。21年より法人向けサステナブルビジネス企画を担当し、2022年9月からサステナブルビジネス部 副部長に着任。
取材・執筆:河﨑志乃
デザイン事務所で企業広告の企画・編集などを行なった後、2016年よりフリーランスライター・コピーライター/フードコーディネーター。大手出版社刊行女性誌、飲食専門誌・WEBサイト、医療情報専門WEBサイトなどあらゆる媒体で執筆を行う。

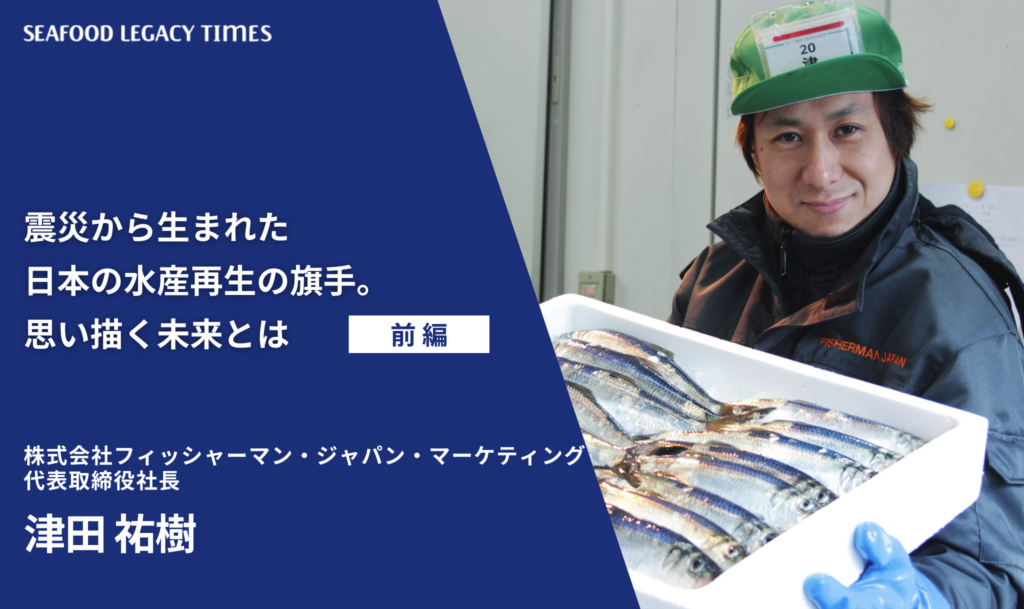























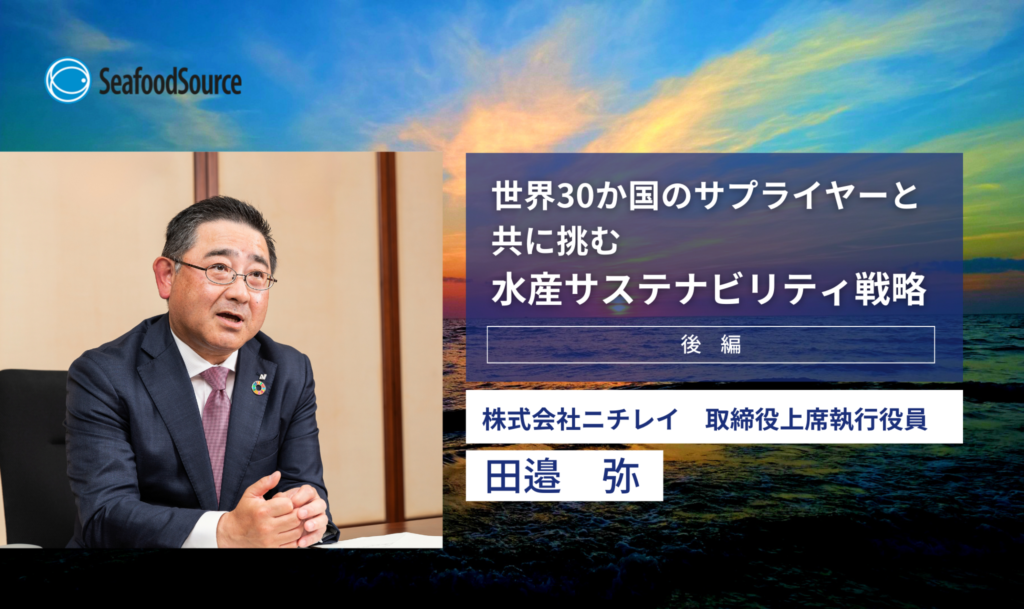
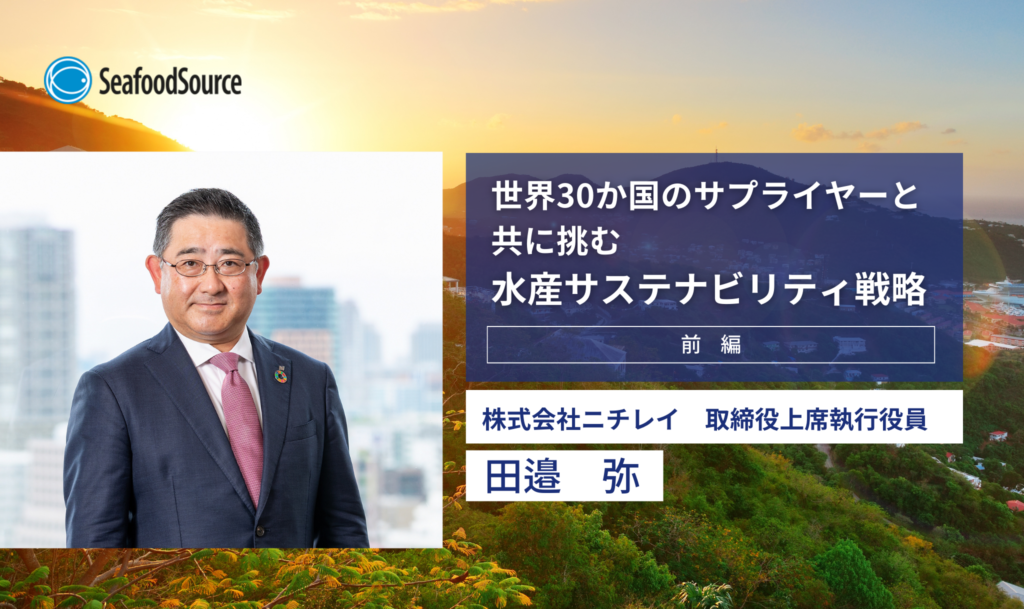










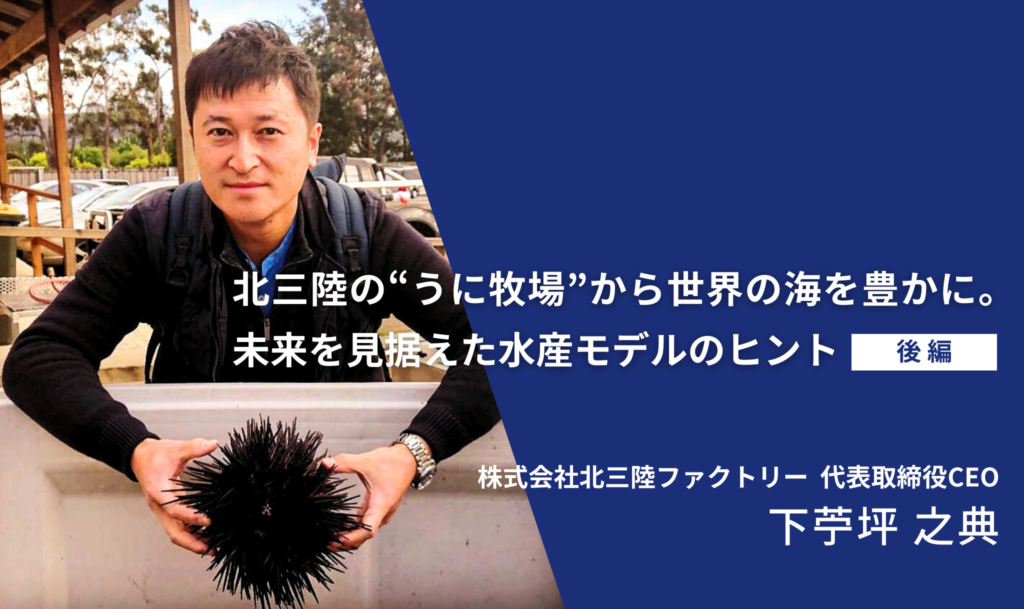




-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

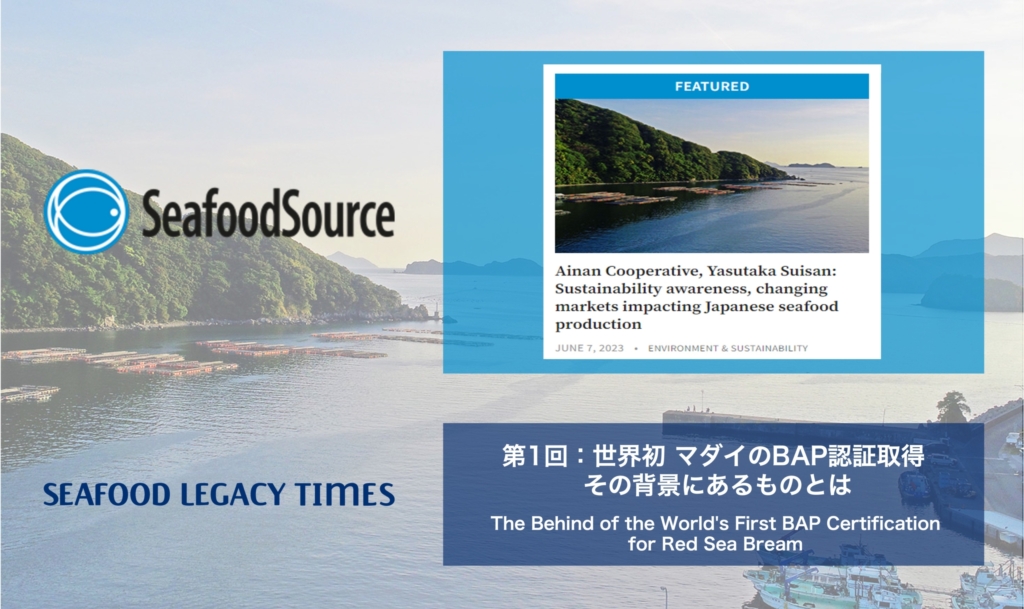
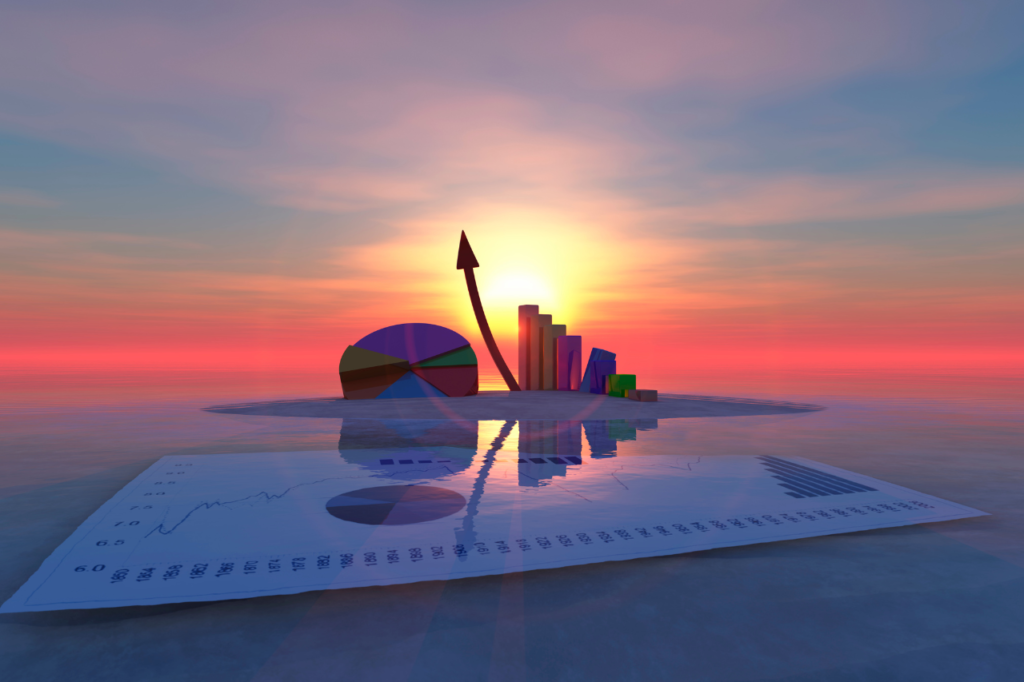










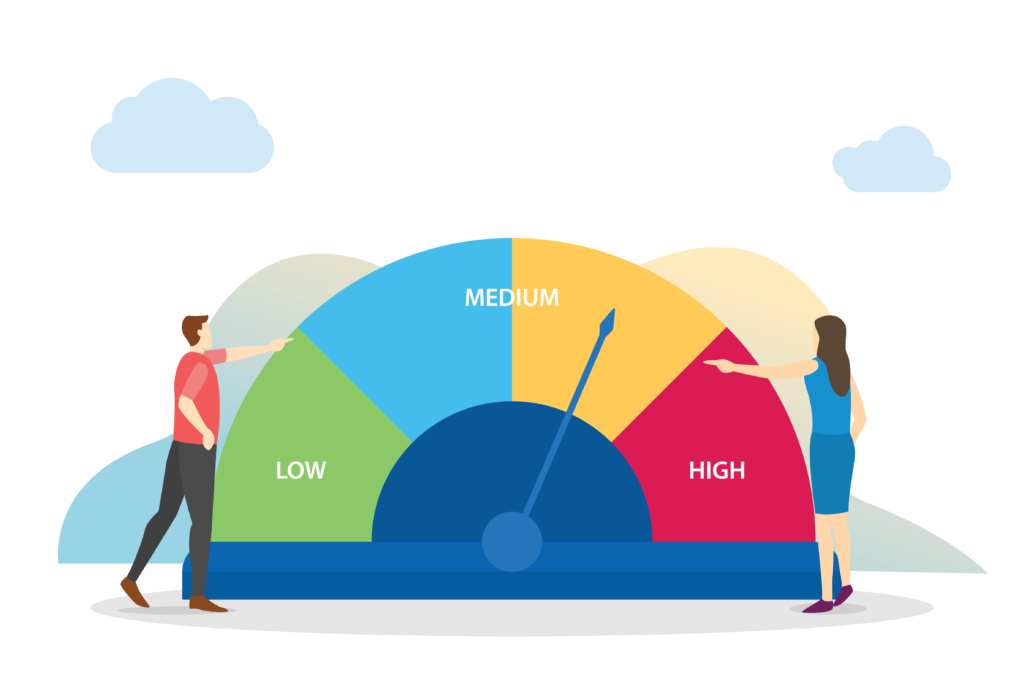

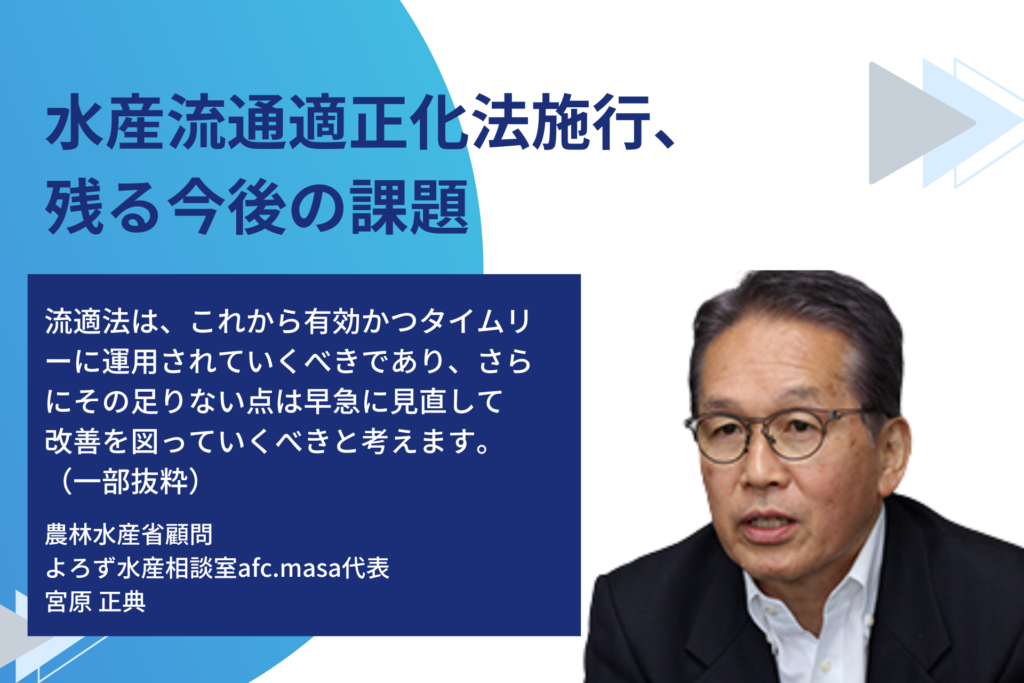
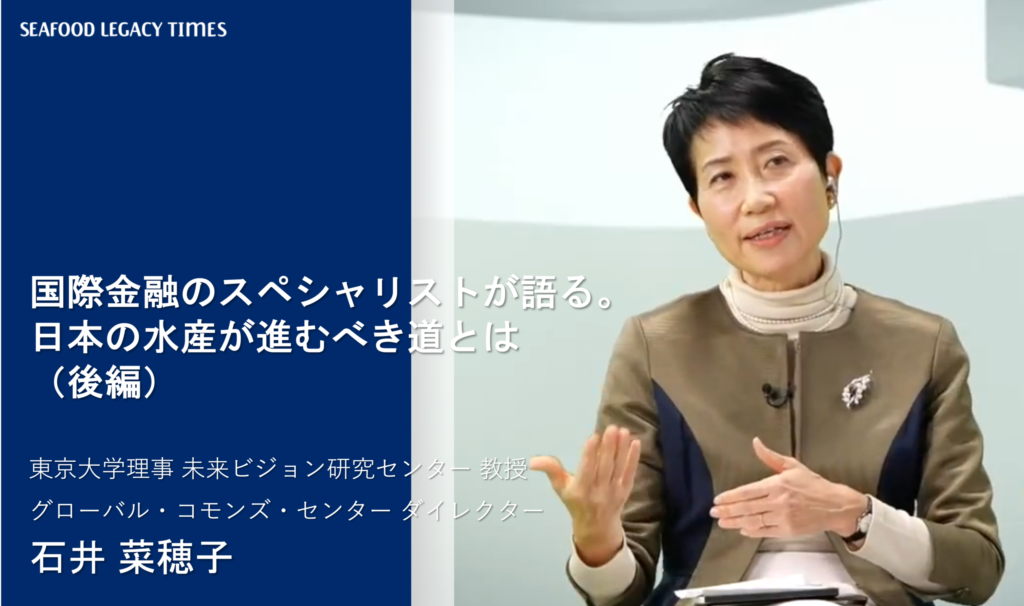


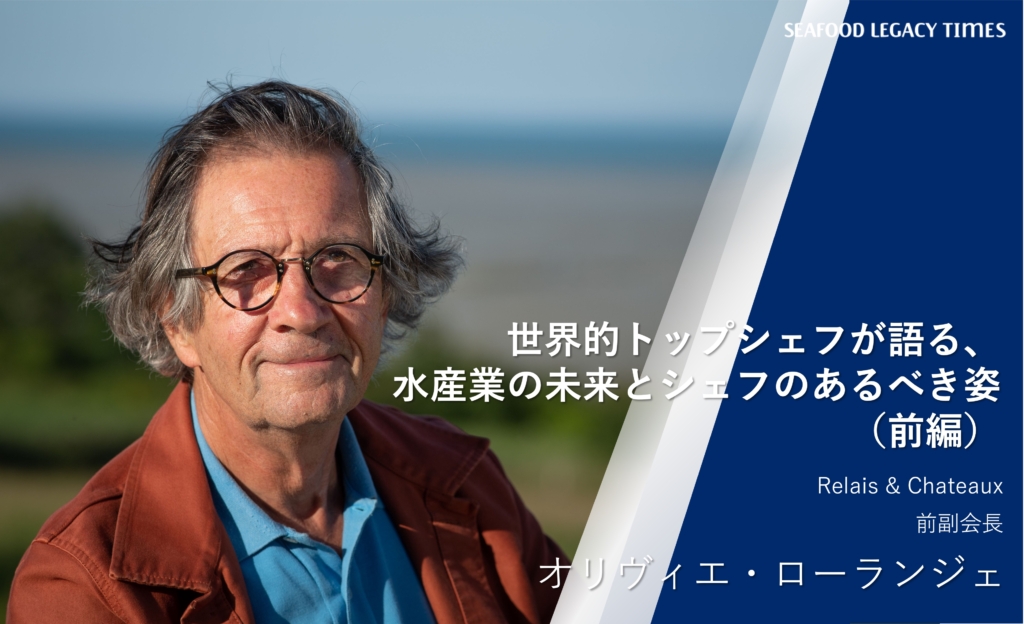



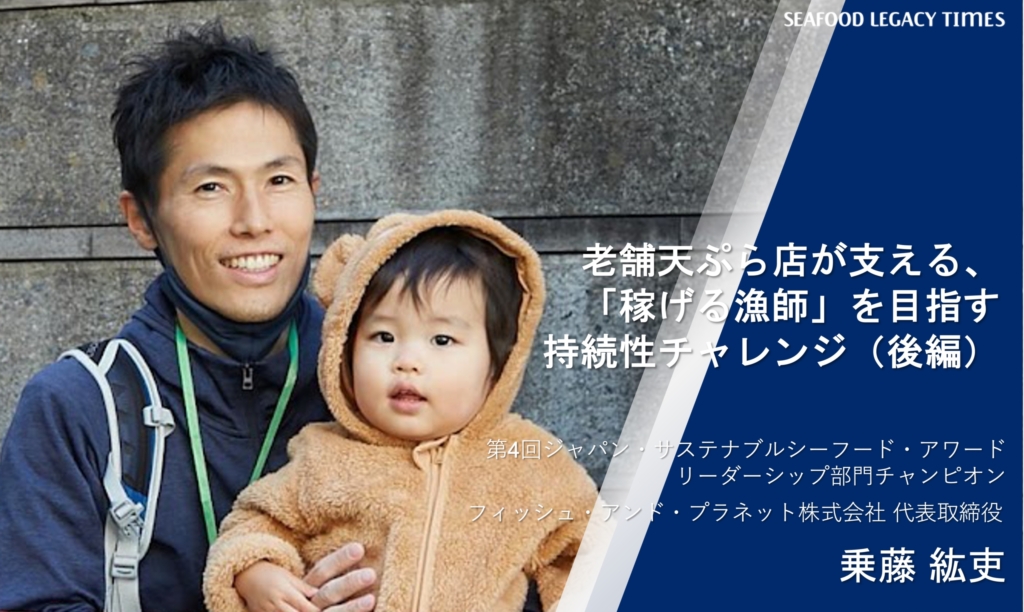
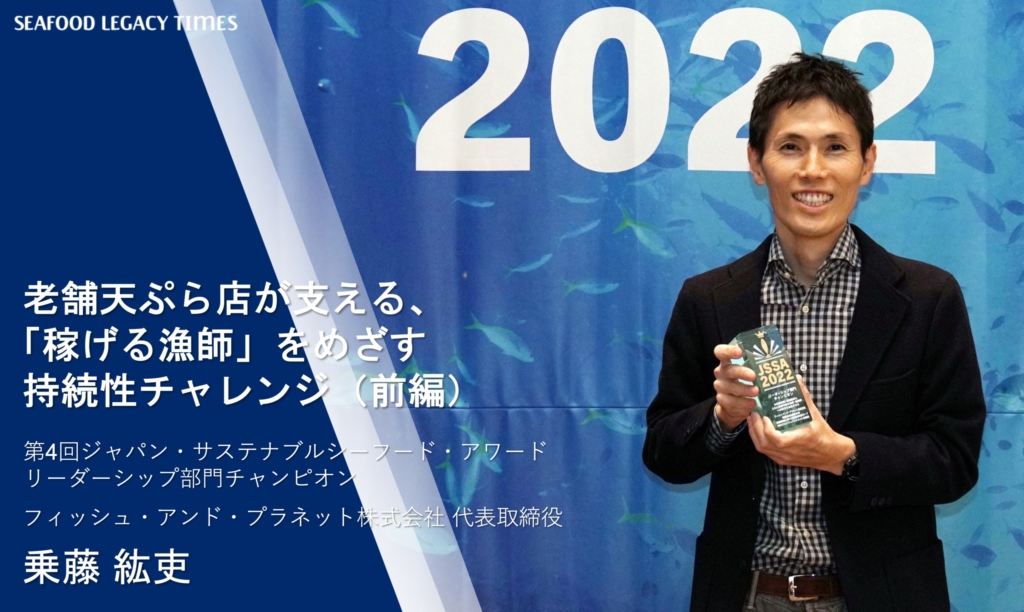

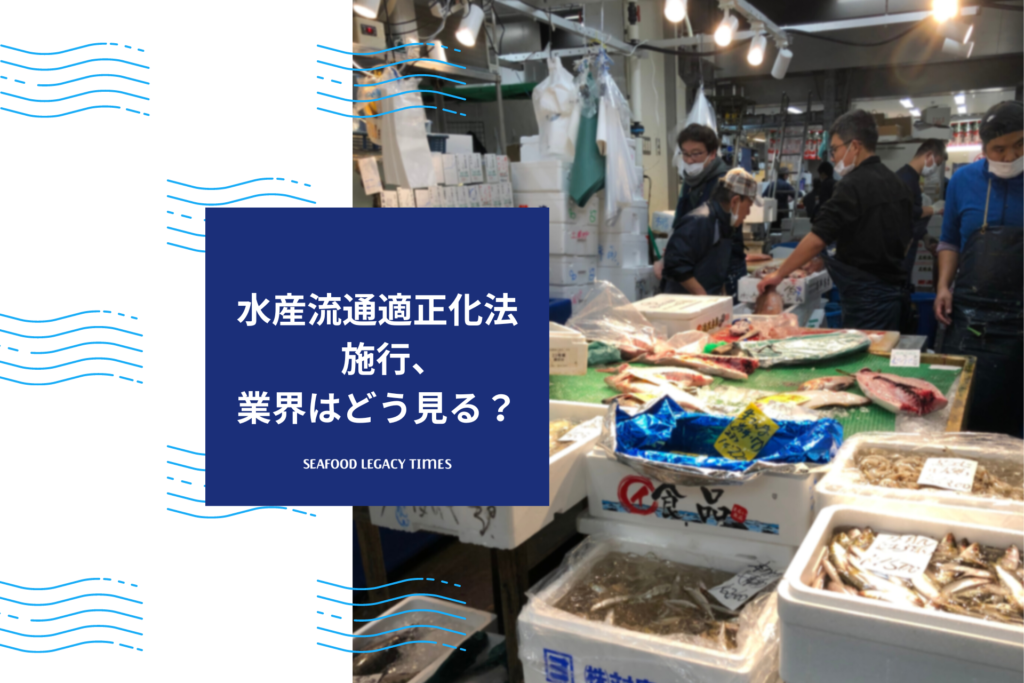
-2560-×-1536-px-1024x614.png)

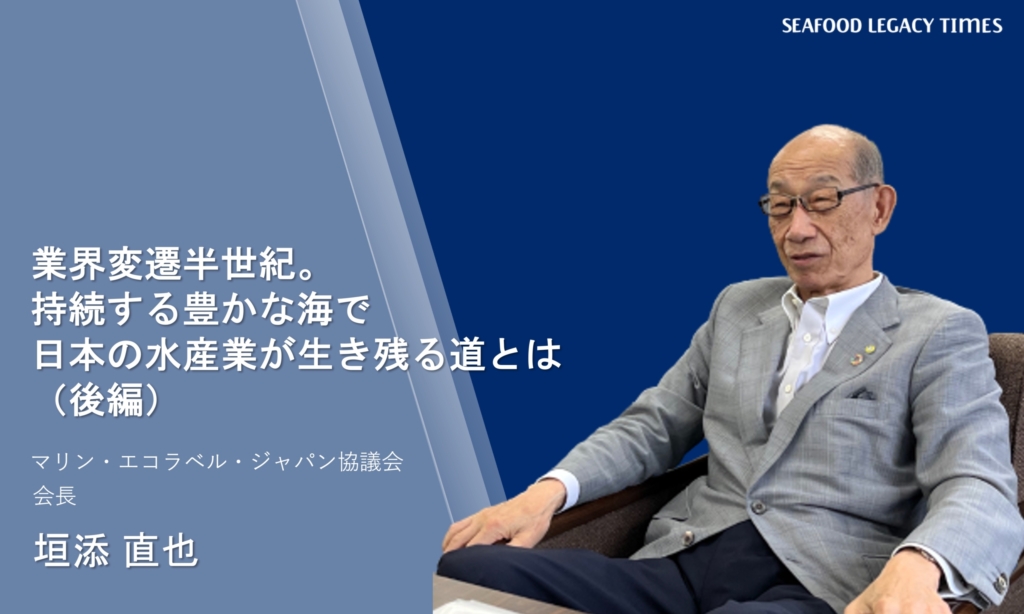

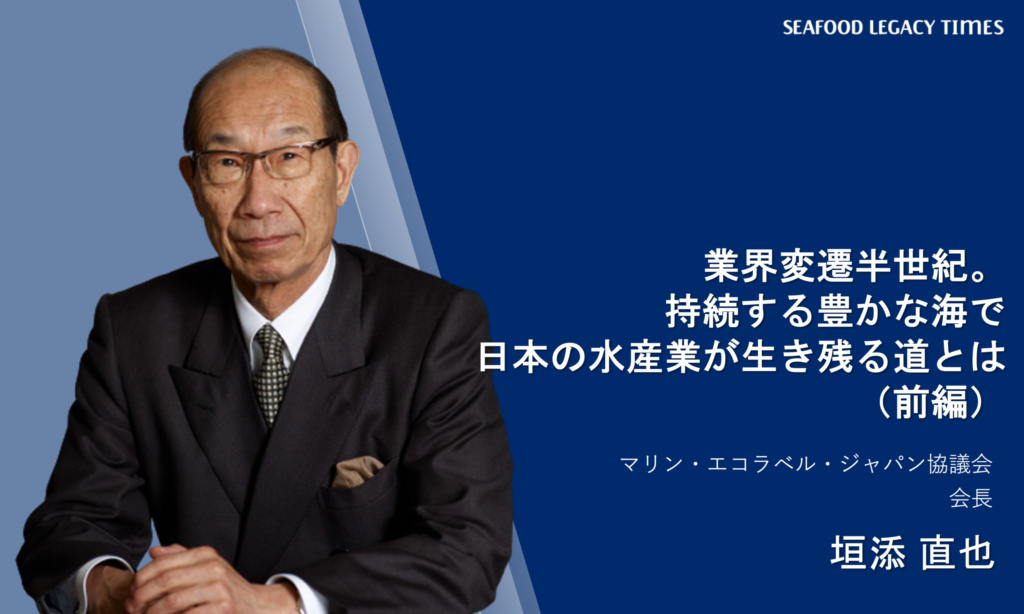







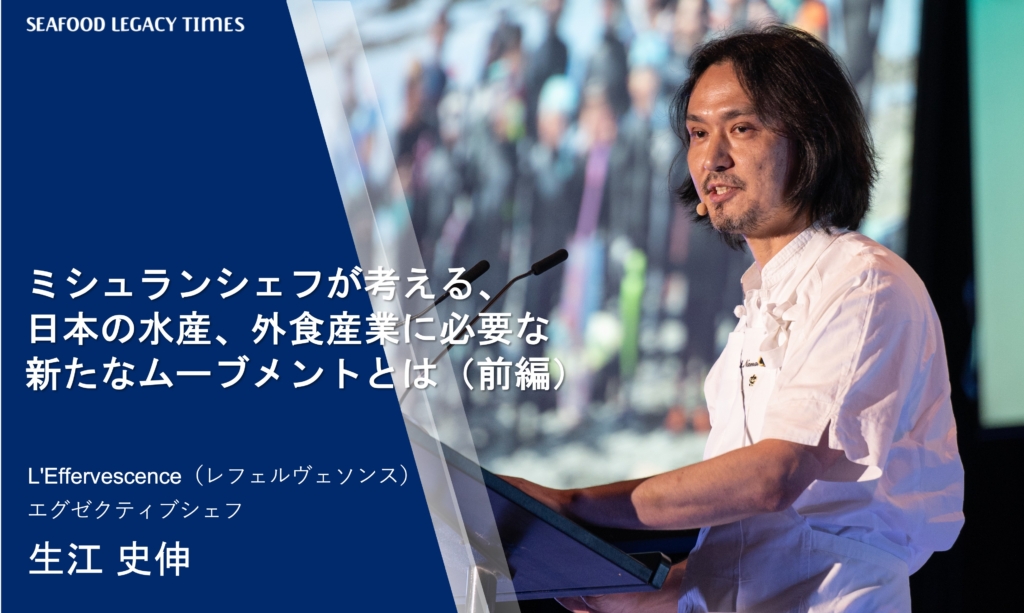






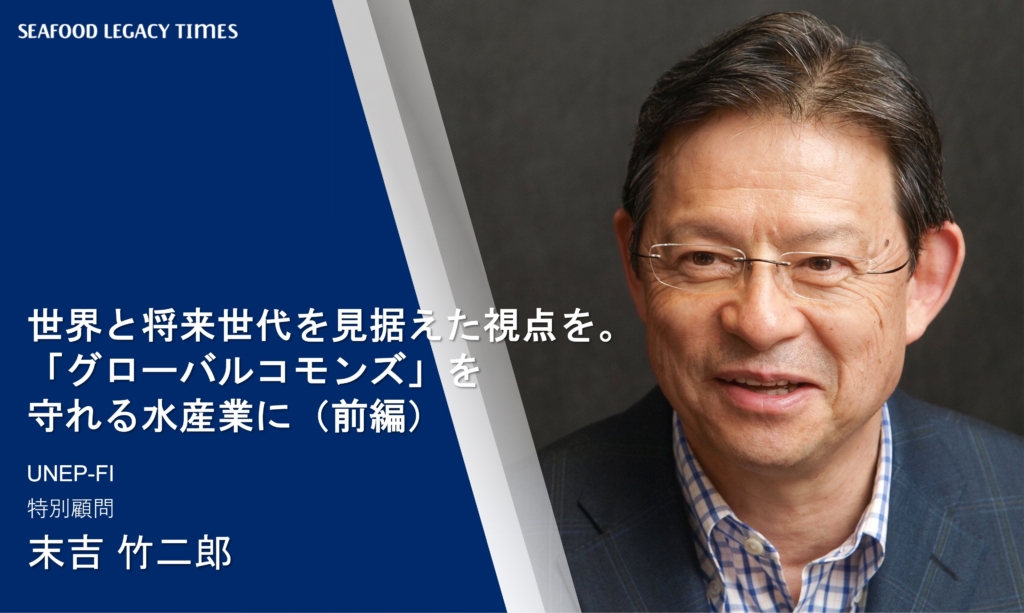









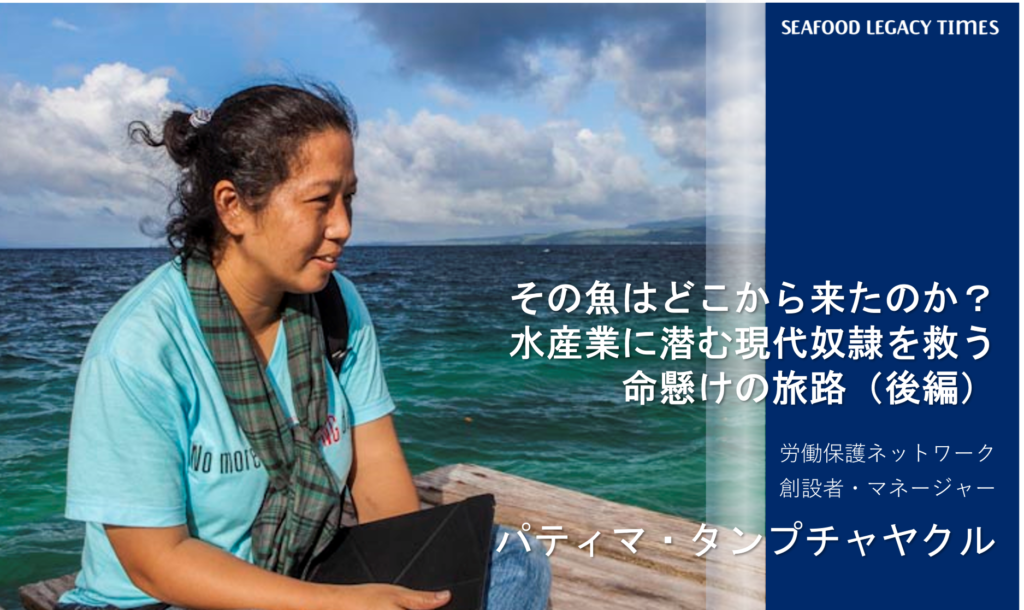

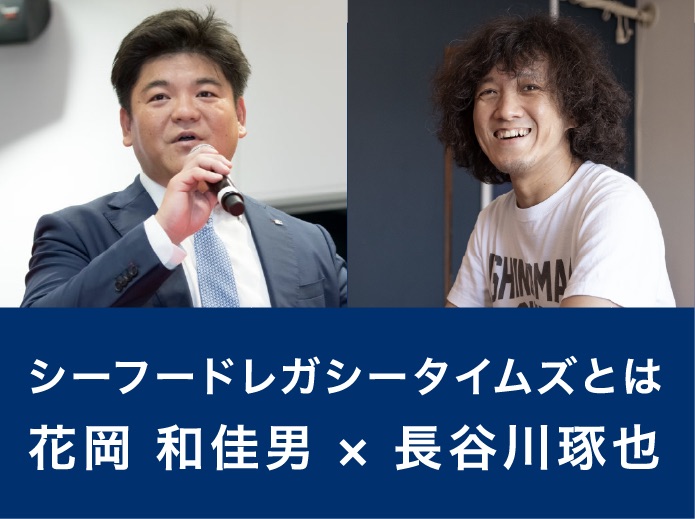
.jpg)