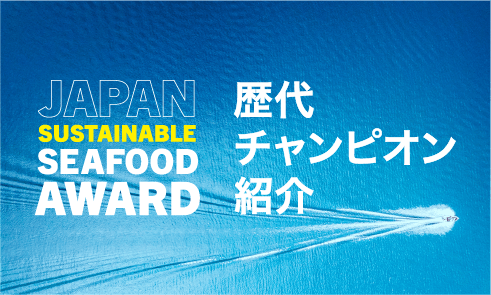日本は豊かな海に囲まれ、排他的経済水域(EEZ)は世界第6位の広さです。日本人はその恵みを享受し多様な魚食文化を継承してきました。しかし今、漁業者は「獲れない」、加工業者は「原料がない」、流通関係者は「売る魚がない」と悲鳴を上げています。世界では成長産業とも言われる水産業が日本では衰退産業と揶揄されるままでよいのでしょうか。
「よいわけがない」と語るマリン・エコラベル・ジャパン協議会 会長の垣添直也さんは、半世紀余り、水産業の節目をいくつも乗り越え、世界と日本の将来を見続けてきました。前編では、日本水産株式会社(以下、ニッスイ)経営トップを10年以上務めた垣添さんのビジネスマンとしての原点となった1960年代の捕鯨現場から見えたこと、そして、その後の資源保護の趨勢を語っていただきます。
垣添 直也(かきぞえ なおや)
1961年東京水産大学卒業、日本水産(株)入社。1999年~2013年、同社代表取締役社長。この間、大日本水産会副会長、日本冷凍食品協会会長、日本冷蔵倉庫協会会長、日本輸入食品安全推進協会会長、食品産業中央協議会会長を歴任。2016年よりマリン・エコラベル・ジャパン協議会会長。
―― 入社してすぐに捕鯨事業に志願されたそうですね。それはどのようなお考えからでしたか。
グローバルな資源の中で、クジラは戦前から資源管理が行われており、戦後も厳しく管理されていました。当時、捕鯨は花形でしたが、食料資源ではなくなってしまうとすでにささやかれていたのを学生時代から知っていたので、早いうちに現場に行っておきたいなと。
―― 何年ぐらい捕鯨部門におられたのですか。
13年いましたかね。南氷洋、北洋、日本近海とサウスジョージア島と。
100年以上前に南氷洋で捕鯨が盛んになった当初は、ヨーロッパから行きやすいところを航行しました。アフリカの西側を通って南下したら、その先にある南大西洋にクジラがいっぱいいた。南大西洋の真ん中にある絶海の孤島がサウスジョージア島です。
イギリス領ですが、ノルウェーの会社が、多いときは10ヶ所ぐらい基地を作って捕鯨船を出していたんですね。イギリスはけしからんとノルウェーを追い出して基地を接収しました。苦境に立たされたノルウェーは母船式捕鯨に活路を求め、そうすると沖で獲りますから、今度は陸上に基地を持つイギリスが競争で不利になりました。
 1960年代の捕鯨現場を振り返る垣添さん(写真撮影:山岡未季)
1960年代の捕鯨現場を振り返る垣添さん(写真撮影:山岡未季)
日本はクジラの肉を利用するオペレーションをやっていましたが、海外は鯨油が目的だったんですね。人造バター、つまり、マーガリンを作るための最も良い原料は鯨油だったんです。だから、私が行っていた頃の一番いいお客さんはユニリーバでした。石鹸とマーガリンをつくる最大のメーカーです。今でこそ鯨油を使いませんが。
―― 昔は鯨油で作っていたのですか!?
ちょうど口溶けの温度がバターと同じぐらいで、マーガリンをつくるには鯨油が一番良いと言われ、特別な値段で取引されていました。だから、欲しかったのはイギリスやドイツで、人口が少ないノルウェーにとっては、輸出のための大事な産業でした。そうやって獲ると獲り過ぎてしまうので、処理ができないわけですよ。処理能力を超えたときは、鯨油が多くて取りやすいところだけ使って、骨なんか捨てちゃう。そんな骨が累々と横たわっていました。
そういうことを二十代で見ちゃったわけです。こんなことをやっていたんだと。

―― サウスジョージア島の捕鯨の最盛期は1920年代だったそうですが、その跡の様子を1960年代にご覧になったわけですね。
はい。ああ、この人たち、ええカッコしてるけど、やってることはひどいじゃないかと思いました。後を追った日本が乱獲していると言われてもね。
―― クジラの資源管理はどのように行われていたのでしょうか。
当時は獲ることが大事だったわけです。やっぱりたくさん獲りたいんですよ。それが漁師。自由に獲れた時代もありましたが、そんなことをやっていたら、クジラがいなくなるよと、それで戦前から皆さんでルールをつくりました。オリンピック方式というのは、全部で1万頭獲ると決めたら、1万頭の範囲内では早い者勝ちなんです。国別割り当てなどは後からできるんですけど。
日本もそうでしたが、捕鯨船が母船の船団長の言うことをきちんと聞くようになったのは、ずいぶん後になってからです。それは、国別の割り当てが決まり、会社ごとの割り当てが決まってからです。そうなって初めて、その中でいかに経営するかを考えるわけです。
例えば、一日のうち午前中に何頭獲って、あとは休んでいなさいというふうに割り当てるようになる。そうでないと結局、明日の分まで獲ってしまうんですよ。すると翌日の朝にはもう鮮度が落ちてしまってる。
欧米の人たちが進んでいて、日本がそうじゃなかったということではなくて、むしろ、近代捕鯨、漁業としては彼らが先に乱獲をやって、しかし、その後で日本も同じようなことをやったということだと私は思います。
―― 1961年にニッスイに入社して2012年に社長を退任されるまでの50年余り、ご自身の中でとくに印象に残っていることを教えてください。
二十代で経験した捕鯨事業は非常に印象に残っていますよ。もう一つは、ずいぶん年月が経ってからですが、1990年代に参加した国際会議のことですね。
グランドフィッシュ・フォーラム(インターナショナル・グランドフィッシュ・フォーラムが主催)という会議があり、ヨーロッパの漁業者や加工業者の集まりから発展して、資源学者や流通業者も入って100人ぐらいで水産業について議論していました。私は95年に、ニュージーランドの会社の紹介で参加したんです。まだニッスイの社長になる前でした。
―― アジアの国が招かれたのですね。
メンバーとしてではなくゲストです。で、びっくりしたんですよ。ここまできているのかと。その会議の場で96年に、今の海洋管理協議会(MSC)が、こういう認証制度をやると皆さんに発表したんです。その活動を支援したユニリーバは、もう鯨油からマーガリンや石鹸をつくる会社ではなくて、総合食品会社として、特にヨーロッパでは冷凍食品のフィッシュスティックを大量に販売していました。
―― 衣をつけてフライにするスティックですね。
その主原料がアトランティック・コッド(マダラ)ですが、原料となる資源を守ることは、ユニリーバにとって自分たちの主力事業を守ることを意味します。すでにカナダのグランドバンクのアトランティック・コッドが乱獲で壊滅状態でしたから。水産資源を大事にしなくてはという話が世界の趨勢になると、そのとき私は直感しました。
 1990年代から開催されているグランドフィッシュ・フォーラム。2019年には第28回フォーラムがドイツ・ベルリンで開催された。(写真提供:垣添直也)
1990年代から開催されているグランドフィッシュ・フォーラム。2019年には第28回フォーラムがドイツ・ベルリンで開催された。(写真提供:垣添直也)
―― FAOの「責任ある漁業のための行動規範」が出たのは1995年でしたね。
ええ。あの辺で一気にいくんですよ。1972年にローマ・クラブの『成長の限界』が出版され、第1回の国連人間環境会議がありました。そこから始まって、10年経つと1982年。国連海洋法条約が決まった年ですね。発効したのはもっと後ですが。
その10年後、92年のリオの地球サミットでは、一般的なエコラベル認証制度が、自然や資源を守るのに有効であるということが合意され、いちばん先に動いたのがカナダの木材関係でした。1993年にFSCができてカナダ全体で急速に動いたのを見て、その認証制度をコピーしたのがMSC。いや、仕組みをコピーするのは全然悪くないんです。
―― 水産分野にも広がったわけですね。
96年のグランドフィッシュ・フォーラムで、MSCが水産エコラベルの構想を発表したら大騒ぎになった。北欧の漁業者たちは、ユニリーバがお客さんだから認証制度はダメとは言えませんが、スペインの連中は大反対でした。スペインの魚食文化で食べるのはメルルーサのような南方系の魚で、資源状態が北欧のタラほど危機的な状況ではありませんでしたから。しかし、反対しようがしまいが97年にスタートして、でも初期のMSCはすごく苦労しましたね。
―― なかなか認証が広がらないという苦労ですか。
そうです。そう簡単にはいかない。知っている人がいないわけだから。認証制度を知っているとか、科学的な水産資源管理をするといったことは、それからMSCの努力の下、広がっていくわけです。
―― 当時ニッスイの社内はどんな状況だったのでしょうか。
ニッスイの遠洋漁業は事実上終わっていました。サケ・マスの最後の漁船団がなくなったのが1988年です。ただ、現地会社をつくってそこに船を移して漁獲できる国がいくつかありました。

アルゼンチンやチリは、100%外国資本でも、その国の会社にしたら魚を獲れたんです。ニュージーランドは50%、アメリカは25%しか資本を持てないルール。そこで、合弁会社をつくって船を移しました。だから、日本から言えば遠洋漁業ですが、向こうに行けば沖合漁業です。
―― そうすると、漁業はもっぱら海外の沖合で、日本国内では販売や加工の事業に集中していったということですか。
自分で獲れない時代になってきたから、もうしょうがないですよね。アラスカにも会社をつくりました。かつて、スケソウダラをニッスイだけで100万トンぐらい獲っていたんです。それを自社のトロール船や母船で処理してすり身にして日本で売る。それによって日本の練り製品産業が発展したわけですね。
アメリカはそれを見て、当初はアメリカの漁船にスケソウダラの獲り方を教えて獲った魚は日本の母船で買い取れという要求をしてきました。つまり、漁船はアメリカ、加工は日本という事業を考えました。それを我々はジョイント・ベンチャーと呼んでいたのですが、そうこうするうちに、アラスカに加工工場をつくれということになり、儲かる部分は資源を持っている国が取る。だから、今までのように魚を獲ることが即、利益を生むわけではなくなるという話です。

―― 水産資源を守っていくという流れは社内ではどう受け止められましたか。
「サステナブル」という言葉がメジャーになってきたのは2005年ぐらいでしたか。2006年に、これから将来に向けてサステナブルな仕事をしていくという方針をつくったら、国内の営業部門が大反対しました。「社長、そんなことやったら売るもんなくなっちゃいます」と。
―― 反対に遭われて、みなさんの考えをどうやって変えていかれたのですか。
反対されたら簡単にはいかないですよ。「面従腹背」という言葉もあるんだから。しかし、現実問題として時代がどんどん変わっていきます。ですから、私はずーっと世の中の流れをプレゼンし続けてきました。毎年、年頭の方針を作りますし、11月には国内外のグループ会社の代表を集めて経営会議をやっています。世の中で起きていることを繰り返し繰り返し話していくということですね。
私が社長を退任したのは2012年ですが、2018年あたりからガラッと変わりました。ニッスイをサステナビリティに取り組む会社にしますと。2006年に「そんなことやったら売るもんなくなります」と反対した人たちが、そのとき会社を牽引する立場になっていました。
(後編に続く)後編では、ニッスイで10年以上経営トップを務め、2016年からはマリン・エコラベル・ジャパン協議会会長に就任した垣添さんに、日本の水産業の課題と処方箋を語っていただきます。
取材・執筆:井内千穂
中小企業金融公庫(現・日本政策金融公庫)、英字新聞社ジャパンタイムズ勤務を経て、2016年よりフリーランス。2016年〜2019年、法政大学「英字新聞制作企画」講師。主に文化と技術に関する記事を英語と日本語で執筆。










































-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)


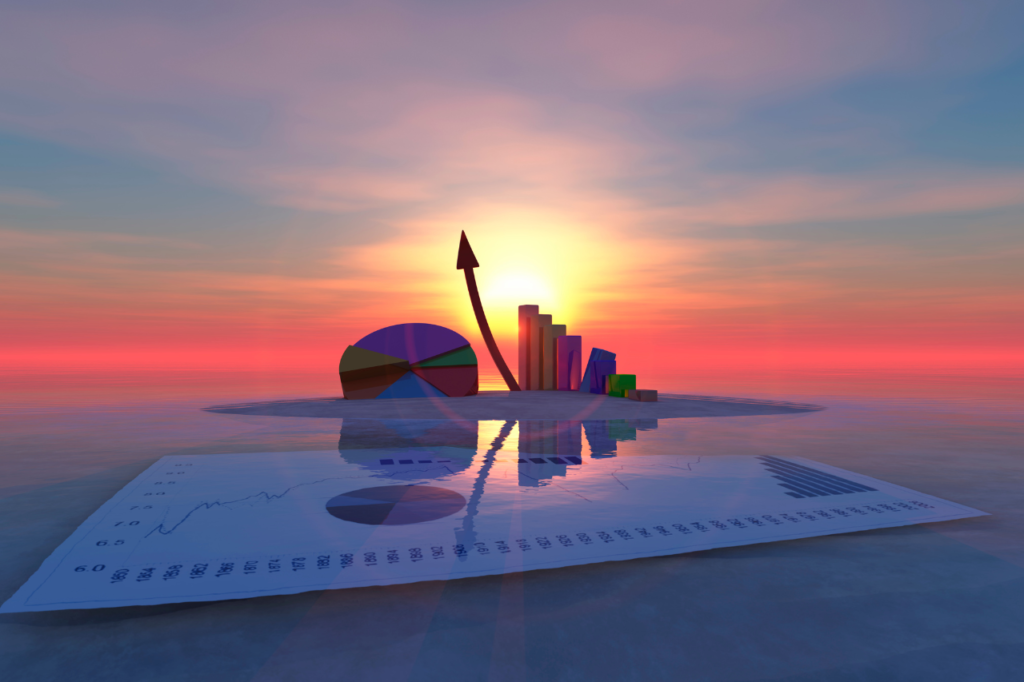










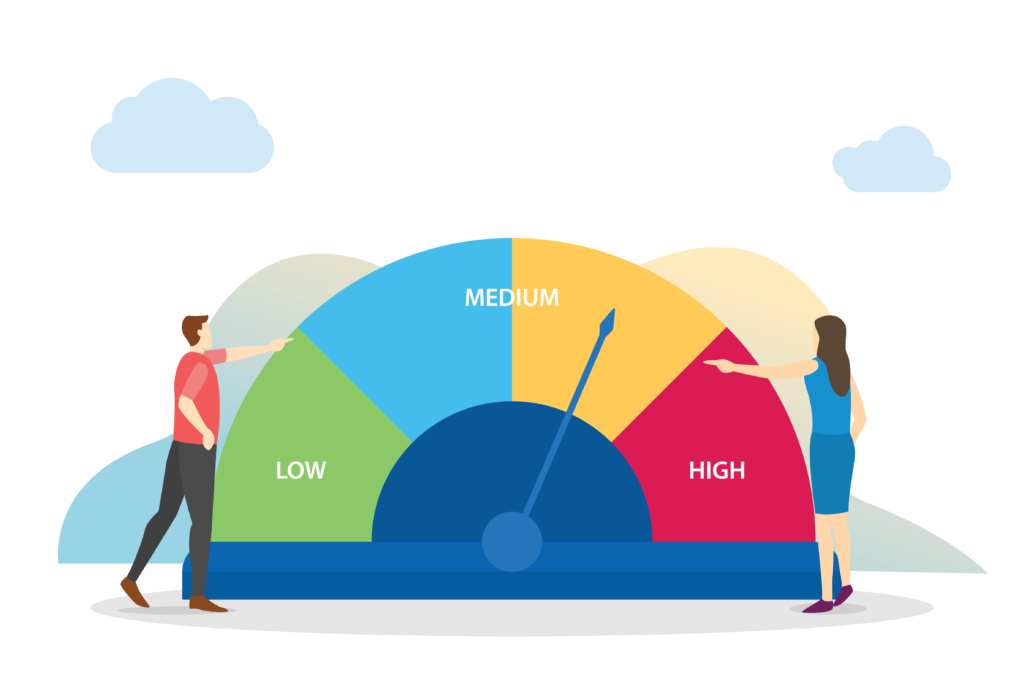

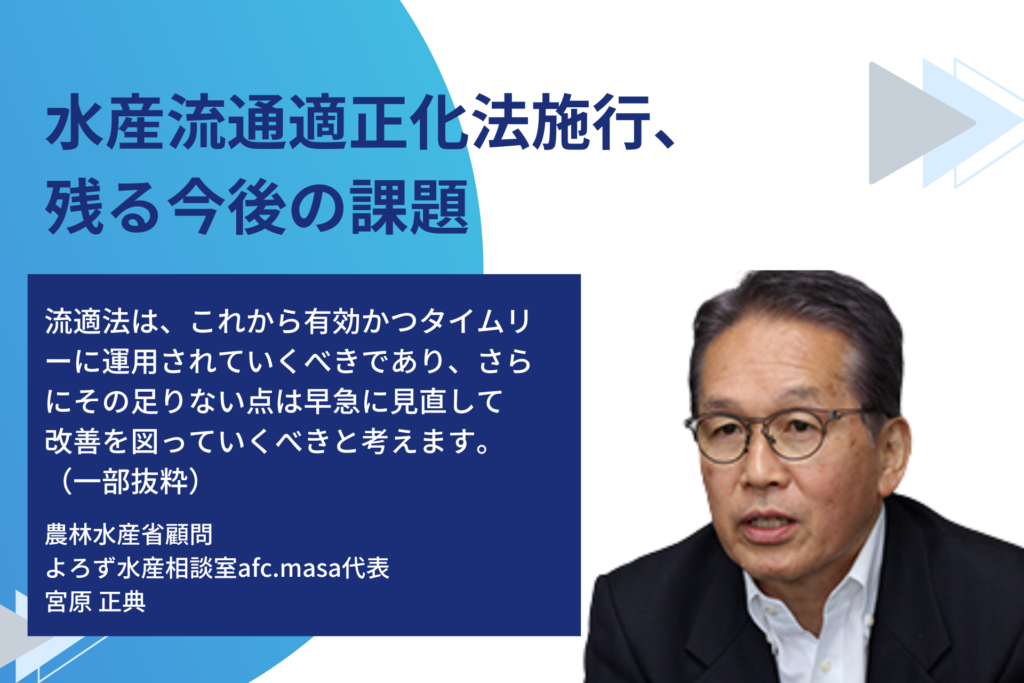











-2560-×-1536-px-1024x614.png)































.jpg)