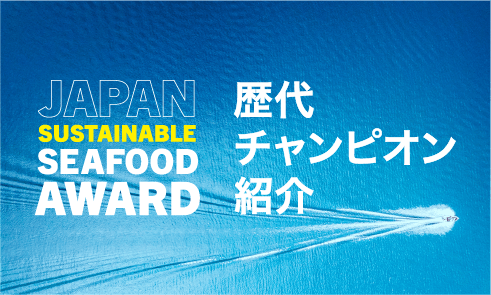サラダに入れたり、サンドイッチにしたり。私たち日本人にとっても身近なツナ缶。そのツナ缶がもっとエシカルなものになるようにと奮闘している企業があります。それが今回ご紹介するタイ・ユニオン・グループ(以下、タイ・ユニオン)です。
タイ・ユニオンは世界のマグロの供給量のほぼ5分の1を生産している世界第三位の水産会社であり、世界最大手のツナ缶メーカーで欧米や中国のメジャーな缶詰ブランドを所有しています。また、エビやイカなどの魚介類の冷凍製品やキャットフードなどのペットフードも手がけ、世界的な水産加工品会社として知られています。
そのタイ・ユニオンが、2021年2月、環境対応型融資「サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)」で400億円超を調達するというニュースが報じられました。融資をするのは、みずほ銀行と三菱UFJ銀行、そして三菱UFJ傘下のアユタヤ銀行。日本の金融機関が多くかかわっています。
サステナビリティ・リンク・ローンとは、借り手のサステナビリティの取り組みの達成状況に応じて、金利の引き下げなど融資条件が優遇される仕組みです。今回の場合は、企業の持続可能性を測る「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス」で高い評価を維持すること、温室効果ガスの削減目標を達成することに加え、IUU(違法・無報告・無規制)漁業との関わりや漁業従事者の人権確保状況などについてトレーサビリティーの強化をはかることがあげられています※1。

タイ・ユニオンは、世界的な社会的責任投資(SRI)評価会社である米国のS&P グローバル社によるサステナビリティ評価の食品業界部門において昨年、世界第1位を獲得するなど、サステナビリティに熱心な企業です。しかし、かつて、2015年頃には、タイ・ユニオンが使用している魚介類を獲っている漁業現場が人身売買や強制労働、搾取や暴力といった人権問題を抱えていることがメディアやNGOによって指摘され、国際社会から厳しい非難を受けました※2。
しかし、その後すぐに抜本的な対応策を実施。国内外の政府機関やNGOなどと協力して、労働者の人権を守るという方針を社内外に周知徹底したり、従業員やサプライヤーなどに対して労働者の権利について研修を実施したりしました。また、サプライヤー管理の徹底、通報制度の確立、被害者支援などにも積極的に取り組んでいきました。
2016年にはサステナビリティに関する取り組みを広く世界に伝えるウェブサイト「SEA CHANGE」を公開。安全で合法な労働、責任ある調達、責任ある運営、人と地域、という四分野について2020年までの目標を設定し、取り組みを展開しました。結果はまだ公開されていませんが、達成状況、今後の展開が気になるところです。
SEA CHANGE https://seachangesustainability.org/
 SEA CHANGEの概要(タイ・ユニオンのホームページより)
SEA CHANGEの概要(タイ・ユニオンのホームページより)タイ・ユニオンの取り組みに学ぶべきポイントは二つあります。
まず一つ目は、常に野心的な目標を掲げ、チャレンジすること。たとえばタイ・ユニオンは、持続可能で健全な水産業の実現を目指す大手水産会社のプラットフォーム、SeaBOSにも参画し、2021年までにIUU漁業や児童労働の根絶といった課題にチャレンジすることを約束しています。こうした目標はなかなか一社では決断できません。
しかし、それを可能にするのが二つ目のポイント、さまざまなステークホルダーとの協働です。タイ・ユニオンが深刻な人権問題を数年間で大幅に改善できた背景には、政府機関やNGOも含めた、国内外のさまざまなステークホルダーとの協働によって専門的な知見や技術を迅速に得たことがあげられます。
今回、タイ・ユニオンが日本の金融機関から融資を調達できたのは多くのステークホルダーと協働しながら野心的な目標にチャレンジしてきた成果とも言えるでしょう。
サステナビリティの取り組みは一夜にしてなし得るものではなく、タイ・ユニオンも決して完璧ではありませんが、水産業界としていかにしてSDGs目標14「海の豊かさを守る」を達成すべきか、その一つのヒントになるのではないでしょうか。

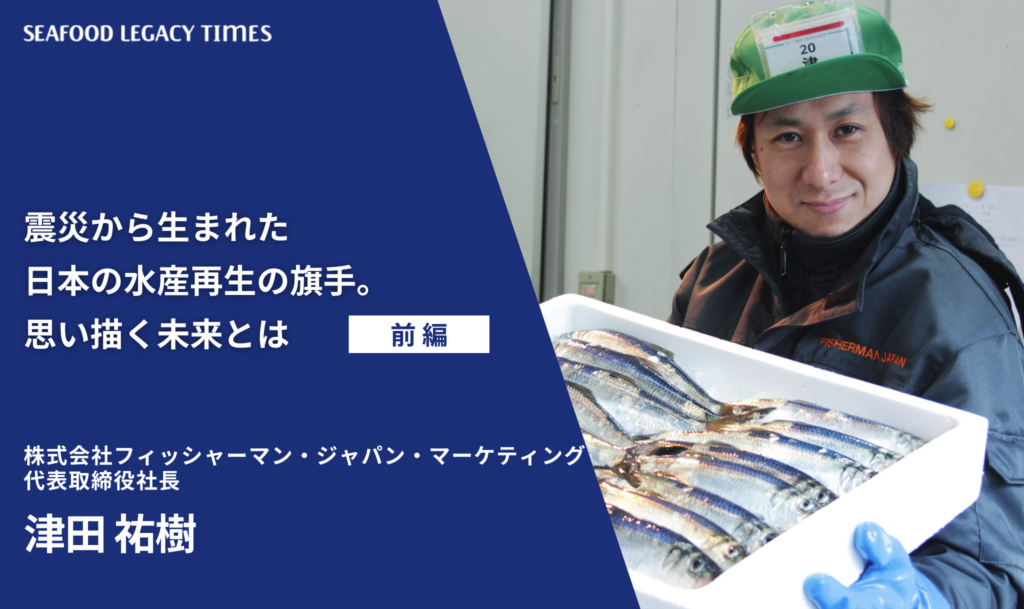























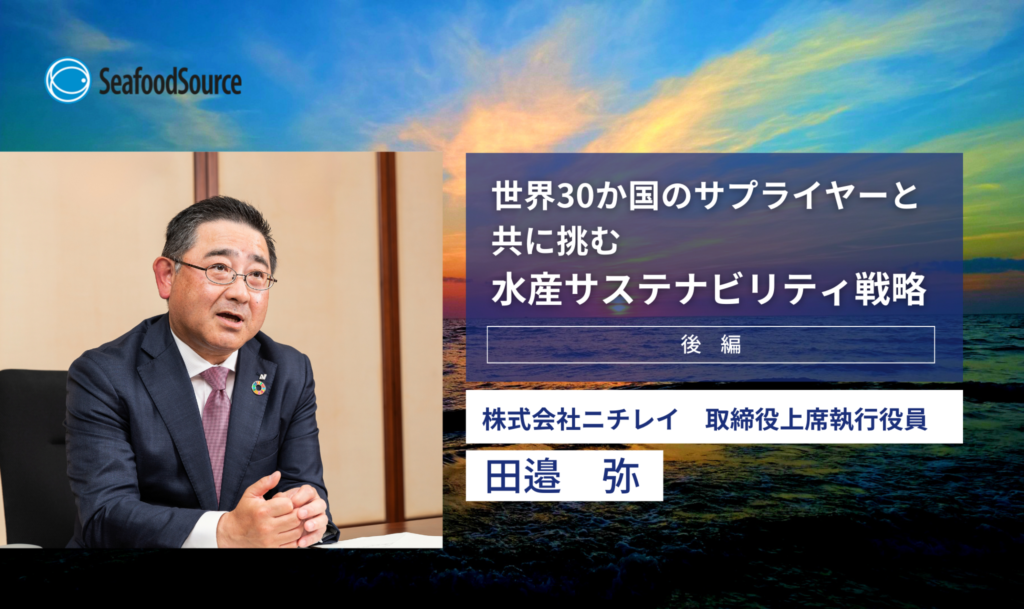
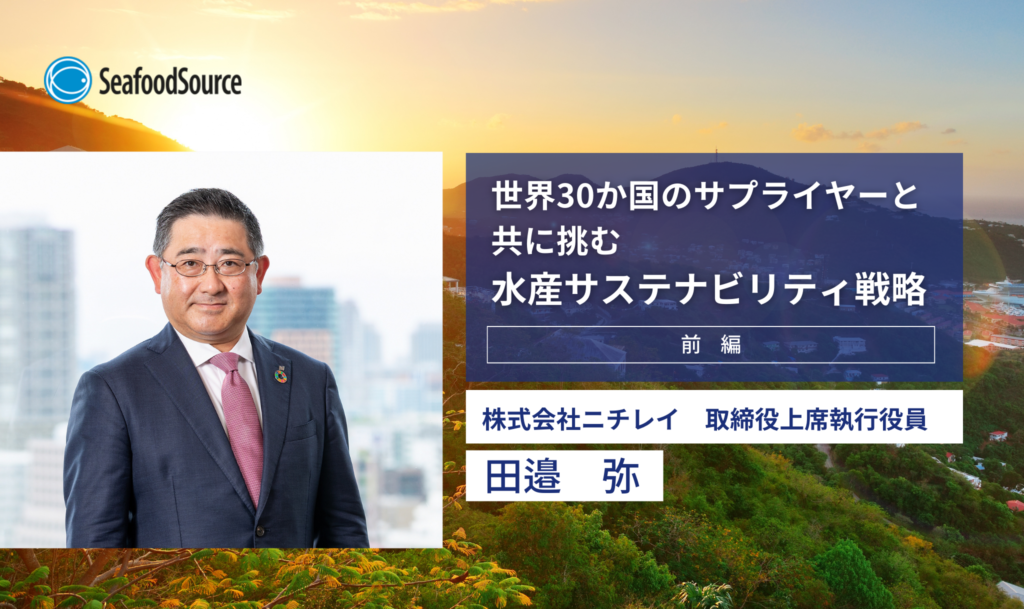










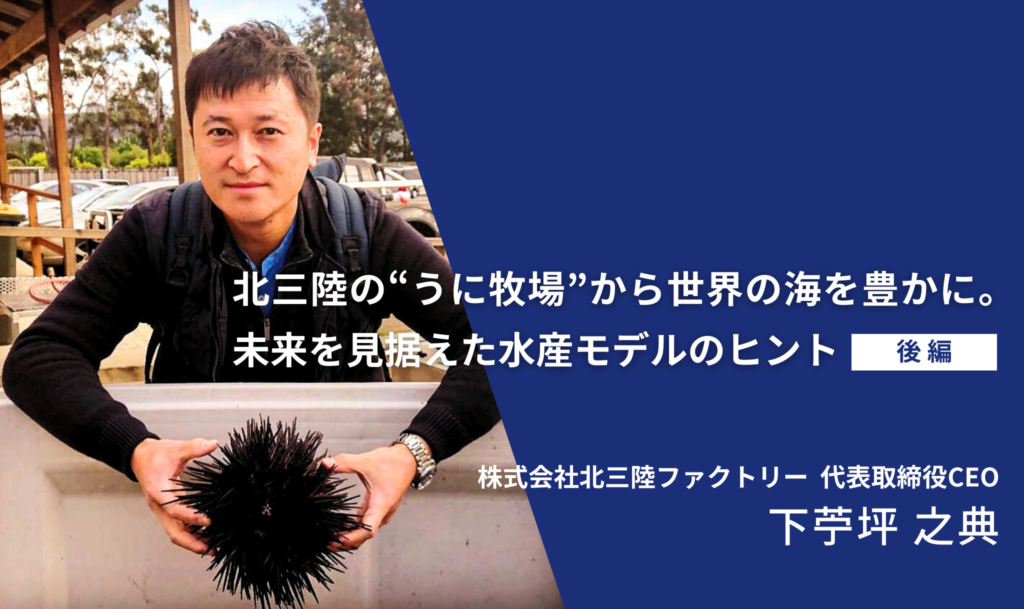




-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)

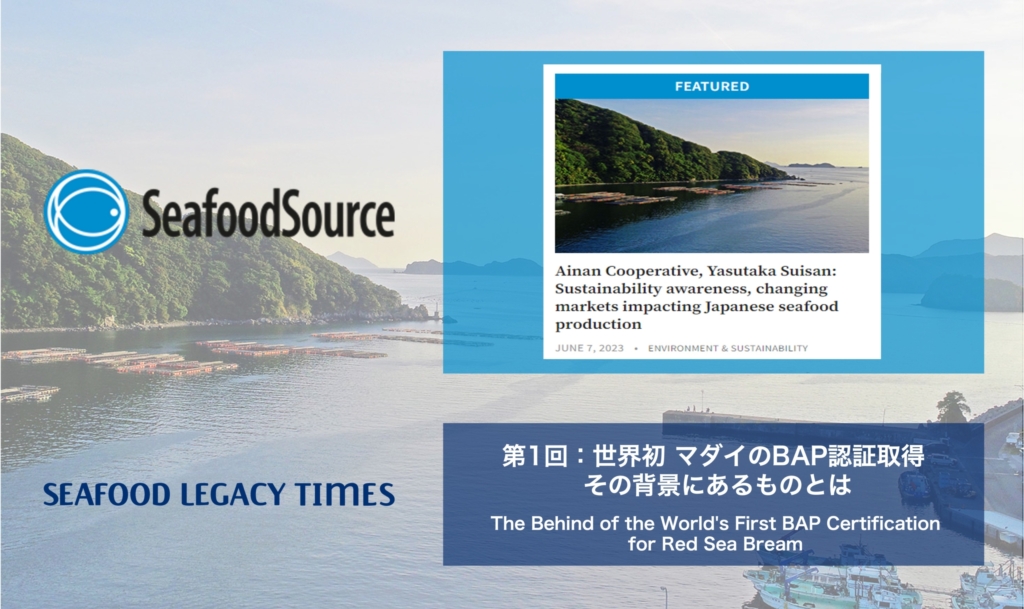
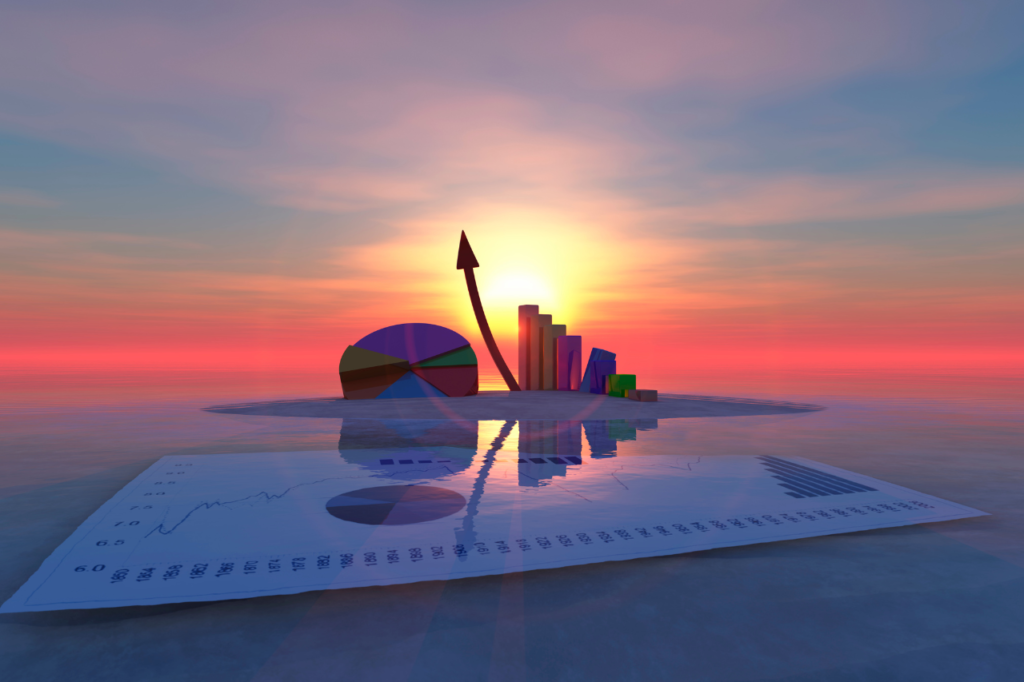










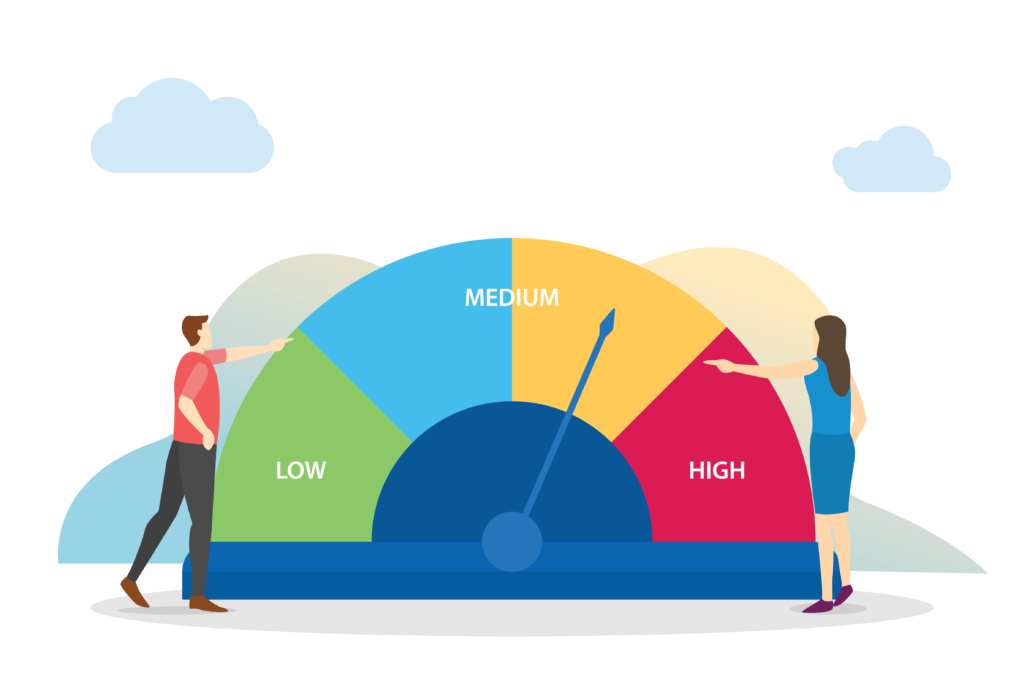

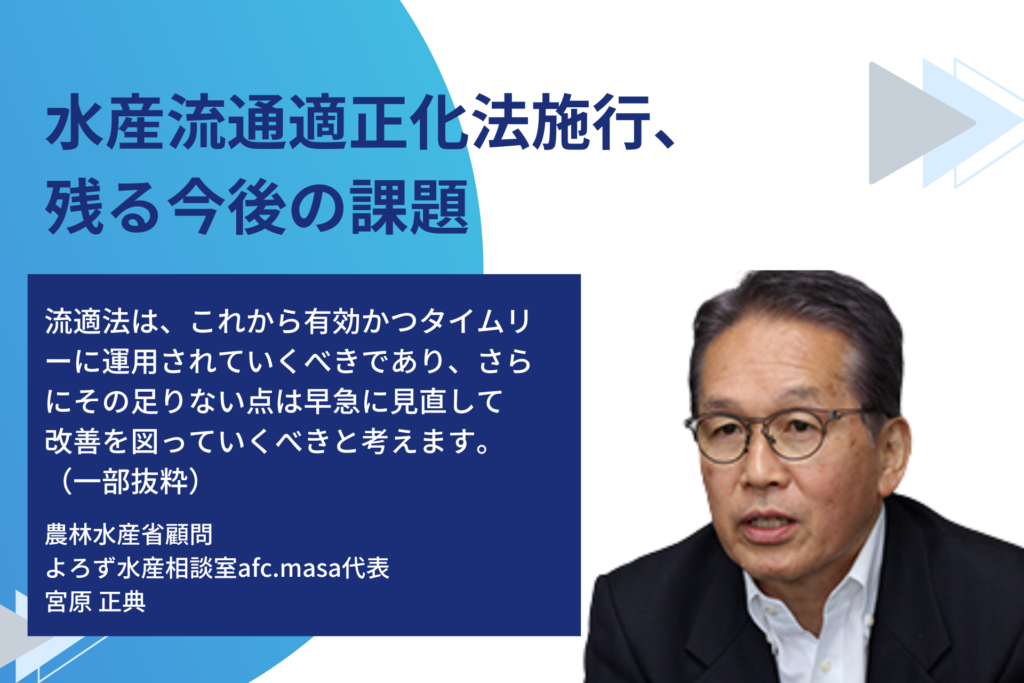
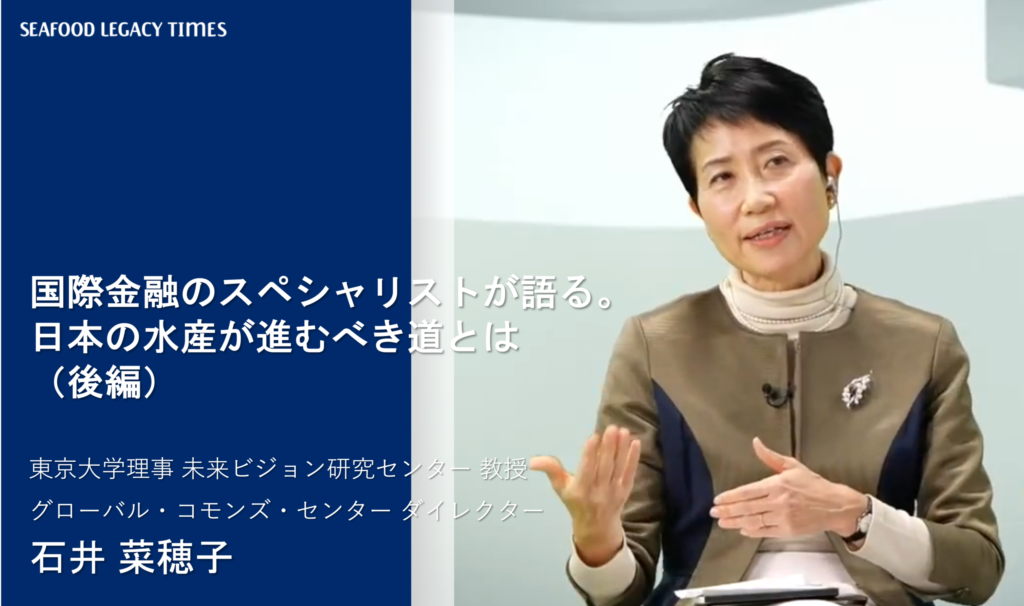


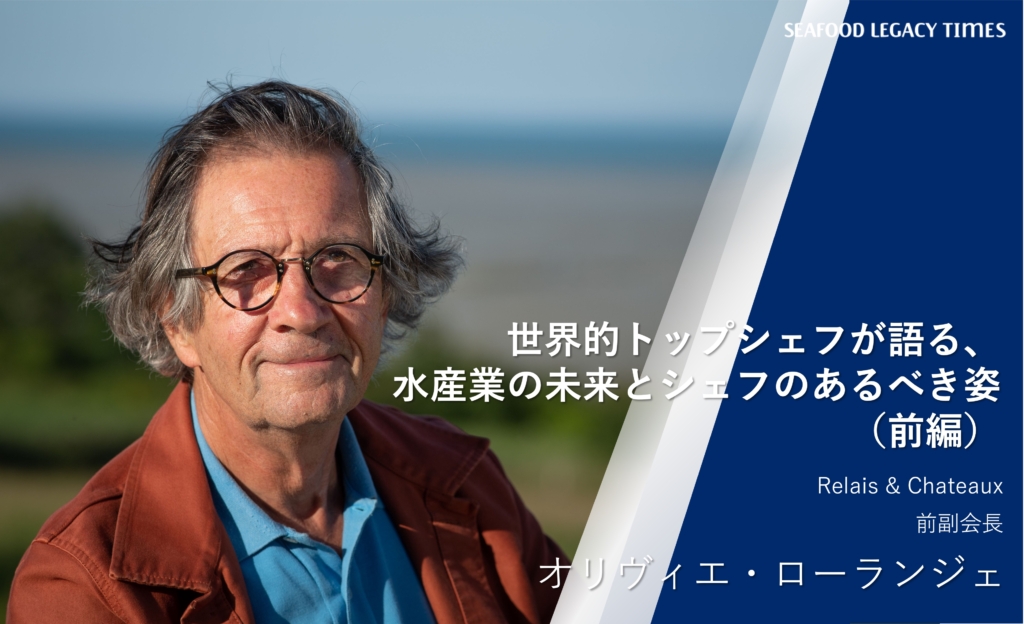



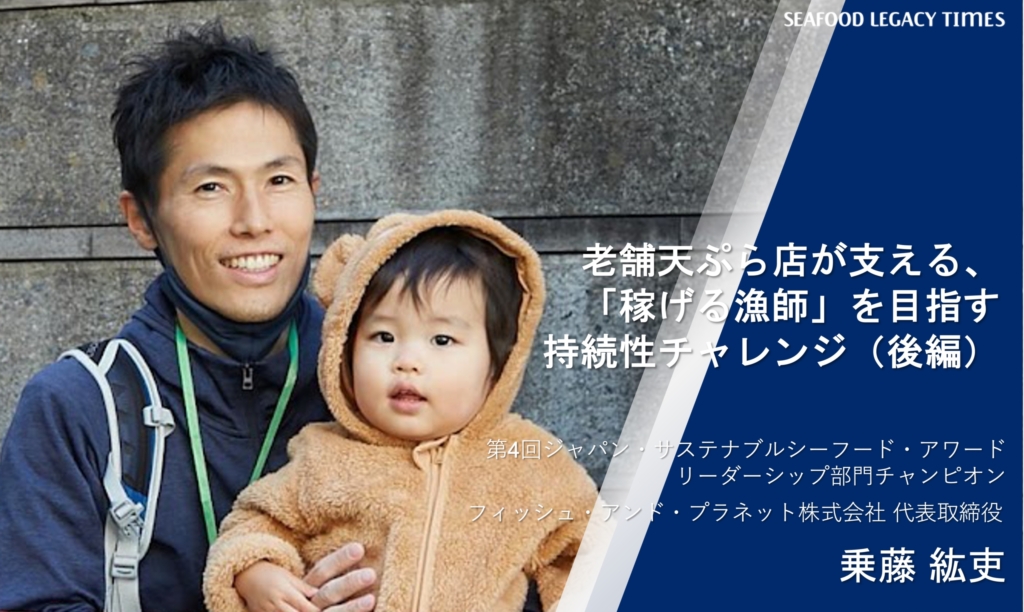
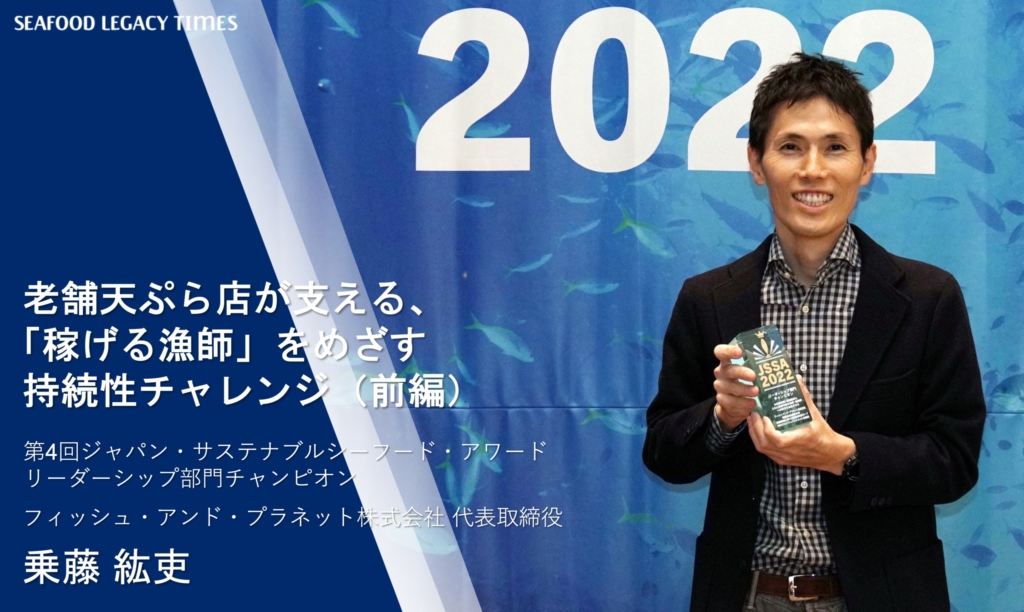

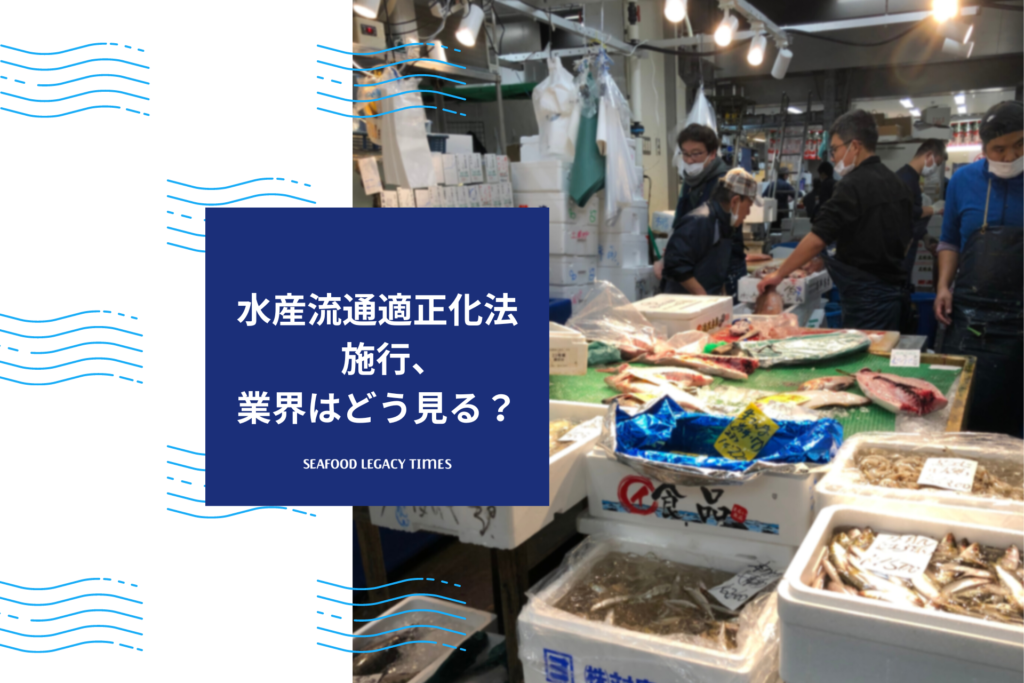
-2560-×-1536-px-1024x614.png)

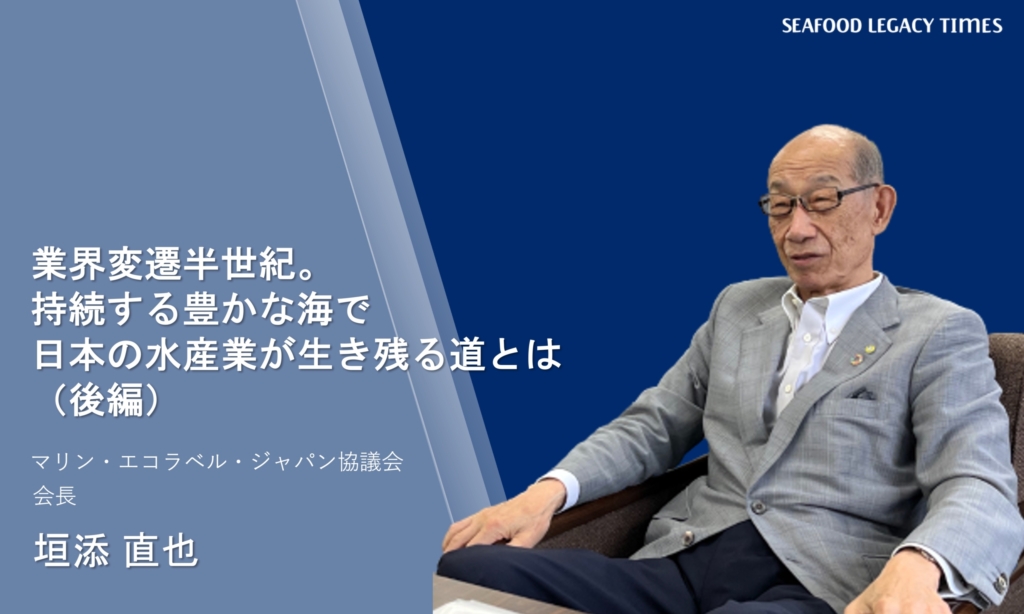

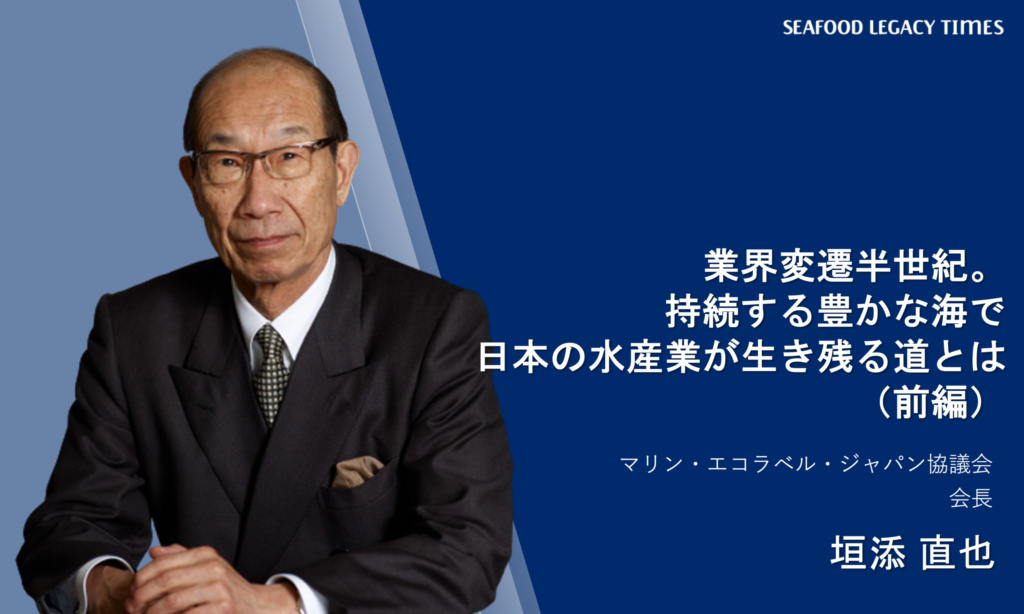







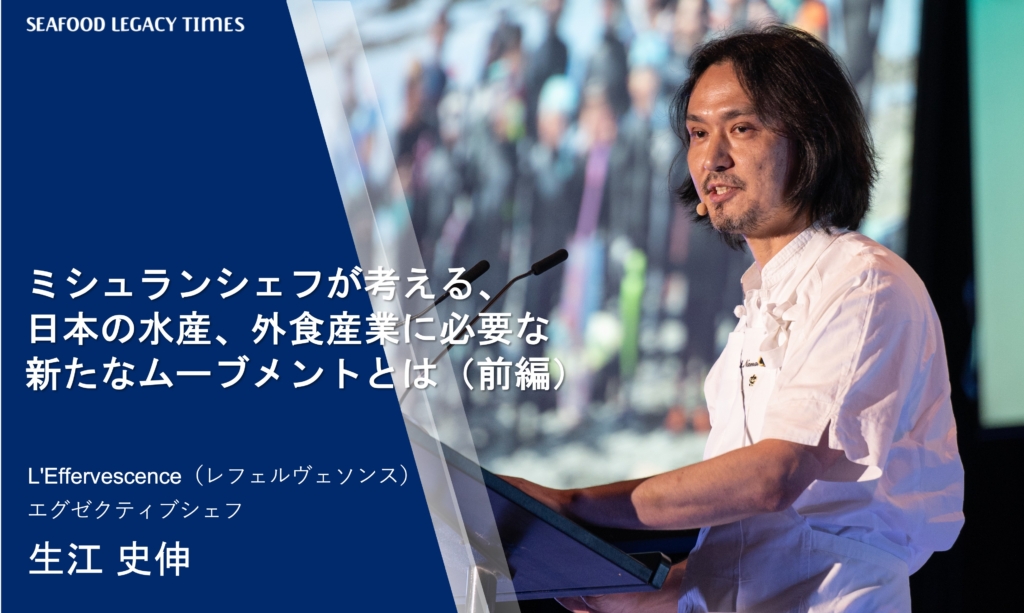






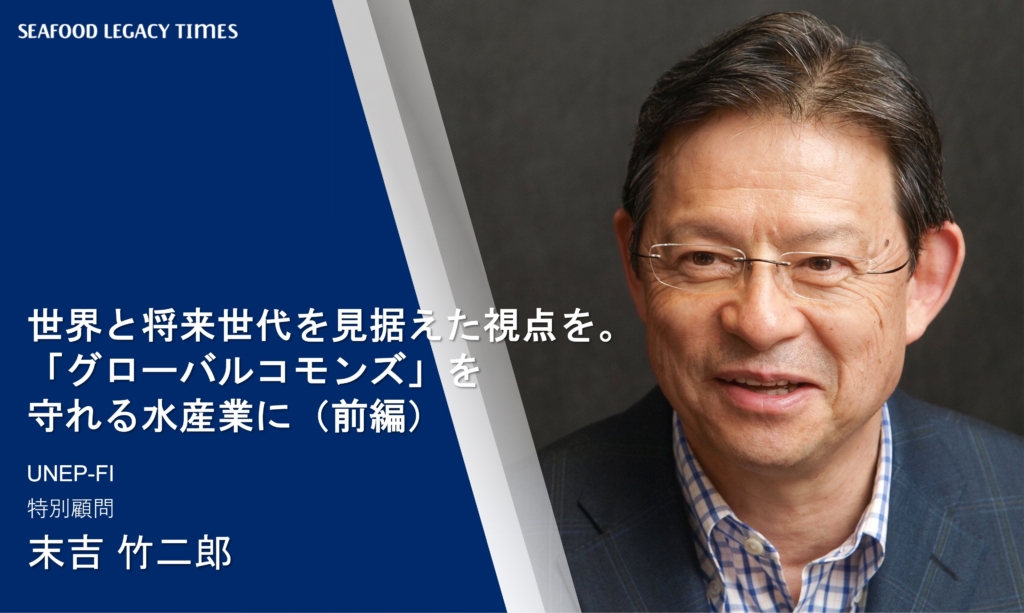









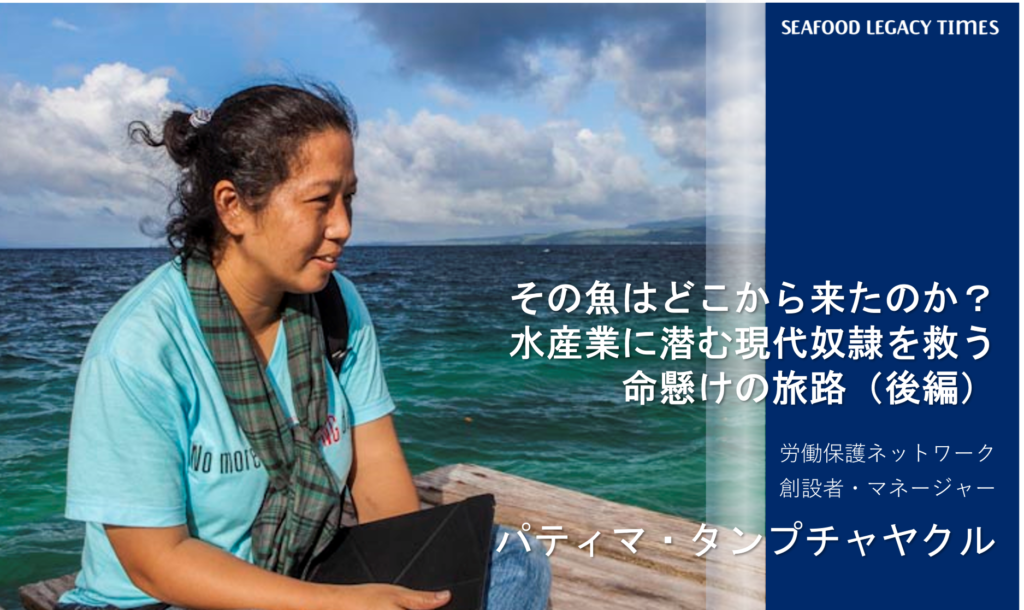

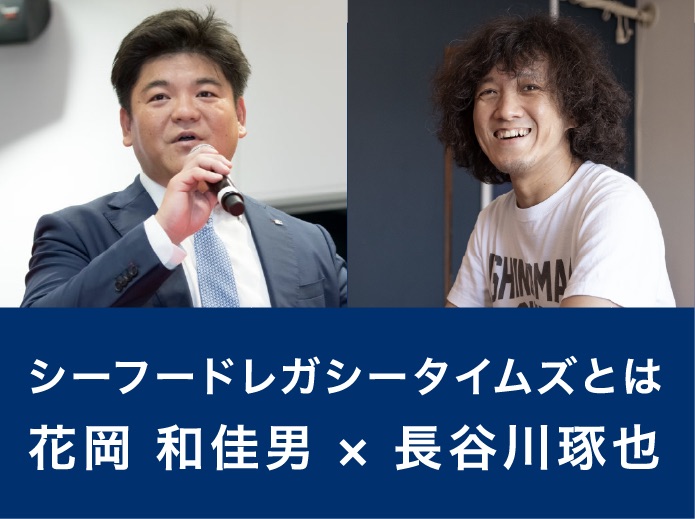
.jpg)