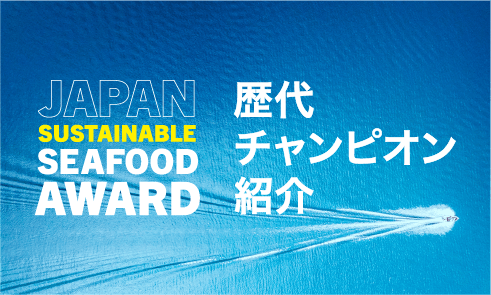世界最大規模を誇る豊洲市場の大卸を率いる伊藤晴彦さんと、持続する豊かな海を目指してソーシャルベンチャーを立ち上げた花岡和佳男。水産業界で模索を続けてきた二人が、2022年の年初に当たり、今後、日本の水産業はどう変わっていくべきか、前編に引き続き、電子トレーサビリティの導入をはじめ、課題と展望を語り合いました。(前編を読む)
花岡:世界中から豊洲市場に集まる魚の約25%を扱う中央魚類の部分のトレーサビリティを確保して、そこから豊洲市場全体やそのサプライチェーンも巻き込んでいくことができれば、日本のみならず、世界の水産物流通にとって、IUU漁業の撲滅や水産資源の回復の面で大きなステップになりますね。電子トレーサビリティの取り組みを進めていく上で、難しさはどういうところにありますか。
伊藤:難しいのは、変わることをあまり望まない人が多いということです。紙の伝票を使うなど、今の仕事のやり方で満足している人が非常に多いので、それを変える提案をしても、大きなメリットがないと、なかなか変えてくれません。そんなに大きなメリットがあるわけではなく、どちらかと言えば、一人ひとりが小さな取り組みをすることで全体が良くなるわけですが、それを説明して理解してもらうのは簡単じゃない。だからこそ、共感者をたくさんつくっていくことが、実現する第一歩だと思っています。
花岡:確かに共感者を増やすことは重要ですよね。システムの電子化により仕事の効率は向上しますし、そこに蓄積される膨大なデータの価値は計り知れません。これは課題解決の手段であると同時に、新たなビジネスオポチュニティですよね。さらに、豊洲市場内で差別化を図るのではなく市場全体で取り組むことで、収集するデータの量も価値も上げていくことができますし、市場自体の信頼性も上がってゆく。素晴らしい構想だと思います。ほかには、今後どのような課題を解決していこうとお考えですか。

伊藤:課題は山のようにあり、手をつけていないことも含めて申し上げると、まず、今までたくさん獲れていた魚たちの数が減っているということがあります。皆さんの間でも有名なのはサンマですね。サンマが減ったのは、気候変動による水温の上昇や外国との奪い合いの部分もありますが、サンマがまだ小さいうちに獲ってしまう現在の漁業管理が、本当に地球にとって一番良い方法なのか、かなり疑問があります。
地球温暖化の多くの部分は、人間が多くの化石燃料を燃やしてきた結果、もたらされたものだと思っております。そういう中で、自分たちはどうしていくのか。まだ明確に行動できていませんが、少なくともSDGsに則った活動を当社もしなければならないと強く思っております。
もう一つ課題を挙げますと、日本では今、一人当たりの魚介類の消費量が年々減っています。やはり、調理が簡単で値段も安価な肉の人気が高いわけですが、日本の魚食文化を絶やさないように、今後も継続的に魚を食べたい、食べようと思ってもらえるような活動に、早く着手したいと思っております。
花岡:水産資源の管理に関して、乱獲や過剰漁業については、どのようにお考えですか。
伊藤:例えば、サバは現在ノルウェーから日本全体で45,700トン輸入をしており、平均単価はキロ当たり220円ぐらいです。それに対して、銚子などで取引されている国産のサバ(輸出向け)は、キロ当たり110円(貿易統計・ノルウェー輸出統計より)というような低価格です。なぜ、そんなに価格差があるのか。
ノルウェーでは、資源管理をして脂の乗ったサバだけを獲るような仕組みがあり、選別もきちんとしているので、日本には良質なサバしか入ってこないのです。それに対して日本では、とにかく、脂が乗る前の小さなサバを巻き網で巻いて全部まとめていくらというような安価で、大概は先進国ではなくアフリカの国々に流れていくという取引になっています。これが本当に資源を有効に活用する国の取引方法なのかと思いますね。
ノルウェーのように資源管理をして、美味しく、高く評価される魚だけを漁獲し、小さい魚は漁獲せずに海で大きく育っていただき、育ったものを獲っていく。そういう当たり前のことが、日本ではできていないのです。ノルウェーの仕事の仕方を見習って、日本で育てたサバをたくさん、皆が食べて喜んでくれるような国にならなきゃいかんと思っております。
花岡:すごく共感します。サバは日本の周りにもたくさん泳いでいるのに、地球の反対側から輸入したサバが僕たちの食卓に並んでいて、僕たちの海で獲ったサバは、アフリカに安く売られていくなんて、本当にもったいない話です。輸送面でも温室効果ガスが余分に発生する悪循環があります。
漁業法が改正され、その実施に向けて水産庁は、MSY(※)ベースの資源評価やTAC魚種を漁獲対象とする大臣許可漁業へのIQ管理の導入を含む、2023年度までの新資源管理推進ロードマップを発表しています。これにより、サバのような問題は解決されていくとされていますが、その実現について、思うところがありましたらお聞かせください。
伊藤:現在はまだ完璧ではないかもしれませんが、それでも時代に合わせて変えていくと多くの方々が考えて、漁業法が改正されたのだと。そのことを否定しないで、自分も、本来あるべき漁業になるように、自分の立場でやれることを一つ一つやりたいなと思っています。

花岡:豊洲市場は、今後どのように変わっていくべきだとお考えでしょうか。特にサステナビリティの観点からお考えをお聞かせください。
伊藤:市場(いちば)は中間流通の部分です。市場だけで成り立つものではなくて、やはり、魚を獲る人、魚をつくる人(養殖という意味ですね)、それから、そういった魚を買ってくれる人、食べてくれる人がいてこそ、成り立つと。関わる人たち皆にとって良い姿を目指して、常に“三方良し”の精神で仕事をするのが大事だと思います。
そのためには、より高品質な商品を、より低いコストで提供することが重要です。そこが我々の生業(なりわい)ですから、いかに低コストでやれるか、一つずつチャレンジしたいと思っています。
例えば、流通段階で何ヶ所もの拠点を通じて商品が入ってくると、コストが上がるわけです。そういう面では、この豊洲市場へ一括で持ってきて、お客様が希望される荷姿、加工等もこの市場の中でできるようになれば、低コストにつながり、サステナブルになります。そういった仕事の仕方を通じて市場が進化していけたらと考えています。
花岡:流通の簡素化・合理化は、先ほどのトレーサビリティの確保にもつながるお話ですね。
花岡:僕は幼少期を海外で過ごしました。それまで生の魚を食べる文化がなかった外国にも寿司が一気に出回って世界の食べ物になり、日本食ってすごいなと幼い頃に思ったものでした。

しかし、漁業関係の国際会議に行くと、日本は悪者扱いされることが今でもあります。確かに、世界各地の海で魚を獲り過ぎてきた過去があり、そういう会議に参加して日本人として残念に思うことが何度もありました。先ほどのサンマの事例でも、漁獲量が減ってしまうから価格が高くなるわけで、しっかり国際連携の上で資源管理をして安定的に供給できる海との関係性を築く必要がありますよね。
日本の人口は減少していますが、世界の人口はどんどん増えています。陸上で食料をつくるキャパシティが限られている以上、やはり、海で食料をつくる能力を増やしていくことが必須になってきます。 その中で、日本の周りには、世界の三大漁場に数えられるぐらい豊かな海があり、資源管理をしっかりしていけば魚が増えていきます。丁寧に管理され漁獲されたその魚が、日本における一人当たりの魚介類消費量を増やし、世界人口を飢餓から守り、豊かさを提供する日を、私たちシーフードレガシーは目指しています。
伊藤:なるほど。
花岡:日本の漁業や流通を含めた水産業界全体のサステナビリティを確立し、海と人とのサステナブルな付き合い方を世界に発信していく、そういうアイデンティティを日本が持てるようになりたいものです。
そのためにも、豊洲市場はアイコン的にも実際の流通においても中心だと思いますし、伊藤社長とお話していて、なおさら、その夢を実現できそうだと感じました。
伊藤:実現するためには、シーフードレガシー1社ではダメで、中央魚類だけでもダメです。やはり、この水産業に携わる人たちの多くが、同じ目標に向かって手を結んでいくことが大事です。シーフードレガシーがつくってきたその輪の中に、多くの人たちを入れていってもらいたいと思います。
伊藤晴彦
1967年東京都生まれ。日本大学農獣医学部在学中に米・アラスカ州のアラスカ大学で一年間サケの遡上を学ぶ。卒業後、株式会社ニチレイに入社、業務用冷食を担当。2000年に中央魚類株式会社に転職。2018年同社代表取締役社長に就任。大型冷蔵庫や物流センターを有する様々な企業から成るマルナカグループを傘下に収める同社の最高執行責任者(COO)として、グループ企業の連携によるシナジー効果の最適化を強く意識し、水産物を中心とした食品総合卸としての発展を目指す。
花岡和佳男
1977年山梨県生まれ。幼少時よりシンガポールで育つ。フロリダ工科大学海洋環境学・海洋生物学部卒業後、モルディブ及びマレーシアにて海洋環境保全事業に従事。2007年より国際環境NGOで海洋生態系問題担当、キャンペーンマネージャーなどを経て独立。2015年7月株式会社シーフードレガシーを設立、代表取締役社長に就任。国内外のビジネス・NGO・行政・政治・アカデミア・メディア等多様なステークホルダーをつなぎ、日本の環境に適った国際基準の地域解決のデザインに取り組む。
取材・執筆:井内千穂
中小企業金融公庫(現・日本政策金融公庫)、英字新聞社ジャパンタイムズ勤務を経て、2016年よりフリーランス。2016年~2019年、法政大学「英字新聞制作企画」講師。主に文化と技術に関する記事を英語と日本語で執筆。
写真:帆刈一哉










































-2048-×-1218-px-1-1024x609.png)


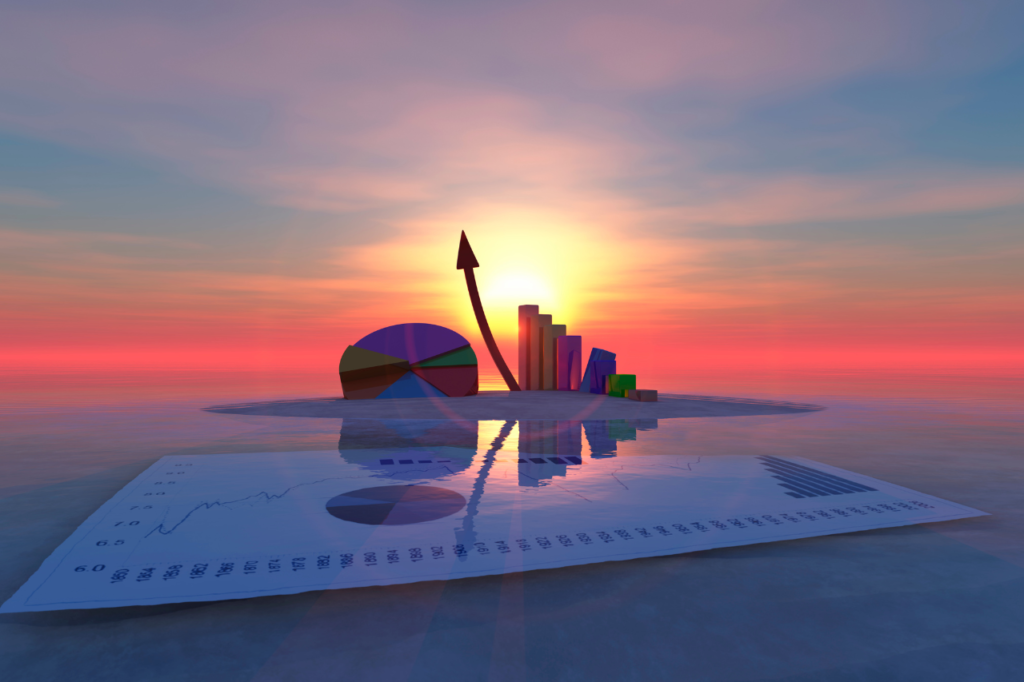










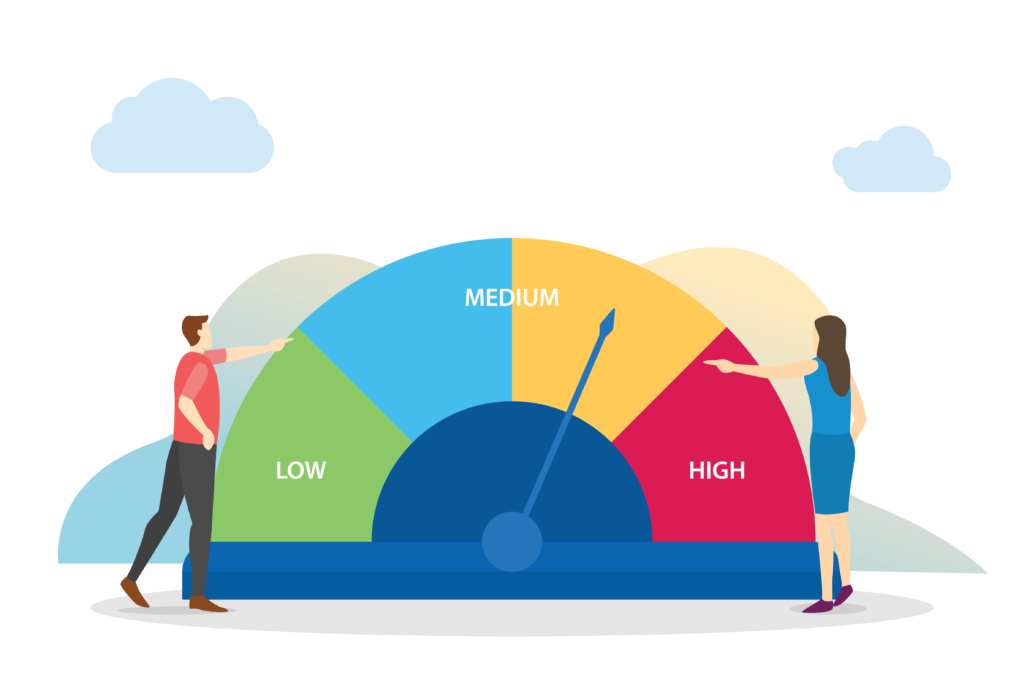

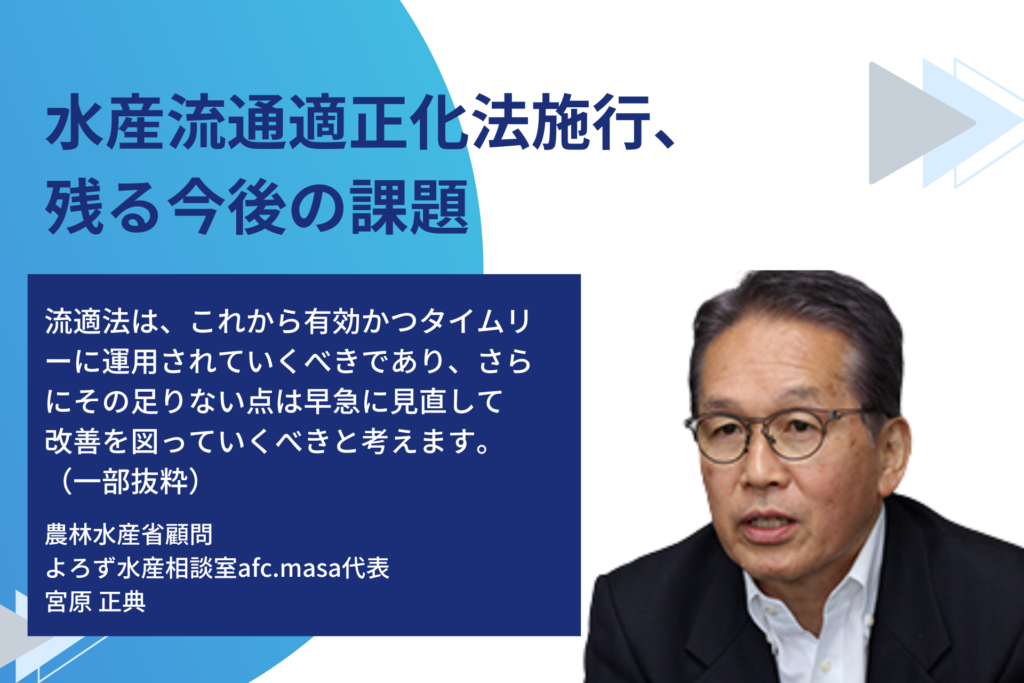











-2560-×-1536-px-1024x614.png)































.jpg)