TAC(漁獲可能量制度)
「漁獲可能量(TAC,Total Allowable Catch)制度(以下TAC)」とは、魚種ごとの漁獲可能量を科学的に測定し、それによって漁獲量の上限を決めることをいいます。獲りすぎを防ぎ、資源維持と回復をはかることで水産資源を保全し、結果として水産業を守っていくことを目的としています。
総量は毎年検討され、水産庁によって決定されます。現在、日本でTACが設定されているのは8種、クロマグロやサンマ、スルメイカなどがあります。今後、漁業法の改正を受けてブリやサワラなどが追加され、漁獲量の8割までTAC管理魚種が拡大される予定です(2021年6月時点)。
海洋資源と水産事業者の経済性、その両方を守っていくために。今後の動向が注目されています。
【参考】
水産庁 TACについて(詳しくはこちら)
TACに関する記事
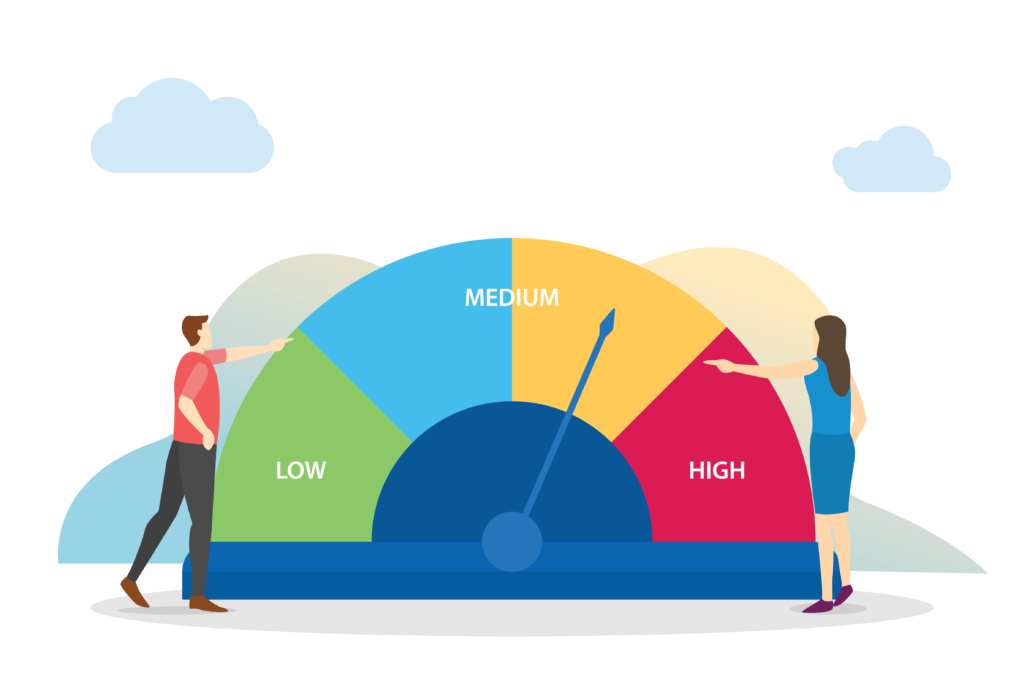
持続可能な水産資源利用と科学的な資源管理
コラム

これだけは知っておきたい改正漁業法のポイント
コラム
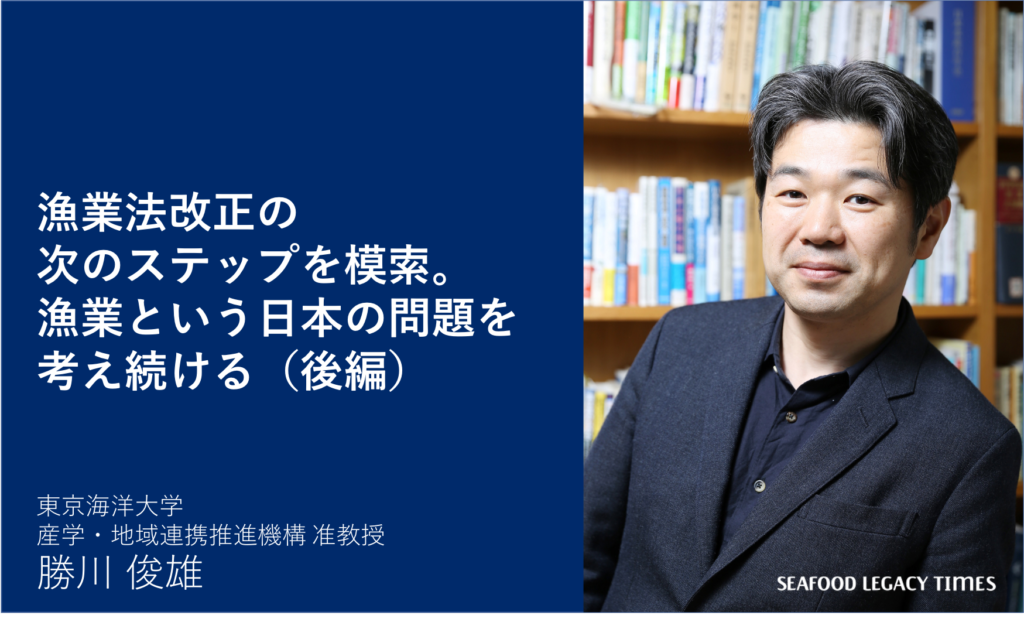
漁業法改正の次のステップを模索。漁業という日本の問題を考え続ける(後編)
インタビュー
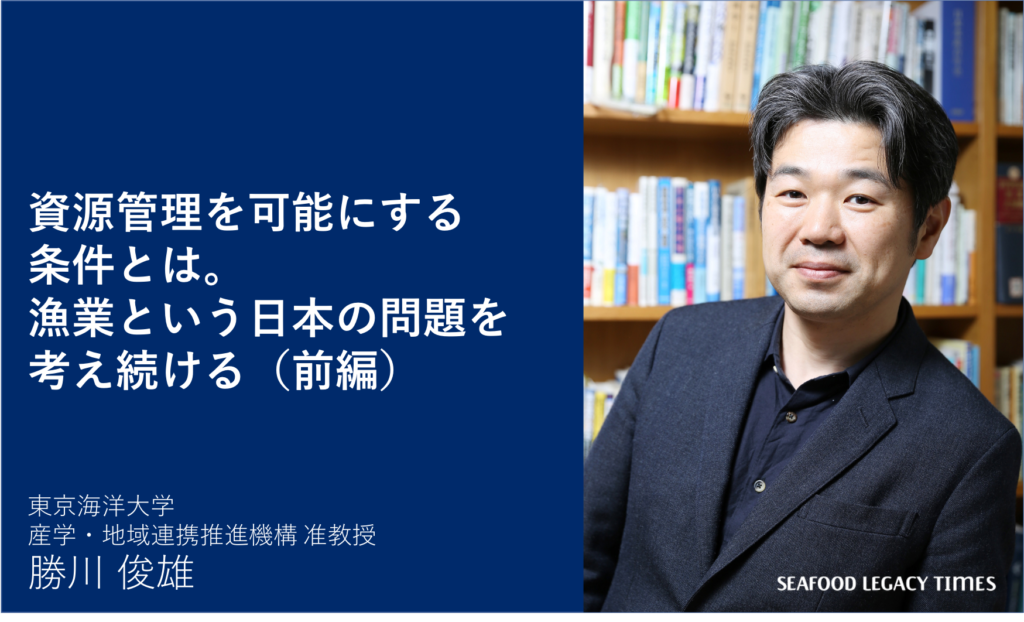
資源管理を可能にする条件とは。漁業という日本の問題を考え続ける(前編)
インタビュー
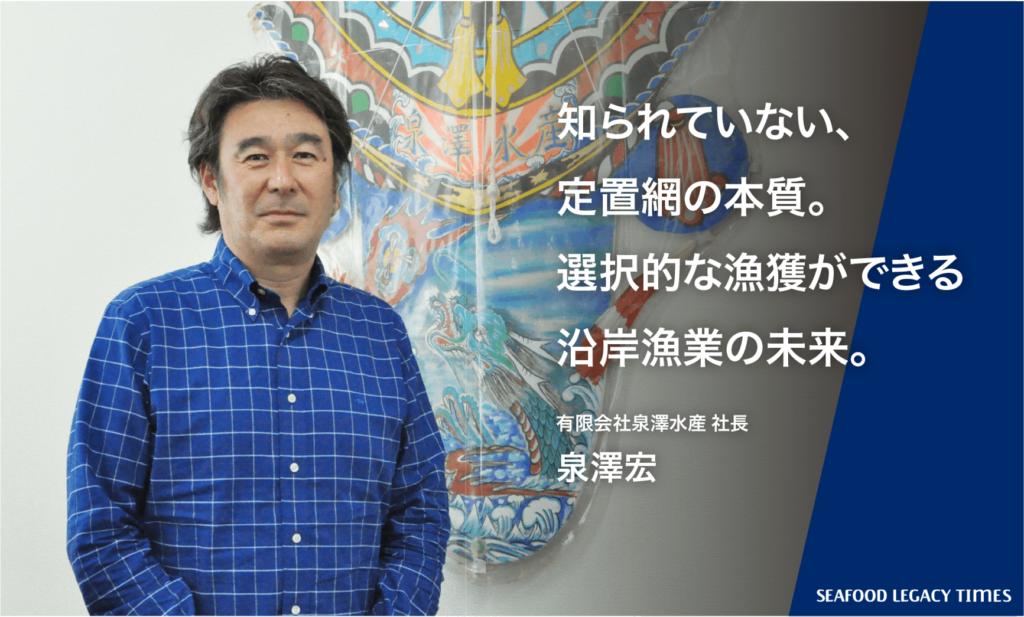
知られていない、定置網の本質。選択的な漁獲ができる沿岸漁業の未来。
インタビュー
